公共工事の利益率を最大化するための秘訣とは?
公共工事の利益率を最大化するためにお困りではありませんか?中小建設会社の経営者様、精確な見積もりが重要であることは分かっていても、利益率が低くて悩むことも多いはずです。本記事では、適正な利益率を把握し、他社との差別化を図るためのヒントをお届けします。これを読み進めれば、確実にあなたの経営に役立つ情報が見つかるでしょう。
公共工事における利益率の平均と目安

公共工事における利益率は、「公共=安定収益」と思われがちですが、実際には入札競争によって利幅が圧縮されやすいのが現実です。特に最低制限価格や低入札価格調査といった制度が存在しているとはいえ、多くの案件で落札価格が制度上の下限ギリギリに集中する傾向があります。そのため、建設業界全体で語られる「平均的な利益率」が、そのまま公共案件でも当てはまるとは限りません。
一般的に、建設業 平均利益率として以下のような目安が挙げられています。ただし、これらはあくまで全体傾向であり、公的な一律基準ではありません。
-
粗利率(売上総利益率):18〜25%前後。完成工事高から工事原価を引いた額をベースに算出
-
営業利益率:5〜10%程度。ただし、間接経費比率や規模感によって大きくブレる
-
経常利益率:2〜7%程度。営業外損益次第で上下するため要注意
-
ROE(自己資本利益率)/ROA(総資産利益率):参考指標だが元請・下請構成比や設備投資状況でばらつきあり
では、自社はどこを目指せばいいのか?答えは「自社過去データを基準にすること」です。たとえば完成工事高と原価の実績から自社なりの粗利率幅を把握し、そこから営業経費・間接費を割り戻して営業利益目標ラインを決める方法です。同じ業種・同じ地域でも現場規模や使用資機材、人員構成によって構造コストが違うため、「隣の会社」の数値より、自分たちに合った目標値設定こそが収益改善への一番の近道になります。
公共工事の利益率を正確に計算する方法

公共工事の利益率を把握するには、単なる売上高や収支の増減だけでは不十分です。具体的な数字をもとに、複数の指標を組み合わせて実態を分析する必要があります。代表的な指標として、粗利益率・営業利益率・経常利益率に加え、財務分析で活用されるROEやROAといった視点も押さえておくべきです。
以下は各種「利益率」の代表指標とその計算式です。公共工事では「完成工事高(売上)」と「工事原価」が基準になり、それに応じた適切な使い方が求められます。
| 指標名 | 計算式 | 意味 |
|---|---|---|
| 粗利益率(売上総利益率) | (完成工事高-工事原価)÷ 完成工事高 ×100 | 案件単位での直接収益性(材料費・外注費除いた余力) |
| 営業利益率 | 営業利益 ÷ 完成工事高 ×100 | 間接費(人件費や販管費)まで含めた会社本来の儲け力 |
| 経常利益率 | 経常利益 ÷ 完成工事高 ×100 | 借入金利など営業外損益影響も踏まえた全体収益性 |
| ROE(自己資本利益率) | 当期純利益 ÷ 自己資本 ×100 | 出資者が得られたリターン水準を見る財務指標 |
| ROA(総資産利益率) | 当期純利益 ÷ 総資産 ×100 | 会社全体の効率性・運営力を評価する尺度 |
公共工事でまず分析に使うべきは「粗利益率」と「営業利益率」です。特に赤字受注リスクの有無を判別するには、「完成前積算」と「実行予算」でこの2つを毎回モニタリングしておくことが最重要になります。ROEやROAはあくまで年間単位などで全体俯瞰したい場合に補助的に活用し、自社内でどこまで改善余地があるか戦略検討に役立てていくとよいでしょう。
公共工事の利益率が低くなる主な要因

公共工事の利益率が民間工事に比べて低くなりやすい背景には、複数の構造的・実務的課題があります。どんなに丁寧に施工しても、これらの要因が積み重なることで赤字リスクは現実化しやすくなります。以下に、主要な原因を5つピックアップし、それぞれが収益性をどう圧迫するかを整理します。
-
建設資材や原材料費の急騰
鋼材、木材、砕石、アスファルト乳剤など、多くの資材が需給バランスや為替の影響で不安定です。予定価格算出時と調達時で価格差が大きい場合、その分利益を圧迫します。 -
労務・外注費の上昇
技能労働者不足による日当単価の増加や重機オペレーター等への外注費上振れは不可避で、人件費計上が甘いとそのままマイナス要因になります。 -
入札制度の構造と競争の激化
最低制限価格(または低入札価格調査)制度自体は存在しますが、多くの場合それに近い額で落札されるため、そもそも利幅を取りづらい設計になっています。特に同一ランク多数企業による競合で顕著です。 -
工期増加による追加コスト
雨雪など気象条件や発注者側工程変更などで日程延長となれば、現場拘束人件費・仮設維持費等で予期せぬ負担増につながります。 -
手元管理の甘さ(積算・実行予算・進捗把握)
積算見積段階で原材料単価や人件コストを正確に盛り込めておらず、それを随時修正できる実行予算との乖離が出る例も多いです。また現場損益判断タイミングが遅れる場合も赤字転落リスクとなります。
こうした要因は一つひとつ見ると避けられないようにも思えますが、事前準備と管理体制次第では一定程度抑えることは可能です。したがって、各要因への対応策(契約前積算精度向上、工程計画ゆとり確保、月次収支チェック体制構築など)を自社内で具体的に設計しておくことが、中長期的な利益確保には欠かせません。
公共工事で適正な利益率を保つために必要な原価管理とは

公共工事の利益率を守るうえで「原価管理」はまさに収益維持の土台です。予定価格制度や最低制限価格制度のもとでは、利幅が限定的になりがちですが、適正な原価把握と対策があれば赤字受注は回避できます。重要なのは“感覚”ではなく、数字に基づいた進行管理です。その中心にあるのが「実行予算」と「工事台帳」です。
以下に、公共工事で利益を維持するための原価管理手法を5つのステップで解説します。
-
実行予算の事前作成と目標利益率の明示
積算後すぐに案件別の実行予算を作成し、人件費・材料費・外注費・間接経費などすべてを内訳化します。この時点で最終的な目標利益率(例:営業利益3%以上)も定め、各カテゴリごとのコスト上限ラインを見える化します。 -
工事台帳を使った各費用情報の記録・比較
現場ごとの毎月発生する支出(仕入・支払)や発注内容をすべて工事台帳に記録します。これは単なるエクセル集計ではなく、「項目別×月次」の形式で設けられることが望ましく、取引先ごとの単価変動も確認できるよう整備する必要があります。 -
差異が出た際の要因分析(実績・積算差)
当初設定した見積額と実績値との差異が出た場合、その理由(物価変動/労務手配遅れ/施工方法変更等)を即時フィードバックしてください。ここで属人的な判断ではなくログ付きで根拠整理しておくことで次工程にも展開可能になります。 -
下請契約・外注費交渉の妥当性確認
協力業者との契約時には積算どおりか、それとも調達コスト増減があるか精査しましょう。「予定より高かった」で終えず、その金額差分が全体粗利構造へどう影響するかまで評価しない限り、本来取れるはずだった営業利益まで失われかねません。 -
月次決算による早期是正措置の実施
一度完成後に損益を見るのでなく、進行中から毎月ベースで粗利率・総コスト推移を見ることがポイントです。仮設費や販管費も含め想定よりオーバーしている場合は早めに内訳見直しと人員再配置などによる対処パターン構築へつなげます。
特定スタッフ任せでは情報偏在しやすく対応遅れになりがちです。その意味でも属人管理から脱却し、全部署横断型で「同じフォーマット」「同じ分析フロー」で回す原価KPI体制づくりこそ、中長期的収益維持への第一歩となります。
公共工事の利益率を改善する7つの具体策
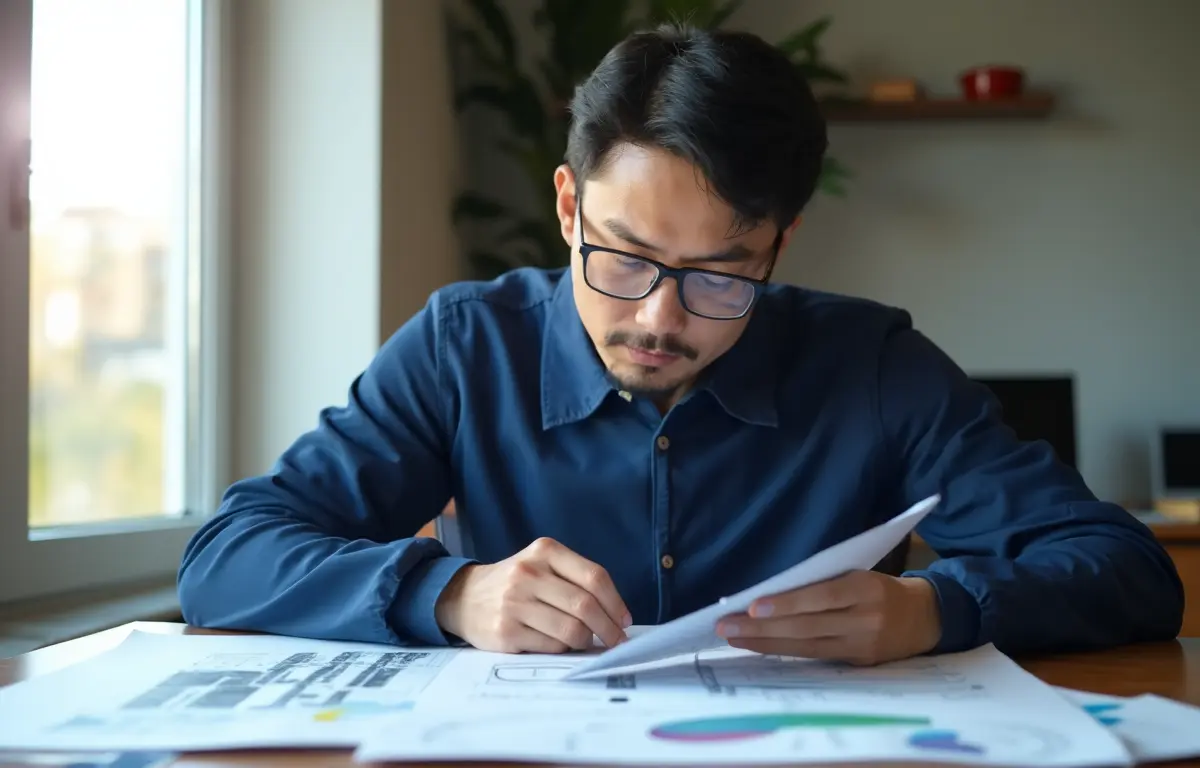
公共工事における利益率が低いまま放置されると、企業運営は資金繰り・人材確保の両面で不利になります。特に入札価格が制度上の下限付近に集中する現状では、「なんとなく積算」「流れで受注」では赤字リスクが高く、自社を守るには収支構造を主軸にした経営へ切り替える必要があります。
公共工事 利益率 の改善には、以下7つのステップによる同時並行的な進行が不可欠です。
-
自社の工事ごとの収支を棚卸し
案件別に粗利ベースでの原価率・利益率実績を把握することで、どこで損失が出やすいか可視化されます。完成工事高と工事原価、外注費、人件費の記録付き台帳分析から始めてください。 -
理想利益率を設定し、見積に反映
一律「○%が理想」ではなく、自社過去5案件以上から平均粗利・営業利益ラインを抽出したうえで、それを超える設定値(例:粗利率22%、営業利益4%)を積算基準とします。 -
不必要なコストの洗い出し(材料、外注)
提出見積前段階で資材単価・施工方法・再委託内容など細部まで調査。特定取引先で価格交渉せず継続している場合は機械的発注となっている可能性があり要見直しです。 -
工期短縮・施工手順最適化による原価効率化
少人数同時施工や先組体制など現場オペレーション面にも一貫管理意識を導入。仮設費や人件日当累計額負担軽減につながります。 -
定例会議や進捗共有で部門間連携強化
見積担当→現場管理→経理処理への情報伝達ロスによって原価超過が起きることも少なくありません。メールベースではなく週1回10分でも共有時間を設ける習慣づけが鍵です。 -
月次での集計と見直しによるPDCA運用
「完了後に気づいた赤字」にならないためには、粗利変動の兆候(増加した仕入/余剰労務時間)を月ごとに確認→即修整できる会計サイクル整備が必要です。 -
経営層が収支・指標を理解し意思決定強化
ROE/ROAなど抽象数値だけでなく、「今月どこの原価科目が崩れているか」を把握できてこそ早期対応できます。経営者自身も台帳フォーマット確認や数値レビュー対象になるべきです。
これら7施策は順番通り進めるものではなく、“同時併用”によって初めて効果が出ます。「自社の実態」を起点に数字根拠ある経営判断へ移行してこそ、本質的な利益率 向上策 として機能します。
デジタル化による公共工事の利益率向上戦略
公共工事で確実に利益を確保するには、属人的・手作業中心の原価管理から脱却する必要があります。ここでカギになるのがDX、つまりデジタル化による原価管理体制の構築です。単なるシステム導入ではなく、「リアルタイムな収支把握」「案件別の進捗確認」「異常通知による早期軌道修正」まで実現できれば、赤字リスクは格段に減少します。
たとえば、見積時に過去工事から材料費・工期要素を引用し、自動的に暫定原価予測が組まれる仕組みを作っておけば、積算精度自体も向上します。また、現場ごとの支出が入力〜集計まで一元化されていれば、本社・経営層も即座に状況把握が可能となり、人員少ない企業でも効率よく複数案件を同時進行できます。
| 機能 | 効果 |
|---|---|
| 原価入力の自動化 | 手間削減+集計誤差低減による実績即時反映 |
| 工事別進捗のリアルタイム追跡 | 現場負担を増やさず人件費オーバー抑制に寄与 |
| 予算と実績の差異可視化 | 月次ベースでの粗利変動傾向を即検知・分析可能 |
| 異常値の早期アラート | 材料費/外注費過大など想定外コストへ即対応 |
| 過去工事実績活用による積算精度向上 | 「安すぎる受注」「高すぎる調達」を防ぐ判断材料に |
もちろん導入当初は操作教育時間や初期投資コストといった障壁はあります。しかし近年ではクラウド型ソフトや簡易操作インターフェースも普及しており、中長期的には人件費圧縮や赤字回避という形でしっかり回収されます。むしろ今後は「ITなしでは採算保障できない」時代とも言え、自社規模を問わずDX活用は公共工事 利益率 安定化への必須ステップになっています。
公共工事の利益率を上げるための具体的なステップ
公共工事の利益率を最適化することは、中小建設会社にとって避けて通れない課題です。この記事では利益率改善のための具体的な方法を紹介しました。まず、現状の利益率を正確に把握することが重要です。粗利益や営業利益率などの指標を用いて計算し、理想とのギャップを明確にしましょう。そして、資材コストや労務単価の上昇といった外部要因に対処するために、原価管理やデジタルツールによるリアルタイム管理を取り入れることが有効です。
最終的に、適正な見積もりを設定し受発注者間で協議することで、より実行可能な方法を見つけられます。具体的には、受注前に実行予算を作成し、赤字受注を事前に防ぐことが鍵です。これらの対策を講じることで、競合他社との差別化を図り、経営の安定性を高めることができます。これまでご覧いただきありがとうございました。この記事があなたのビジネスに少しでも役立てば幸いです。次はあなた自身の手で、これらの知識を活かしてみてください。


