地質調査建設業許可の取得ガイド 施工内容に応じた許可要件とは
地質調査業を始めるまたは運営する方にとって、建設業許可の取得は避けられないステップです。その過程で直面するのは、複雑な手続きや不明確な許可要件でしょう。許可取得に失敗したくない、時間やコストを無駄にしたくないという不安があるあなたに、このガイドが安心をもたらす道筋を提供します。
地質調査における建設業許可の必要性と判断基準

地質調査を行うなかで、「すべての業務に建設業許可が必要」と思われがちですが、実際はそうではありません。たとえば、ボーリングデータの解析、土質試験、報告書作成などの「施工を伴わない業務」であれば、建設業法規上の『建設工事』には当たらず、地質調査建設業許可は不要です。これはいわゆる技術コンサルタント業務に分類されるためであり、多くの純粋な地質調査会社がこの範囲内で活動しています。
一方で、「実際に穴を掘る」「地盤を改良する」「井戸を掘削する」といった“現場施工”が発生する場合は話が変わります。こうした業務は建設工事として扱われ、『とび・土工工事業』や『さく井工事業』などの各種指定業種に該当しうるため、施工内容に応じた許可要件を満たした上で地質調査建設業許可を取得しなければなりません。特に民間企業や自治体から請負契約で依頼されるケースでは、形式的にも法的要求への対応が必須となります。
判断基準としては「請負金額」と「工事内容」が大きなポイントになります。以下に整理します。
- 設計・解析・報告のみ:施工なし → 建設業許可は不要
- 試掘(手掘り・重機)を含む → 「とび・土工工事」の可能性あり
- ボーリング調査で削孔作業 → 内容によって「さく井」や「土工」に該当
- 地盤改良(薬液注入等)を含む → 工種判断次第で許可対象
- 請負金額500万円(税込)以上の場合 → 軽微な工事ではないため原則として許可必須
このように、自社の行っている施工内容と受注形態(金額規模)から総合的に判断しないと、知らぬ間に無許可状態となるリスクがあります。とくに群馬県を含む地方自治体では現場指導が厳格になっており、不適切な対応はその後の入札参加資格にも関わるため要注意です。地質調査会社側も、自身のサービス分類だけでは見落としやすいので、一度専門家による判定サポートを受けてみることも有効です。
地質調査に該当する建設業許可の業種分類

地質調査を行う企業が施工を伴う業務を受注する場合、建設業許可が必要になるケースがあります。その際、どの工事業種で申請すべきかは、実際の施工内容に応じて適切に判定しなければなりません。ここでは、地質調査建設業許可を取得する際に該当しやすい代表的な2つの工種について説明します。
とび・土工・コンクリート工事に該当するケース
現場で手掘りや機械による掘削作業を行ったり、地盤改良を伴うような作業を行う場合は、「とび・土工・コンクリート工事」に分類される可能性があります。たとえば以下のような現場調査技術(現地対応型ボーリング技術等)を含む場合、この工種での許可取得が求められます。
- 表層部または中層部までの試掘(重機使用含む)
- 薬液注入などによる地盤改良
- 土留めや仮設構造物(シートパイル・支保工)の構築
この分野では「単なる土質データ収集」ではなく、「構造物の安定性確保や施工準備」を目的とした作業かどうかが判断ポイントになります。特に公共案件においては発注仕様書から「どこまでが現場施工か」明確になっているため、それを軸として検討するとよいでしょう。
さく井工事に該当するケース
地下水位把握や岩盤層観察など、高精度のボーリング工程がある場合には、「さく井工事」に分類される可能性が高くなります。特に深井戸掘削用ボーリング技術や、大口径穿孔装置など専用機器を使う場合は、この区分で判断される傾向があります。
主な該当例としては以下のような施工があります。
- 地下水位測定・取水用井戸設置
- N値測定用穿孔(スタンダードペネトレーションテスト含む)
- 岩盤評価用深層ボーリング
これらはいずれも「単なる観測」の範囲では済まず、一定規模以上では重機搬入と連続作業工程になるため、建設業法上も“軽微”とは見なされません。請負金額500万円(税込)以上となる場合も多いため、「さく井」で許可取得しておくことで安心して案件受注につながります。
なお、「さく井」と「とび・土工」のどちらにも関わる複合的な内容の場合、それぞれ別途で要件確認しながら両方登録しておくことも実務上一般的です。これは地質調査建設業許可取得後、想定外の規模拡大時にも柔軟対応できる準備となります。
地質調査会社が取得すべき建設業許可の種類と区分

地質調査建設業許可を取得する際、まず判断しなければならないのが「知事許可」か「大臣許可」かという区分です。これは「工事する地域」でなく、「営業所を置いている都道府県の数」で決まります。たとえば、群馬県内にしか営業所がなければ群馬県知事許可になります。他方、群馬と埼玉にそれぞれ営業所がある場合は、大臣許可が必要になります。
次に確認すべきなのは「一般建設業」か「特定建設業」のどちらかです。これは工事を下請に出す金額で判定されます。下請への発注が5,000万円(税込)以上となる工事を受注する場合には、「特定建設業許可」が必要です(建築一式の場合は8,000万円以上)。通常の地質調査施工(掘削や井戸ボーリングなど)は元請けで完結する小規模なケースも多いため、一般建設業で対応できることも少なくありません。
では地質調査を行う際にどのような判断になるのかと言えば、例えば小規模な土壌ボーリングや表層掘削だけならば、一つの都道府県で活動し、下請なしで業務するケースなら「知事+一般」で十分対応可能です。しかし、多数地域で活動したり、多額の重機作業を伴うような地下水評価・薬液注入工事などになると、「大臣+特定」を選ぶ必要があります。この判断によって後々 認可範囲や案件受託可能性も大きく変わります。
| 許可種類 | 判定基準 | 内容の特徴 |
|---|---|---|
| 知事許可 | 営業所が1都道府県のみ | 地方中心・限定エリア向け |
| 大臣許可 | 2つ以上の都道府県に営業所あり | 全国展開・応札範囲拡大向け |
| 特定建設業(vs. 一般) | 下請総額5,000万円超(建築一式除く) | 資本力証明や施工能力要件あり |
このように、自社の施工内容と展開地域をよく精査した上で、それぞれ最適な地質調査建設業許可区分を決めることが重要です。誤った選択は後から訂正や区分変更が必要になり、「実務停止」が生じるリスクもあるため、経験豊富な専門家と慎重に検討するべきです。
地質調査における建設業許可の取得要件

地質調査業者が施工を伴う業務で建設業許可を取得しようとする際には、主に4つの「許可要件」を満たす必要があります。
まず経営体制の面では、従来義務だった「経営業務管理責任者(いわゆる経管)の必置制度」は撤廃され、現在は常勤役員等に適切な経験と能力があれば足ります。つまり、5年以上などの形式的な条件から、「実際にどれだけ事業を担って管理していたか」が重視されるようになりました。この変更により、中小や新興の地質調査会社でも参入がしやすくなっています。
次に技術面では、各営業所ごとに「技術者」の配置が義務となります。これは業種ごとに指定された資格や実務経験によって認定される仕組みであり、「1級・2級土木施工管理技士」や対応分野の「技術士」などが代表例です。一方、「地質調査技士」や「RCCM」は原則として建設業法上の専任技術者とは認められないため注意しましょう。判定は地質調査建設業許可の根幹であるため、不安があれば事前に専門家認定について相談することをおすすめします。
| 要件カテゴリ | 代表書類 | 留意点 |
|---|---|---|
| 経営体制(適正管理能力) | 略歴書・経験証明 | 常勤役員による実績年数・内容で判断 |
| 専任技術者要件 | 資格証明・実務証明書類(契約書等) | 対象工事との整合性を詳細確認 |
| 財産的基礎(自己資本等) | 貸借対照表・残高証明・融資承諾書など | 自己資本500万円以上が原則目安 |
| 誠実性・欠格事由なし | 誓約書・登記事項証明書 等 | 暴力団排除条項、不正行為歴確認も含む |
| 営業所確認資料 | 賃貸借契約書・写真 等 | 物理的な拠点確保と常駐人員配置必要 |
| 社会保険加入状況 | 加入証明控え一式(健康保険等) |
地質調査会社が建設業許可を取得するまでの手続きの流れ
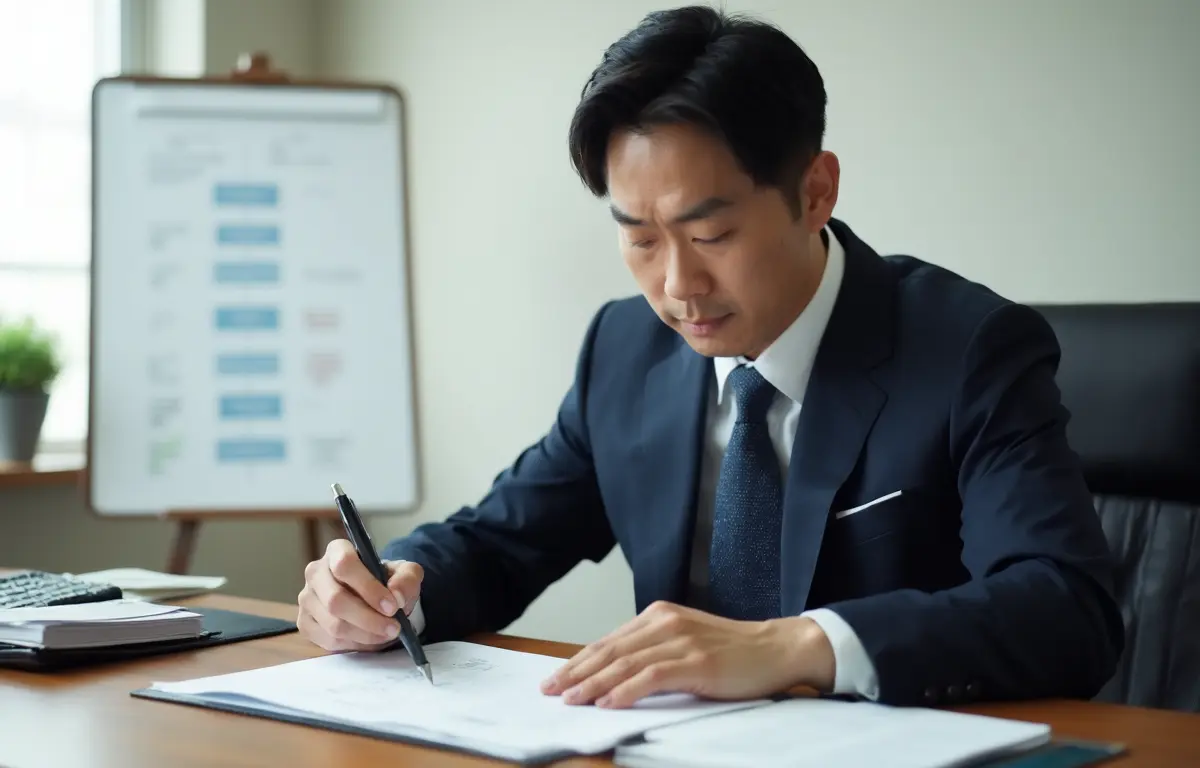
地質調査建設業許可を取得するには、業種選定から申請後の審査に至るまで、いくつかの明確なステップがあります。以下では実務的な観点から、許可の取得プロセスと注意点を5段階に整理して説明します。
処理期間は通常1か月前後ですが、書類不備や資格要件の不足があると補正対応で長引くことも多く、「事前準備」が全体のスムーズさを左右します。とくに建設業許可申請方法として最も基本的なのは「提出書類の精度」を高めることです。
- 事前相談・要件チェック
どの工種(例:とび・土工/さく井)で許可を取るべきかや、常勤役員や専任技術者が要件を満たすかどうかを確認します。よくある落とし穴は「地質調査技士」など関連資格はあるが、許可上の専任技術者資格として認められないケースです。必ず事前に該当資格と職歴証明資料を突き合わせて判断しましょう。 - 必要資料の収集
登記簿謄本、定款、営業所確認資料(写真・賃貸借契約書など)、資金証明(残高証明または金融機関書類)、経営経験や実務経験証明となる契約書・請求書類など、多岐にわたります。「直近決算2期分」と誤解されることがありますが、新規法人は開業直後でも金融証明等あればクリア可能です。 - 申請書作成と提出
各都道府県または地方整備局指定様式で一式作成し、本店所在地を管轄する庁舎へ郵送または来庁して提出します(群馬県の場合、オンライン専用ではなく郵送・来庁受付)。不備があると補正指示となり、その間審査ストップになるため正確性最優先です。 - 審査・補正対応
標準処理期間は1か月ほどですが、不備訂正や追加資料指示が出た場合さらに時間がかかります。特に多い補正理由では「実務経験年数が足りない」「契約日付や工種名不一致」などありますので、第三者視点でチェックすることが有効です。 - 許可取得後通知受領・保存
許可通知書がおりたらその写しおよび公告文面含めて社内保存し、以降5年間ごとの更新管理へ進みます。この段階では施工内容拡張や他県展開への変更届準備も検討対象になります。
なお、新規取得時には法定手数料として知事許可9万円、大臣許可15万円が必要ですが、それ以外にも行政書士報酬(おおむね15万円~20万円程度)が別途発生するため予算管理にも留意してください。この一連の手続きフローと注意点から逆算して進めれば、大きなリスクなく地質調査建設業許可まで到達できます。
許可取得後に必要となる維持管理・更新手続き
地質調査建設業許可を取得した後も、その効力は永久ではありません。まず押さえるべきなのは「許可の有効期間は原則5年間」であるという点です。つまり、満了日前に必ず〈免許更新手続き〉を行わなければなりません。更新申請には原則として現在の許可要件(経営体制・専任技術者・財産的基礎など)を引き続き満たしていることが前提であり、内容に変更があれば関係書類の添付提出も求められます。
毎年必須となるのが〈決算変更届〉であり、これは事業年度終了後4か月以内に所管庁へ届け出ることが義務づけられています。たとえ前年と数値変動が少なくても「毎年出さないといけない」という点に例外はありません。一方で、「経審(経営事項審査)」は公共工事入札のための別制度であり、更新や決算届とは無関係ですので混同しないよう注意しましょう。
実務上ありがちなのが、〈役員変更や専任技術者交代〉を届けずにそのまま運用を続けてしまうケースです。これは形式上「虚偽申請」と解釈されかねず、次回更新時に不利になる可能性もあります。また、不注意で決算変更届を期限までに提出できなかった場合でも即失効にはなりませんが、「遅延理由書」の提出や補正指導対象となるため、本来不要だった手間が発生します。こうしたリスクを避けるためにも〈許可状況の確認〉は定期的かつ確実に行い、疑問点があれば早めに〈許可取得後のサポート〉体制への相談がおすすめです。
地質調査業者登録制度との違いと併用の重要性
「建設業許可」と「地質調査業者登録制度」は混同されがちですが、全く別の制度であり、それぞれ求められる目的や役割、管轄機関が異なります。
建設業許可は、施工を含む工事(例:掘削・地盤改良・井戸ボーリング等)を他者から請け負う際に必要となる「請負工事のための許可」です。施工行為そのものを対象とした許認可制度であり、所管は国土交通省または都道府県知事です。一方、地質調査業者登録制度は、技術的信頼性と運用能力を確保するために設けられた「調査会社としての資格管理制度」であり、経済産業局または国土交通省が担当します。
たとえば自治体や大手ゼネコンのプロジェクトでは、「地質調査報告書作成」と「現場掘削作業」の両方が求められることがあります。このようなケースでは『建設業許可(施工)』と『地質調査業者登録(報告書等技術管理)』の両立が必須になることもあります。どちらか一方では発注条件を満たさない可能性もあるため、併用体制を整えることが実務的メリットとして極めて重要です。
| 建設業許可 | 地質調査業者登録 | |
|---|---|---|
| 制度の管轄 | 国土交通省/都道府県 | 経済産業局/国土交通省等 |
| 対象業務 | 施工(掘削・改良 等) | 報告書作成・試験・技術管理 等 |
| 有効期間 | 5年間(更新制) | 5年間(更新制) |
このように、「地質調査会社選び」においても、自社発注要件に対しどちらの資格保有が必要か検討しておくことが発注ミス防止につながります。
地質調査建設業許可に関するよくある質問と実務アドバイス
Q1. 個人事業でも地質調査に関する建設業許可は取得できますか?
はい、できます。建設業許可は法人・個人を問わず取得可能です。要件(経営経験・専任技術者など)を満たせば、個人でも地質調査に伴う工事について法定手続きに従い申請が行えます。
Q2. R技士やRCCMを持っていれば専任技術者要件を満たしますか?
基本的には満たしません。地質調査技士やRCCMは重要な民間資格ではありますが、建設業法上の「専任技術者」資格としては原則認められません。土木施工管理技士や該当分野の技術士での証明が一般的です。
Q3. 実務経験で専任技術者になる場合、どう証明すればいいですか?
契約書・請求書・注文書・工事写真など客観的資料によって工種対応と年数を裏付ける必要があります。ただし内容と形式が所管庁指針とずれていないか確認必須です。
Q4. 労働者派遣契約なので建設業許可はいりませんよね?
その通りです。「請負」ではなく「労働力の派遣」に該当する場合は建設業許可の対象外です。ただし、実際には請負風を装った派遣形態(偽装請負)となっている例もあるため契約形態の正確な分析が重要になります。
Q5. 許可要件を1つでも満たしていない場合、どうすべきですか?
即時申請不可ですが、多くの場合「証明資料準備」や「外部協力(非常勤→常勤への切替等)」で対応可能なケースが多いため、まずは現状整理から始めることが勧められます。
実務アドバイス(補正防止・効率化)
- 実務経験証明に使える客観資料は早いうちから集めてスキャン保管しておく
- 専門資格や職歴判定について行政書士など専門家による初期診断活用がおすすめ
- 記載ミス・様式違反による補正防止には所管庁最新フォーマットで一貫作成すること
地質調査業における建設業許可取得のポイント
地質調査業を運営する上での建設業許可取得へのステップは、複雑に感じられるかもしれません。特に不明確な条件や書類準備でのミスを避けたいという思いがあるなら、このガイドで紹介する情報が役立つはずです。この記事では、地質調査目的のボーリング工事と建設工事目的の場合の許可要否、必要な手続きや登録制度の要点を詳しく取り上げました。
あなたが直面している許可取得の複雑さや不安を払拭し、スムーズな許可取得をサポートするための助けになれば幸いです。今後ともさまざまな情報をもって、あなたの事業が円滑に進むことを願っています。연락åde


