宅建業と建設業許可の違いと相乗効果を理解し、事業を拡大しよう
あなたは不動産や建設業界で事業を展開し、さらにビジネスの幅を広げたいと考えていますか?「宅建」と「建設業許可」の違いに頭を悩ませ、どちらが自分の事業に最適なのか、また両方取得すべきなのか迷っていませんか?この記事を読み進めることで、それらの疑問が明確に解消され、申請手続きをスムーズに進めるための具体的なステップが見えてきます。
宅建業免許と建設業許可の違いと関係性

宅建業と建設業は、似ているようで実は制度も目的も明確に分かれている別々のライセンスです。簡単に言うと、不動産を「売る・貸す・仲介する」には《宅建業免許》が必要、建物や設備を「作る・直す・請け負う」には《建設業許可》が必要になります。
たとえば土地を仕入れてマンションを建てたい場合、単に工事ができるだけでは完結しません。土地の購入や販売仲介には宅建業免許がなければ違法取引となります。一方、不動産会社が自社所有の土地に新築ビルを建てたい場合、「工事総額」が軽微な金額(500万円未満など)を超えるなら、やはり建設業許可が求められます。このように両者の境界線は明確ながらも、実務上では密接につながっているんです。
以下の比較表で、それぞれの役割・制度のポイントを確認しておきましょう。
| 分類 | 宅建業免許 | 建設業許可 |
|---|---|---|
| 主な業務 | 不動産売買・仲介 | 建築工事の請負 |
| 必要な人員 | 専任の宅地建物取引士 | 専任技術者、経営業務管理体制 |
| 許可/免許期間 | 5年 | 5年 |
| 管轄官公庁 | 都道府県知事または国土交通大臣 | 都道府県知事または国土交通大臣 |
二つのライセンスを連携させるメリットは非常に大きいです。
例えば一連流れ「土地取得 → 自社施工 → 販売 or 賃貸」まで自社でワンストップ対応できれば、外注コスト削減だけでなく品質コントロールもしやすくなります。加えて、「経審」においても兼業売上(Y評価)としてプラスに働く可能性があります。
だからこそ、「宅建と建設業は別物」と切って考えるよりも、「どう組み合わせれば効果的か」という視点が重要なんですよ。
宅建業と建設業の兼業メリットと経営効果

宅建業と建設業許可を両方取得し、組み合わせて運用することは、単なる法的対応に止まらず、大きな経営メリットにつながります。
たとえば、自社で土地を仕入れて、そのまま自社で施工した新築住宅や賃貸物件を販売・運用するという一貫体制が可能になります。
この流れでは、外部発注が不要になるぶん中間マージンが発生せず、受注から販売までのスピードも向上します。
また、それぞれの顧客対応でも、「土地探しだけなら宅建業」「リフォームだけなら建設業」のように分断されることなく、顧客ニーズに対してワンストップで提案できる点が大きな武器です。
さらに、売上面でも統合効果があります。
経営事項審査(経審)においては、不動産(≒宅建)部門の売上は“兼業売上”として「Y評点」の算定対象となりますので、請負工事だけでは評価が伸びにくい企業にも加点要素として有利にはたらく可能性があります。
以下のような複数メリットを生む理由から、多くの地域施工会社や地場不動産会社がこの形態へ移行・検討しているわけです。
- 自社施工案件の土地取得から販売まで一括管理できる
- 顧客ニーズへの柔軟な対応が可能
- 売上構成の多角化による安定経営
- Y評点の加点対象となりうる
- 外注コストの削減
- 社内リソースの有効活用
ただし、このような兼業運営には、それぞれ規定された人員要件・事務所要件・専任性などを的確に満たす必要があります。
特に群馬県内では実務審査も丁寧に行われるため、「営業所レイアウト」「帳簿管理体制」「兼任スタッフ配置」が制度上問題ないかどうかを事前戦略として明確化しておくことが最重要となります。
宅建業免許および建設業許可の取得条件と要件の違い

宅建 建設業 許可を両方取得して事業を展開するには、それぞれの制度が求める要件と配置人員の条件を明確に把握しておく必要があります。
まず、宅建業免許に必要な要件は次の通りです。
- 専任の宅地建物取引士を1名以上配置(原則として正社員)
- 独立性・専用性を備えた事務所(180cm以上のパーティションによる区画が望ましい)
- 欠格事由に抵触しない法令遵守および素行履歴
次に、建設業許可を取得するためには以下のような要件が課されます。
- 業種ごとの専任技術者を常勤で配置
- 経営業務の管理体制:常勤役員または直接補佐する者による体制整備
- 500万円以上の自己資金または資本金など、一定水準以上の財務基盤
これら両制度とも、「専任性」「常勤性」が厳密に審査されます。
たとえば、1人で宅建士としても専任技術者としても名義登録したいと思っても、実際には同一時間帯に両方の職責で“常勤かつ専念”していることが求められるため、実務上は兼務がかなり困難です。形式的な肩書だけではもちろん不許可になる可能性が高く、どちらにも支障なく従事できる配置計画が必要になります。
特に群馬県などではこの「専任」が極めて実質的に審査される傾向なので、二つの資格要件を持ちたい場合は、それぞれの職責に対し別々の人物を配するかどうか慎重な検討と事前協議が不可欠です。
また、「自社施工にも関わらず宅地販売だけ先行したい」など片側だけで走り出すケースでも、該当行為ごとに建築 許可・宅地 建物取引業免許それぞれ個別基準がありますから、その都度チェックリスト的な確認作業は避けられません。
不動産会社が建設業許可を取得する際の申請手順と費用・期間

不動産業者が宅建 建設業 許可 の両方を取得して一貫体制を構築するためには、スムーズな申請準備と費用感の把握が重要です。
ここでは、建設業許可を新たに取得する手順と、それにかかる費用・時間をステップ形式で整理しています。
建設業許可取得の流れ(知事許可の場合)
- 事前相談
都道府県の建設業担当部署や行政書士に相談し、必要要件(体制・人員など)の充足状況を確認します。特に経営業務の管理体制や専任技術者について事前チェックが必須です。 - 必要書類の準備
- 経営業務管理体制に関する証明書類(役員履歴、補佐者の職歴など)
- 専任技術者の資格証明または実務経験証明(最も時間がかかる)
- 財務諸表や社会保険加入状況など基本台帳情報
- 申請書提出
書類一式を都道府県庁または行政窓口へ提出します。近年では電子申請への移行も進んでいますが、一部紙ベースで対応する自治体も多いため確認が必要です。 - 審査と補正対応
提出後は平均1〜2ヶ月程度で審査されます。不備や追加資料要求があれば速やかに補正対応しないと審査期間が延びることもあります。 - 許可証交付
審査完了後、知事名義で「建設業許可通知書」が発行されます。この時点から正式な工事受注活動が可能になります。
費用・期間まとめ
| 手続き項目 | 金額の目安 | 所要期間 |
|---|---|---|
| 建設業許可(知事)申請 | 約9万円 | 約2ヶ月 |
| 宅建免許申請 | 33,000円 | 約1~2ヶ月 |
| 宅建保証協会加入費 | 60万円(本店)+入会費 | 手続き後すぐ |
同時進行による効率化ポイント
宅建 建設業 許可 の両方を並行して取得する場合は、「人員計画」「社内常勤性」「営業所レイアウト」の整合性確保が不可欠です。各制度で共通検討される項目(例えば専任性や独立したオフィス空間)が重複するため、一括設計すれば、二度手間なく効率的なスケジューリングが可能になります。
群馬県など実地審査に力を入れている地域では特に、有資格スタッフや配置計画について早期段階から行政側へ相談しながら設計したほうがスムーズです。
専任技術者と専任宅建士の兼務リスクと注意点
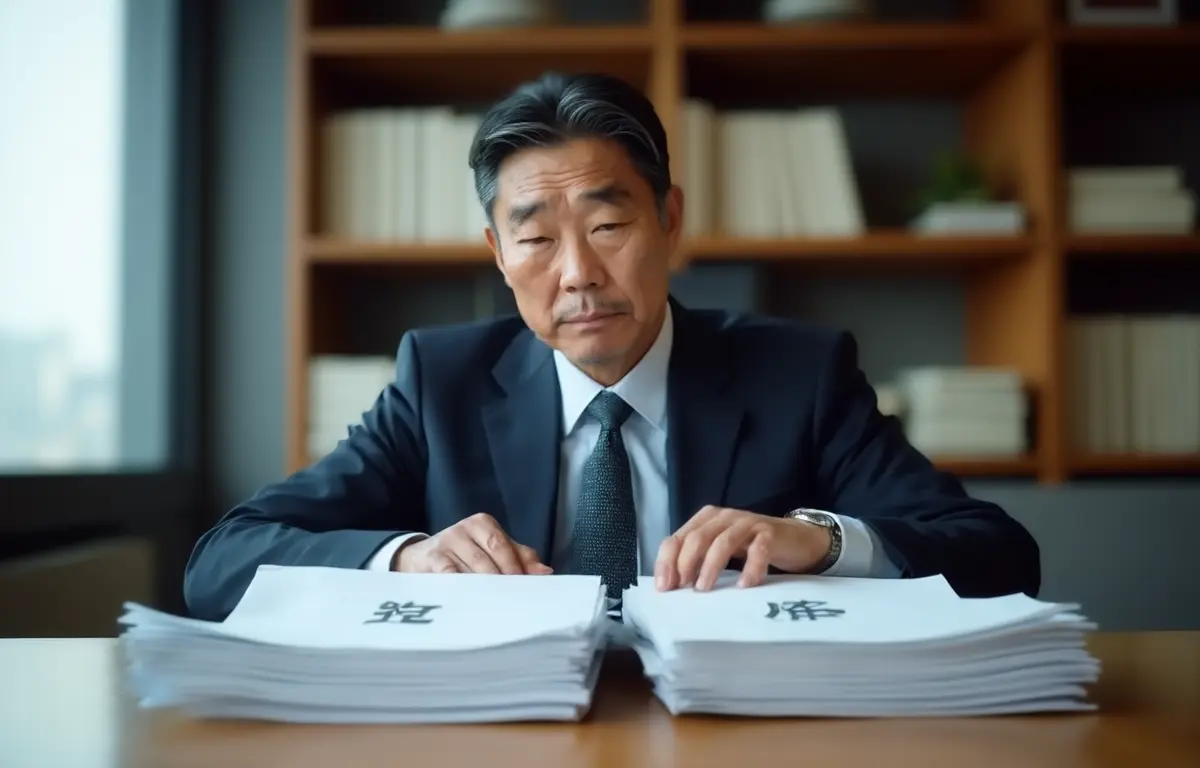
宅建 建設業 許可 の両方を取得した上で、一人のスタッフが「専任技術者」と「専任宅地建物取引士(宅建士)」を兼ねられないか?という疑問をよく受けますが、結論から言うと可能です。
原則として、これらは兼務できません。しかし、**同一法人・同一場所(同じ建物内)**で、業務量を考慮して専任性が問題ないと認められる場合に限り、兼務が許可される場合があります。
例えば、建設会社の代表者が宅地建物取引士の資格も持っている場合、同一の事務所で両方の業務を兼ねることは可能です。ただし、厳密な判断は個別のケースや都道府県によって異なるため、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
建設業者が宅建業を兼業する際の事務所と人員配置の注意点
「宅建 建設業 許可」を両方持って事業を展開しようとする際、事務所や人員配置には非常に細かな規定があります。
特に宅建業では、“事務所の専用性・独立性”が審査の重要ポイントになります。建設業との兼用も不可能ではありませんが、基本的には機能別に物理的な区分が必要です。
たとえば「自宅兼事務所」や同一フロアで2つの法人を運営する場合には、壁や180cm以上のパーティションで空間を明確に分け、その上で宅建・建設各業に必要な設備・標識・備品をしっかり個別化しておくことが求められます。
以下は、群馬県など実地審査が丁寧な地域で特に確認されるチェックポイントです。
- 出入口が法人ごとに分かれているか
- 机・電話回線・帳簿など、備品類の区分管理が明確か
- パーティションは180cm以上で天井まで隙間なく設置されているか
- 宅建業者票(標識)や案内看板を独立して掲示しているか
- 専任宅地建物取引士(専任宅建士)の勤務状態・出勤状況が具体的に実証できるか
仮に受付だけ共通でも、その先の説明や契約対応などで免許外職員(=無免許法人)が関与した場合、「無免許営業」と判断されるリスクもあるため、人員にも慎重な切り分けが必要です。
よって、自宅兼事務所とかワンルームオフィスだからダメ、と決められているわけではなく、問題となるのはあくまでレイアウトと運用体制。現場ごとの柔軟性はあります。
最終的には管轄都道府県による運用判断も大きいので、運用前提となる平面図やスタッフ体制表を整理した上で、申請前に行政窓口へ相談し“NGにならない構造”かどうか確認を取っておくことが確実です。
宅建・建設業許可の両方を活用したビジネス展開事例
A社のケース
都市部で投資用マンションを手がけるA社は、宅建 建設業 許可 の両方を取得し、仕入れから施工、販売、さらに賃貸までを自社内でワンストップで運用しています。
特に強みとなっているのは「一貫体制による意思決定の速さ」と「中抜きコストの削減」です。また経営事項審査(経審)では、宅建部門から発生した売上がY評点に加算され、以前より10点以上向上。これにより公共工事の指名競争にも参入できるようになりました。
B社のケース
従来は地元密着型のリフォーム専門業者だったB社。しかし近年、「空き家×中古住宅再販」に注目し、新たに宅建業免許を取得。
今ではフルリフォーム後に自社媒介・販売まで完結できるため、「施工のみ」時代と比べ粗利益率が約20%向上しました。同時に、自社物件へのリノベ提案も可能となり営業提案力も格段にアップしています。
C社のケース
C社は元々賃貸仲介や売買仲介を主とする不動産会社でしたが、新築着工数減少など市場変化を見越して建設業許可を取得。
その結果、既存顧客(地主層)から直接リフォーム・外構工事など請け負えるようになり、直近2年で営業利益が30%増となりました。「物件管理だけ」で終わらない高単価案件獲得へつながっています。
宅建 建設業 許可の違いとその活用法
不動産や建設業界でビジネスを展開していると、「宅建」と「建設業許可」という二つのライセンスの違いに直面することがあります。この二つのライセンスはそれぞれ異なる条件と用途を持ち、お互いの特性を理解することでビジネスの強化が可能です。宅建免許は不動産取引に必要な資格であり、建設業許可は建設に関わる工事を行うために必要です。それぞれの取得条件とプロセスを把握し、ご自身の事業にどちらが必要か、または両方必要か判断することが大切です。
宅建業免許には専任宅地建物取引士が必要であり、建設業許可には経営業務の管理責任者や専任技術者が求められます。これらの要件を満たしながら、不動産と建設の知識を融合させることで新たなビジネスチャンスを獲得できます。申請手続きは複雑に感じられるかもしれませんが、計画的な準備と適切なアプローチによりクリアできます。
そのためには、まずそれぞれの資格の目的や要件を十分理解し、どちらか一方または両方のライセンスを取得することがあなたのビジネスにどんなメリットをもたらすのかをよく考えましょう。この記事を通じて得た知識が皆さんのお役に立てれば幸いです。引き続き成功をお祈りしております。


