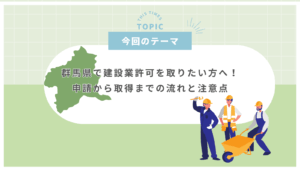建築業許可の全貌を解説!取得の流れと必要条件を完全ガイド
建築業界に飛び込む準備、または事業拡大を考えていますか?しかし、「建築業許可」を取得するための複雑な手続きや変動する法的要件に頭を悩ませていませんか?このガイドでは、あなたが直面している時間とコストの不明瞭さを解消し、スムーズに許可を取得する道を示します。
建築業許可とは何か?基本的な定義と仕組み

建築業許可とは、建設業法に基づき、建設工事(住宅の新築、道路や橋梁の整備など)を請け負って業として行う際に必要となる許認可制度です。木造の小規模なリフォームなど「軽微な工事」に該当する場合を除いて、多くの建設業務ではこの許可が義務付けられています。
建築業 許認可には大きく分けて2種類あり、「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」があります。営業拠点が1つの都道府県内だけに存在する場合は知事許可を取得しますが、複数の都道府県にまたがる場合は大臣許可が必要です。また、扱う工事の内容によって「一般建設業」と「特定建設業」に分類され、それぞれ別個の基準と条件があります。
建築業 許可証 が必要な理由
-
公共工事や大手民間案件への入札資格を得るため
-
不正施工・責任逃れ防止などの法的整合性確保
-
発注者に対する信用/実績証明として活用可能
-
更新制によって常時適格性を証明し続けられる
このように、建築業 許認可は単なる書類手続きではなく、社会的な信頼性と合法運営を確保するための重要な仕組みとなっています。
建築業許可が必要となるケースと例外

原則として、建築業許可が必要となるのは「1件の請負代金が税込500万円以上」の建設工事を行う場合です(建築一式工事の場合は1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅)。
この「500万円」というラインは材料費や労務費をすべて含んだ総額であり、消費税込みで判断されます。つまり、見積書で税込499万円ならセーフですが、これを超えると許可なしに請け負うと法令違反になります。
ただし、以下に該当するような「軽微な建設工事」では建築業許可を取得していなくても施工可能です。
許可が必要となる代表的なケース
-
住宅の新築工事(延べ床面積150㎡超)
-
500万円(税込)を超える内装リフォーム
-
公共事業(地方自治体との請負契約)
-
外壁や屋根などの大規模修繕
-
耐震補強や基礎工事の改修
| 工事の種類 | 建築業許可 必要性 |
|---|---|
| リビングの壁紙張り替え(100万円) | 不要 |
| 木造平屋住宅(120㎡)新築 | 不要(150㎡未満かつ1,500万未満) |
| 外構全体リノベーション(600万円) | 必要 |
| マンション共用部改修工事(2,000万円) | 必要 |
なお、「材料支給で労務のみ」のような契約でも、総額500万円(税込)を超える場合には許可が求められます。特に発注側から見て営利目的である限り、その形態に関係なく規制対象になりますので注意してください。
建築業許可の種類とその違い

一般建設業と特定建設業の違い
建築業許可 は、「一般建設業」と「特定建設業」の2つに分類されます。これは工事の発注金額や元請としての責任範囲によって分かれる制度です。
「一般建設業許可」は、下請けに出す金額が4,000万円未満(ただし、建築一式工事の場合は6,000万円未満)の場合に取得すればよいものです。比較的小規模な現場や、下請負人を大きく抱えないような企業が対象になります。
一方で「特定建設業許可」は、下請けに発注する金額が4,000万円以上(建築一式工事では6,000万円以上)となる場合に必要です。また、特定建設業を営む場合は高額工事を統括して管理する責任があるため、より厳しい経済的要件や技術者配置条件が課されます。
たとえば、大型商業施設の新築工事で複数社へ下請け発注を行うような元請会社は、「特定」を取得していないとそもそも契約できません。一方、リフォーム会社や小規模住宅専門の施工会社などは「一般」で運営可能です。
建設業の業種分類
さらに、 建築業許可 を取得する際には、自社が取り扱う工種ごとに申請しなければならず、日本国内ではその区分は全部で29種類あります。
この29種は、それぞれ別個に審査・登録されるため、「大工」として許可を取った会社が自動的に「内装仕上」も施工できるわけではありません。ひとつひとつ明確な条件と実績提出が求められます。
代表的な取得対象となる 建設業 許可区分 は以下の通りです。
-
建築一式工事(戸建住宅から大型施設まで全般)
-
大工工事(木材構造物・造作など)
-
内装仕上工事(クロス貼り・床材施工)
-
電気工事(照明・配線)
-
管工事(水道や空調設備ほか)
-
塗装工事(外壁・内壁ペイント等)
したがって、自社で多様な施工内容を担当したい場合、その都度対応した 建築業許可 を追加申請する必要があります。複数の種類を同時保有している企業も少なくありません。
建築業許可の取得要件と資格条件

建築業許可 を取得するためには、以下の5つの主要な条件を満たす必要があります。どれか一つでも欠けると認可されませんので、それぞれの項目をしっかり確認しましょう。
1. 経営業務の管理責任者がいること
まず、会社や個人事業として建設業を運営するうえで「経営業務の管理責任者」が在籍していることが必須です。これは、事業全体を経営的に監督できる人材であり、具体的には「過去に建設業の経営業務を5年以上経験した役職者」などが該当します。法人なら取締役クラス、個人事業主なら本人かそれに相当する補佐役であることが求められます。
2. 専任技術者が配置されていること
次に必要なのは、「専任技術者」です。これは現場監督や設計など、技術的判断を行う専門職で、自社に常勤する必要があります。その資格として有効なのが、「2級建築施工管理技士」など国家資格です。また、一定年数以上の実務経験(通常10年以上)でも代替可能なケースがあります。ただし無資格で実務だけではかなり難易度が高くなるため、多くの場合は資格取得が現実的です。
3. 財産的基礎または金銭的信用を有していること
建築業許可 条件として、最低限500万円以上の自己資本(資産-負債)があるか、それに準ずる金銭的信用状況も審査対象となります。これは突発的な事故や工事中断時にも対応できるよう、不測リスクに耐えられる財政状態かどうかを見るものです。直近決算書や通帳コピーなどで証明します。
4. 誠実性があること
過去に著しい法違反歴や工事契約上のトラブル履歴などがないことも条件となります。「誠実性」と聞くと曖昧ですが、行政処分歴・談合参加・下請企業への不払い行為などは重視されます。そしてこれらは許可更新時にも審査対象になるため、一度クリアすればよいというものではありません。
5. 欠格要件に該当しないこと
最後に、「欠格要件」に該当していないかも重要です。具体例としては破産手続き中、公序良俗違反による刑罰から5年以内などがあります。また虚偽申請や書類偽造等によって過去に許可取消処分された場合も含まれます。この判断は代表者本人だけでなく役員全員について行われますので注意してください。
建築業許可の申請方法とステップガイド

建築業許可を取得するには、いくつかの明確な手順に沿って申請を進める必要があります。以下では、建築業許可 申請 の流れを4つのステップに分けて解説します。
建築業許可 取得方法:4つのステップ
-
要件の確認
経営業務管理責任者や専任技術者が在籍しているか、財務基準や誠実性など、法律で定められた取得条件を事前にチェックします。該当しない場合は修正や体制整備が必要です。 -
申請書・添付書類の作成
自治体指定フォーマットで申請書類を作成し、各種添付書類(後述)と併せて整えます。ミスや漏れがあると予備審査で差戻しされることもあるので慎重に進めましょう。 -
予備審査(事前相談)
一部自治体では提出前に事前相談が可能です。職員による内容チェックを受けられるため、不備による再提出リスクを軽減できます。 -
正式審査&許可証交付
本申請後、管轄行政機関による審査が行われます。不備がなければ正式許可となり、「建設業 許可証」が発行されます。
必要となる主な提出書類一覧
| 書類名 | 概要 |
|---|---|
| 法人登記簿謄本 | 会社の基本情報・設立履歴を示す公的書類 |
| 経営業務管理責任者証明資料 | 過去5年分程度の建設業経営経験を示す証拠 |
| 専任技術者関連資料 | 国家資格証や実務経験証明など技術力裏付け |
| 財務諸表(直近2期分) | 自己資本額・負債状況など財務健全性確認用 |
| 納税証明書 | 法人税または所得税納付状況確認用に使用 |
| 誓約書・欠格事由確認書類 | 役員が欠格要件に該当しないことの自己宣誓文など |
所要期間と注意点
建築業許可 の 許可証取得方法 として、一連の流れには通常「1ヶ月〜2ヶ月」程度かかります。ただし、資料不備や補足説明依頼などが入った場合はさらに日数が延びることもあります。
また、多くの都道府県で「事前相談」を推奨しており、この段階でミスを防げば全体のスムーズさに大きく影響します。必ず最新フォーマットと記入例を自治体HP等から入手したうえで取り組むよう心掛けましょう。
建築業許可の費用と予算計画
建築業許可を取得するにあたり、想定すべき費用は地域や申請内容によって多少異なりますが、以下の項目で構成されるのが一般的です。特に、知事許可と大臣許可では申請手数料が大きく異なるので注意してください。
| 項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 知事許可 申請手数料 | 90,000円程度 |
| 大臣許可 申請手数料 | 150,000円程度 |
| 添付書類収集費用(登記簿謄本・証明書など) | 3,000〜10,000円前後 |
| 行政書士への依頼報酬(任意) | 100,000〜300,000円前後 |
| 合計想定コスト(平均) | 200,000〜500,000円前後 |
コストを抑えるポイント
-
自分で書類作成・提出を行えば、行政書士費は削減可能
-
書類を事前に整理し、不備による再提出リスクを最小化
-
複数業種同時取得の際は手続き一括化で経費削減可能
無駄な支出を防ぎつつも、スムーズな認可取得につなげるためには、全体像を把握しながら計画的に進めることが何よりも重要になります。
建築業許可の有効期限と更新手続き
建築業 許可証 更新 の有効期限は「5年」です。この期限までに「更新申請」を行わないと、許可は無効となり、その瞬間から無許可営業となります。
特に注意すべきは、更新申請の「期限」。建築業許可 更新 を行う際は、満了日の「30日前」までに書類を提出しなければなりません。土日祝であっても猶予はありませんので、ごく正確なスケジュール管理が重要です。
更新手続き:3つのステップ
-
更新時期の確認とスケジュール策定
満了日の半年前を目安に通知が届く場合が多いため、そのタイミングから準備開始しましょう。30日前ギリギリで動き出すと間に合わない可能性があります。 -
必要書類の収集・作成
5年前より法令変更がある場合、必要な追加書式や説明文が変わっていることがあります。最新版を確認し、正確に揃えることが大事です。 -
行政庁への提出・審査
提出後、およそ1週間〜数週間程度で審査が完了します。不備があれば即再提出となるため、事前チェックも怠らずに。
主な必要書類(例)
-
建設業許可更新申請書(指定フォーマット)
-
経営業務管理責任者および専任技術者の現在証明資料
-
直近2期分の財務諸表・納税証明書など
-
欠格要件非該当誓約書
更新期間を越えてしまった場合、新規取得扱いとなり全ステップをやり直す羽目になります。絶対に忘れないよう注意してください。
個人事業主と建築業許可:取得のポイントと注意点
個人事業主であっても、建築業許可の取得は可能です。ただし、法人よりも体制面で不利な部分があるため、いくつかの重要ポイントを慎重に確認する必要があります。
まず最初に求められるのが、「経営業務の管理責任者」の設置です。個人の場合は基本的に本人がこれを担うことになりますが、過去5年以上の建設業経営経験または補佐経験が必要です。
また、「専任技術者」も必要であり、自身に資格・実務経験がない場合には有資格者を雇用する必要があります。加えて、財産要件として自己資本500万円以上(資産-負債)が問われます。
法人の場合は会社全体の資金繰りや保証能力が比較的備わっていますが、個人では確定申告や通帳写しなど、明確な証明資料を準備する必要があります。
注意すべき4つのポイント
-
過去5年以内にきちんとした建設業経営経験があるか
-
資格を持つ技術者を自分自身または従業員から用意できるか
-
安定した財産基盤(500万円以上)を保有しているか
-
欠格要件に該当するような法令違反履歴がないか
行政書士など専門家に依頼すれば、不足書類の補完や要件整理のサポートを受けることも可能となり、審査突破への近道になります。特に初めて建築業許可 申請 に臨む個人事業主には心強いサポート体制となりますよ。
建築業許可の情報検索と事業者確認方法
建築業許可を持っているかどうかを確認したい場合、オンラインで簡単にチェックできます。特に契約前や依頼検討段階では、事前の確認がリスク回避につながります。
ここでは「建築業許可 検索」を行う具体的な手順と、実際に使える主な検索サイトをご紹介します。
建設業許可 検索:3つのステップ
-
公式WEBサイトへアクセス
国土交通省または各都道府県(例:東京都)には、建設業許可 検索システムが用意されています。 -
検索条件を入力
会社名・商号・建設業許可番号や所在地を入力。加えて、どの工種で許可を取っているか(例:土木一式、大工など)も確認できます。 -
検索結果から詳細をチェック
表示されるページで、有効な許可か/更新済みか/どの知事または大臣の認定か 等が明記されています。不正業者や期限切れに注意してください。
利用できる 主な 建設業者検索サイト一覧
| サイト名 | URL |
|---|---|
| 国土交通省 建設業者・宅建業者等企業情報検索システム | https://kensetsu.mlit.go.jp/ |
| 東京都 建設局 建設業者情報公開サービス | https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/ |
| 神奈川県 建設業者検索サービス | https://www.pref.kanagawa.jp/ |
特に「東京都 建設業許可 検索」では、申請書類PDFまで閲覧できるケースもありますので重宝します。検索時は正式社名を使うことでヒット率が高まりますよ。
建築業許可を取得するための結論
建築業界への参入や事業拡大を考える際に直面する「建築業許可」取得の複雑さは、多くの企業家にとって大きなハードルですよね。このガイドを通じて、建設業許可を取得するために必要な手続き、必須要件、また関連する費用と時間に関する不明瞭な点を明確にし、よりスムーズなプロセスへの道筋を示してきました。許可の取得は単に法的要件を満たすだけでなく、信頼を獲得し、事業の成長に大きなプラスとなることでしょう。
これからも変化する法規制をチェックしつつ、計画的に準備を進めることで、このプロセスを可能な限り効率的に進めることができますよ。このガイドが少しでも貴社の成功に役立つことを願っています。