建設業経理士資格で経営事項審査に加点される秘訣と戦略公開
中小建設会社の経理担当者や経営者の方々、経営事項審査(経審)での加点方法に悩まれていませんか?建設業経理士資格がどれほど評価に影響するのか、不安に思っている方も多いでしょう。この資格がどのように経審の評価を引き上げ、公共工事の受注増加に役立つのかを解説します。この機会に、手間やコストをかける価値があるかを知って、より良いビジネス戦略を立てましょう。
建設業経理士が経営事項審査で加点される全仕組み

経営事項審査(通称:経審)では、建設業経理士資格を有する者の在籍状況が「W点」と呼ばれる項目にて加点対象となります。W点は他の評価指標と異なり、すべての業種で共通して点数アップに寄与するため、同等規模・実績の他社との差別化に直結する重要要素です。
加点は「技術力」「経営状況」の評価に反映される仕組みであり、特に中小規模事業者の場合は、一人の建設業経理士保有でも非常に大きな得点差となって表れます。この評価は、単なる形式的な人数確認ではなく、「常勤」であることを社会保険書類等で証明できる場合に限って認定されます。
建設業経理士資格保有人数と級数による加点構造
加点される建設業経理士点数は、級数と人数によって上下し、各社の資格配置戦略によって得られるメリットも変わります。
- 2級保持者については1名につき3点が基準となり、最大で15点が一般的な上限となっています。
- 一方、1級保持者の場合には1名6点と扱われることが多く、2名配置なら12点と即戦力として強く評価されます。
- 実務上では15〜25点の間で運用されているケースも報告がありますが、大多数の場合15点を超えるには制度的・条件的裏付けが必要になります。
以下は職員数および保有資格レベルごとの想定加算シナリオです。
- 2級1名:+3点
- 2級3名:+9点
- 2級5名:+15点(上限近く)
- 1級1名:+6点
- 1級2名:+12点
- 1級3名以上:条件次第で20〜25点可能性あり
このような形で、自社内への建設業経理士資格者の適切な配置は 経営事項審査基準 に照らして直接的かつ確実な 経審加点基準 戦略になります。経験上、中小企業ほどこの戦略が顕著な成果につながりやすいので、計画的な人材育成や採用施策を検討する価値があります。
建設業経理士資格の概要と種類(1級・2級の違い)

建設業経理士資格は、建設業界における会計専門人材を育成する国家試験ですが、経営事項審査で加点対象となるのは「建設業経理士1級」と「建設業経理士2級」の2つです。
2級では主に「仕訳処理」「原価計算」など基礎的な実務能力が問われ、現場担当者や中堅社員向けとして機能します。一方で、1級は「財務諸表分析」「資金管理」「経営指標の把握」など、より高度な内容が求められるため、管理職~上位マネジメント層向けとされます。
取得難易度も異なり、建設業経理士2級の場合は合格率が約30〜40%、学習時間も150〜200時間程度で済むケースが多いです。それに対し建設業経理士1級の合格率は20%未満であり、300時間以上の学習を要することも珍しくありません。
下記に両者の違いをまとめてあります。
| 項目 | 建設業経理士1級 | 建設業経理士2級 |
|---|---|---|
| 試験内容 | 財務分析・原価計算・会計応用 | 会計基礎・原価計算基礎 |
| 合格率 | 20%未満 | 30〜40% |
| 学習時間目安 | 約300時間以上 | 約150〜300時間 |
| 経審加点目安 | 6点/人(最大25点程度) | 3点/人(最大15点程度) |
このように、どちらも建設業 経営事項 審査 に直結する有力資格ですが、自社に必要な加点幅や実務レベルに合わせて 建設業経理士資格取得 戦略を練ることが重要です。特に 経理士キャリアアップ を考えるなら、最終的には1級取得を目指す価値がありますよ。
経営事項審査と加点制度の基礎知識

建設業が公共工事を受注するには「経営事項審査」、通称「経審」を受ける必要があります。
この制度の理解(=経営審査制度理解)は、入札参加の基本中の基本です。
まず、企業の総合力を数値化して評価されます。
この点数によって、公共工事における競争入札での優劣が左右されるため、「いかに加点できるか」が極めて重要になりますよ。
以下は、経審点数制度で評価対象となる主な5つの項目です。
建設業経理士資格がどこに貢献するかも、この中から見えてきます。
- 完成工事高(X)
直近2年間または3年間平均の完成工事実績で評価され、大手ゼネコンほど得点が高まりやすい傾向があります。 - 技術職員の状況(Z)
技術職員資格や人数などによって算定。一級施工管理技士など有資格者が多いほど有利になります。 - 経営状況(Y)
総資本利益率や自己資本比率など8項目をもとに計算。財務体質や健全性が問われるエリアです。 - 財務状況解析結果(W点)
ここで建設業経理士資格者がいると加点されます。常勤証明付きで在籍していれば、1名につき最大6点(2級は3点)加算可能です。 - 法令順守・社会性等
労災保険加入率、安全管理体制、地域貢献実績など複合的要素をプラス評価する領域となります。
つまり、建設業 経理 士 経営事項 審査 において、「自社人材に何級・何人在籍しているか」でW点領域を底上げできるわけです。
このようなスコア構造を把握し、自社リソースと組み合わせた戦略的な加点対策(=経審制度知識)が中小企業でも差別化のカギになりますよ。
常勤証明と建設業経理士の加点対象条件

建設業 経理 士 経営事項 審査で加点対象となるためには、「資格を持っている」だけでは十分ではありません。
実際にその資格者が「常勤社員として在籍している」ことを明確に証明できなければ、経審加点対象にはなりません。
なぜ常勤性が必要かというと、単に資格者が籍だけ置いている状態では制度上の「人材的な即戦力」として評価されないためです。
経審制度実践の観点でも、「常勤性」は実務処理能力や組織的な会計体制構築力を示す基準になっています。
つまり、経営審査手続きで建設業経理士をW点加点項目として申請する際は、形式的な登録や派遣契約などではなく、正式に雇用して日々勤務していることを提示しないと意味がないということですね。
具体的には、以下のような書類が「常勤性」の追証資料として必要になります。※地域によってさまざまなケースがあります。
- 社会保険標準報酬決定通知書
- 賃金台帳写し
- 住民票記載事項証明書
- 雇用契約書
- 労働契約に基づく就業実績(勤怠管理記録など)
あくまで雇用形態と雇用主との実態関係が確認できればOKなので、年度途中で採用した場合でも適切な手続き・書類を揃えれば大丈夫です。
だからこそ、建設業経理士経審登録時の運用ルール・提出タイミングをきちんと把握しておくことが、中小施工会社でもスムーズに加点へつなげるカギになりますよ。
建設業経理士資格の取得方法と学習ステップ
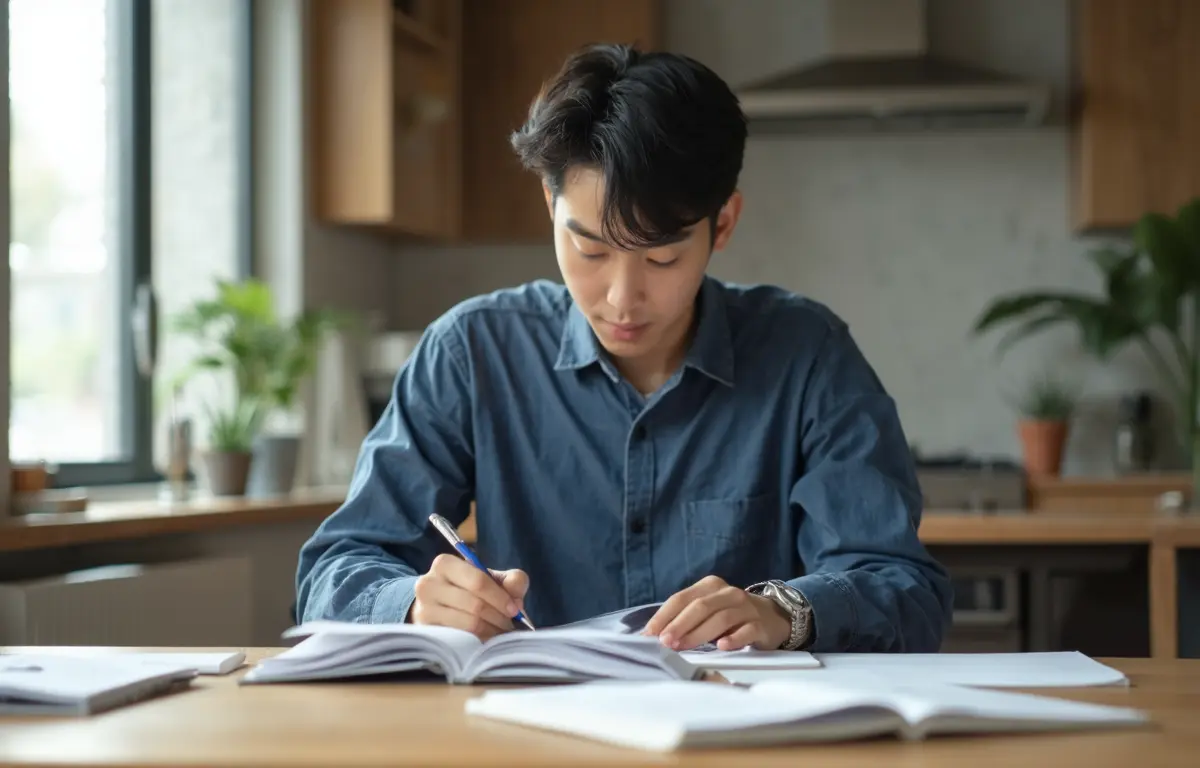
建設業 経理 士 経営事項 審査 において加点対象となる建設業経理士資格の取得方法は、大きく分けて「独学」と「講習(スクール)」の2つがあります。
2級の場合は市販テキストや過去問を活用した独学でも十分合格が狙える一方、1級になると出題範囲が専門的かつ広範になるため、対策講座を受講する受験者が増える傾向です。
まず、2級試験の出題範囲では「簿記基礎」「仕訳対応」「原価計算」など実務に直結する論点が中心です。比較的短期間(目安150〜300時間)で集中学習すれば合格も可能なので、現場経験者や他資格持ちにとっては取り組みやすいレベルですよ。一方1級では「財務分析」「会計理論」「会社法関連」など抽象度も高く、記述力や応用力が試される内容になるので、本格的な対策講義や演習問題を通じた練習が不可欠となります。
どちらの級を狙う場合でも、「何点で合格できるか」よりも、「どれだけ実務で活かせる知識か」を軸にして勉強すると定着率も変わってきます。以下に2級と1級それぞれの難易度・費用感・学習方法をまとめました。
| 項目 | 2級 | 1級 |
|---|---|---|
| 学習時間 | 150〜300時間 | 300時間以上 |
| 合格率 | 30〜40% | 20%未満 |
| 試験費用 | 約8,800円/回 | 約8,800円/回+講座費数万〜10万円超 |
| 勉強スタイル | 独学可能、市販教材多数あり | スクール・通信講座利用が主流 |
効率よく 経理士受験対策 を進めたい方には、近年人気のオンライン 建設業経理士講習 や模擬試験教材の併用もおすすめです。自社でW点加点を目指すなら、少なくとも2級は誰か1人、できれば複数名体制で取得しておくと戦略面でも大きな差になりますよ。
建設業経理士資格保持による業務上の実務効果とは?
建設業 経理 士 経営事項 審査 での加点だけが全てではありません。
建設業経理士資格を社内に持つことは、日々の経理実務面でも明確な効果を発揮します。
まず、建設業特有の複雑な会計処理や原価管理に熟練しているという点で、資格保有者は「その現場を理解した経理専門職」として重宝されます。
つまり単なる帳簿整理担当ではなく、プロジェクトベースで動く工事案件ごとの損益把握・予算管理、さらには支払いサイトの適正化まで踏み込んだサポートが可能になります。
これはまさに建設業経理士役割としての真価ですね。
また、高精度かつ迅速な決算処理によって申請書類や中間報告書作成もスムーズになり、その結果として監督官庁や取引銀行などへの信頼性も大きく向上します。
これは実際、税務調査時や資金繰り相談時にもプラスに作用する要因になりますよ。
さらに中小企業の場合、「代表ひとり+外注税理士」でなんとかまわしていたところに有資格者が加わるだけでも統制力が激変します。
つまり制度知識と現場理解を兼ね備えた社内財務ブレーンができるわけで、小規模体制ほど効果は大きいです。
以下に代表的な5つの実務面メリットをまとめました:
- 社内会計基準の適正化:会計処理基準がブレずに維持されるため、不正リスク低減
- 監督官庁への信頼性向上:精度高い提出書類で審査印象UP
- 税務調査対応の簡素化:帳簿整備・説明資料準備工数の大幅削減
- 決算処理の迅速化:締め作業をタイムリーかつ効率的に完結可能
- 銀行など外部機関への与信力向上:財務可視化によって融資折衝にも強み
こうした実践的な経理士知識向上とその活用範囲(=経理士業務範囲)が、内部整備から外部評価まで広く波及する点こそ、「経審だけじゃない」資格保有価値になりますね。
経営事項審査点数を効率的に上げる戦略とは?
経審(経営事項審査)の点数を限られた人員や資金の中で効率よく上げたい。
その場合、「建設業 経理 士 経営事項 審査」で確実に加点できるW点対策が最優先です。
しかし、現実にはW点だけ上げても大幅な点数増とはなりません。
完成工事高・技術職員・財務指標など複数項目との連動が必要です。
以下の「3ステップ」で、経審点数向上を狙った合理的な経審合格戦略が立てられます。
経審計画作成:3ステップで考える最適ルート
- 財務分析と弱点項目の特定
まず今の自社経審結果から「伸ばせる項目」「改善不要項目」を整理しましょう。
Y(財務状況)正味キャッシュ比率やZ(技術)に偏りすぎてないか確認し、弱いスコアは具体的に可視化。これが戦略設計の出発点になります。 - 建設業経理士の社内育成と常勤配置
即効性があるW点強化として、「2級」1名配置で+3点、「1級」なら+6点と明確な得があります。
中小企業ならまず誰か1名取得させれば、それだけで他社との差別化になりますよ。 - 定期的な情報収集・制度改正チェック
制度改正によって加算基準や該当項目は毎年変わる可能性があります。
過去5年でも実際に評価方法刷新されており、最新データの入手と反映は抜け漏れないよう注意しましょう。
このように、「建設業 経理 士 経営事項 審査」を軸として戦略を組めば、継続的かつ安定した経審点数向上につながりますよ。
建設業 経理 士 経営事項 審査での評価向上の実現
中小建設会社の経理担当者や経営者の方々、建設業経理士資格がどのように評価に影響を与えるかについて理解することは、非常に重要なポイントです。この記事を通じて、この資格が経営事項審査(経審)での加点にどのように役立つか、その具体的な仕組みを明確にしました。資格取得が評価を高め、公共工事の受注増加へとつながる可能性があるため、手間やコスト以上に大きなメリットが得られます。この記事を参考に、新たなビジネスチャンスをぜひ見出してください。また、この記事をご覧いただき、感謝いたします。少しでもお役に立てたなら幸いです。


