建設業許可「特定」と「一般」の違いを徹底解説!選び方のポイントは?
建設業に新規参入を考えている経営者のあなた、または許可区分の切り替えを検討している方へ。特定と一般、どちらの建設業許可があなたのビジネスに最適か迷っていますか?制度の複雑さに戸惑うことなく、この記事を読めば、自分に最適な許可を選ぶための重要なポイントをしっかり理解できます。
建設業許可「特定」と「一般」の定義と違いを徹底解説

建設業許可には大きく分けて「特定建設業許可」と「一般建設業許可」があります。
両者のもっとも大きな違いは、元請事業者が下請契約を結ぶ際の金額規模にあります。
具体的には、1件の工事で下請契約が総額4,500万円以上(建築一式工事であれば7,000万円以上)となる場合、「特定建設業許可」が必要です。
逆に、これ未満の金額で工事を請け負う場合は「一般建設業許可」で対応可能です。
| 許可種別 | 下請契約額 | 必要性あり・なし |
|---|---|---|
| 特定建設業許可 | 5,000万円以上(建築一式は8,000万円) | 必要 |
| 一般建設業許可 | 50,00万円未満(建築一式は8,000万円未満) | 必要 |
| 軽微な工事(例:500万円未満) | 該当なし | 不要の場合あり |
「特定」は大規模な元請け工事に携わる企業向けとなっており、財務体力や技術管理責任体制など厳格な要件が課されます。
これは、発注者や下請業者を保護するための制度的配慮によるものであり、高額な取引においても安心・安全にプロジェクトが進行できるようにするためです。
一方、「一般」は比較的小規模〜中規模案件への対応を前提としており、会社の立ち位置としては、主に下請けや一定規模以下の施工管理を行う形になります。
このように、「特定」と「一般」それぞれの役割と対象範囲は明確に区分されており、自社がどのような工事を元請として担うかによって選ぶべき許可タイプが決まります。
制度全体としても、透明性と過度なリスク集中の回避を目的とし、健全な市場環境づくりにつながっています。
特定建設業許可の取得条件と特徴

特定建設業許可を取得するには、以下のような厳格な条件を満たす必要があります。
これは大規模工事を元請として受注する際に、発注者や下請業者との信頼関係を構築し、安全かつ適正な工事管理を行う体制があるかどうかを確認するための制度です。
特定建設業許可を取得するための5つの主要要件
- 財務基盤:純資産4,000万円以上・資本金2,000万円以上が必要
- 経営業務管理責任者:一定年数以上の実務経験を持つ経営経験者が在籍していること
- 技術者要件:国家資格(例えば一級施工管理技士など)を有し、かつ常勤で勤務できる専任技術者が必要
- 監理技術者 配置義務:工事規模に応じて、監理技術者が必ず現場に配置されること(監理技術者 必要性)
- 財産証明と納税実績:直近年度の貸借対照表などで十分な支払い能力と納税実績が確認できること
このように一般建設業許可に比べて、特定建設業許可では財務体力や技術的能力、それに伴う責任体制の強さが求められます。
制度としては、「高額な下請け契約が発生する場合」に元請け企業側へ高度な管理能力・資金力・法令遵守意識を求めることで、公共・民間問わず工事全体の品質確保や下請け保護につながる仕組みになっています。
つまり、大きな取引規模で「トラブルなく安全に完了させられる会社なのか?」という評価基準とも言えるでしょう。
これは他の一般的な建設業許可とは大きく異なる点(=建設業許可 必要条件 としての厳格さ)になります。
一般建設業許可の取得条件と活用の実態

一般建設業許可を取得するためには、比較的ハードルの低い条件を満たせば十分です。
財務面では「純資産500万円以上」があればよく、技術者配置も求められますが、国家資格必須などの厳格な要件は特にありません。
経営業務管理責任者についても、一定年数の経験があれば認められる基準となっており、「建設業許可 必要条件」としては中小企業にも手が届きやすい内容になっています。
このような取得要件だからこそ、初期コストや事務負担が少なく済む点も大きな強みです。
特定建設業に比べて維持費用・更新手続きも軽く、参入障壁が低いため、新規開業者やフリーランス、大型工事を請け負わない施工事業者にとって非常に現実的な選択肢となっています。
特に「許可のメリット」として、市町村などから発注される中小規模公共工事への入札権を得ることが可能になる点は重要です。
一般建設業 制約として、大口案件(下請契約5,000万円以上または建築一式で8,000万円以上)には対応できません。
それでも、大多数の中小会社や個人施工者の場合、小中規模案件を主力としていることから、この制約はそこまで大きく感じないケースも多いです。
そのため、「一般建設業許可 概要」としては、“無理なく身の丈に合った形で事業拡大できる制度”という位置づけになります。
特定・一般建設業許可の比較表と選び方のポイント
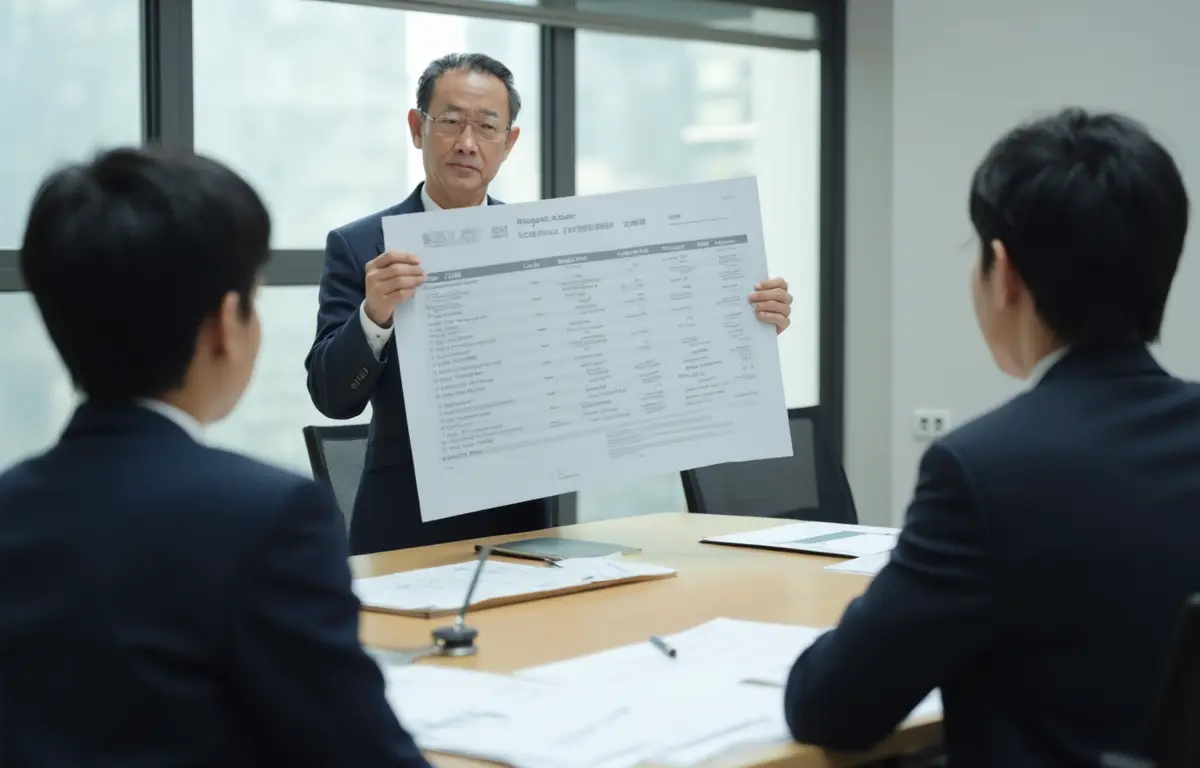
建設業 許可 特定 一般 違い を理解するうえで最も重要なのは、「どちらが自社の事業規模・方向性に合っているか」を適切に見極めることです。
以下は、財務条件や技術者配置など主要6項目における一般建設業許可と特定建設業許可の違いを示した比較表です。
| 比較項目 | 一般建設業許可 | 特定建設業許可 |
|---|---|---|
| 財務基準 | 純資産500万円以上 | 純資産2,000万円以上、かつ負債比率等も管理対象 |
| 技術要件 | 一定の実務経験or資格保有者 | 国家資格保持技術者+現場常駐(専任)義務あり |
| 経営業務管理責任者要件 | 緩やかな実務年数基準でOK | より長期間・大規模工事経験が必要な場合あり |
| 対象工事規模 | 下請契約5,000万円未満(建築一式は8,000万円未満)向け | 5,000万円以上の下請契約が発生する元請案件向け |
| 責任・義務範囲 | 通常水準(支払い保証なし) | 下請けへの保護制度あり |
| 申請書類数・審査難度 | 簡易/一部書類で足りる場合あり | 経営事項審査含め複雑/厳格な確認項目多数あり |
選び方は、次の3つの視点から整理すると判断しやすいです。
- ① 現在扱う工事契約金額:5,000万円を超えるようなら「特定」一択。それ以下なら「一般」で十分な場合多数
- ② 財務体力:資本金や自己資本を十分満たせるかが分岐点になる
- ③ 将来的経営戦略:「今は小中案件でも将来大型元請を狙いたい」場合、将来「特定」に移行可能性も想定しておく
このように、「まずは一般→後に特定への切替」という形も十分現実的で広く選ばれているパターンです。
許可取得 のステップは自社成長と合わせて計画的に進めることが 成功につながります。
許可申請手続きの流れと必要書類の違い

建設業 許可(特定・一般)のどちらを取得する場合でも、許可申請 手続きとしては基本的に以下のような流れで進みます。
- 事前相談(任意)
- 必要書類の準備
- 所管官庁への提出(都道府県か国交省)
- 審査(内容確認・補正依頼など)
- 許可通知の受領
この一連の許可申請プロセス自体は共通ですが、「特定」と「一般」では求められる書類と審査の厳しさに大きな違いがあります。
共通して準備すべき主な書類
- 経営業務管理責任者に関する証明書(経験年数等)
- 専任技術者に関する資格や経歴証明
- 商業登記簿謄本(法人の場合)
- 納税証明書
- 事務所所在地が確認できる資料
特定建設業のみ追加で必要な主な書類
- 貸借対照表・損益計算書等による財産証明
- 純資産4,000万円以上であることを示す資料
ここで大事なのは、「特定」は審査基準が厳格なので、単なる形式チェックではなく、企業経営の健全性まで細かく見られる点です。
また、都道府県単位で処理するか国交省へ出すかという提出先の違いもあるため、自治体ごとの手続様式も確認が要ります。
許可申請 書類が多くなる「特定」の場合は、不備や修正指示が出ることも少なくありません。
よって、
- 書類作成時から専門家へ相談しておくこと
- 審査官とのやり取りを見越し余裕を持ったスケジュール作成
などが、許可申請プロセス 効率化には不可欠です。
申請前から段取り良く動くことで、無駄な時間や手戻りリスクを抑えることができるでしょう。
特定と一般それぞれのメリット・デメリット
| 許可種別 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 特定建設業許可 | 大規模工事の元請け受注が可能/官公庁案件での信頼性向上 | 財務・書類・技術要件が厳格/維持コストや責任が重い(例:賃金立替義務) |
| 一般建設業許可 | 取得しやすく手続きも簡潔/初期コストが軽く参入障壁が低い | 大規模案件に参加不可/一部自治体発注案件の応募制限あり |
「特定建設業許可」は、5,000万円以上の下請契約を伴う元請け工事を行うために必要となるため、大口取引や自治体・官庁からの案件にも対応できるという点で優位性があります。
これは企業の信頼性アップや受注拡大戦略において有利ですが、その反面、自己資本4,000万円以上、国家資格者の専任配置、下請け賃金遅延時の立替義務など特定建設業 制約は非常に重くなります。
一方で、「一般建設業許可」は中小規模案件中心あるいは下請けポジションで活動する企業には最適です。
特別な国家資格なしでも要件を満たせる点や、財務基準も緩いため、新規事業者でも比較的スムーズに取得できます。
ただし、大規模な元請工事には参入できないという一般建設業 制約があります。
このように、両者とも明確な「許可のメリット」と「制約」があるため、自社の財政余力や施工戦略をふまえて選ぶ視点が重要になります。
許可制度の背景と法律上のポイント
建設業許可制度が存在する最大の理由は、「施工体制の適正化」と「下請け事業者の保護」にあります。
特に大規模工事では、元請が多額の下請契約を結ぶため、適切な管理能力と財務体力がなければ後々トラブルになりやすいです。
この制度は、建設業法に基づいて運用されており、「契約金額の規模による許可区分」が明確に定められています。
たとえば、
- 元請が5,00万円以上(建築一式なら8,000万円以上)の下請契約を締結する場合 → 特定建設業許可
- それ未満の場合 → 一般建設業許可
という基準です。
この法制度で最も注目されるべき点は、「特定」の方にはより重い法的義務が課せられていることです。
法的枠組みによって「施工品質や契約の透明性」が担保されており、これがまさに建設業 法律遵守や法的義務 理解という観点で重要な部分になります。
言い換えれば、“いい加減な元請”によって現場全体が崩壊しないよう防止する仕組みとも言えます。
これはまさしく建設業法 特徴と言えるでしょう。
建設業許可区分のよくある誤解と注意点
建設業 許可 特定 一般 違いを理解せずに申請や工事を進めてしまうと、後々思わぬトラブルを招くリスクがあります。
ここでは「関係制度 情報」や「建設業実務 ノウハウ」の観点から、特に注意すべき3つの誤解を紹介します。
- 500万円未満の工事ならすべて許可不要だと思い込むパターン
→ 正しくは、「軽微な工事」であっても建築一式や公共事業関連では別基準が適用されることがあり、単純な金額基準のみで判断するのは危険です。 - 一般許可で今後ずっと対応できると過信するケース
→ 成長に伴い大規模案件へ参入した場合、「特定許可」が必要になります。将来見越して制度選択しておかないと、突然工事ができなくなる恐れもあります。 - 一部要件をごまかして申請し、発覚したら大問題になるタイプ
→ 虚偽申請や資格者要件未達成が発覚すると「許可キャンセル リスク」が現実となり、営業停止・入札除外など重大な制裁につながります。
このような誤解は現場でも頻発します。
制度理解不足による失敗は取り返しがつかない場合もあるため、申請前には最新情報と専門家への確認を必須としましょう。
建設業許可の特定と一般の違いについての結論
この記事を通じて、特定建設業と一般建設業許可の違いを詳しく理解することができたと思います。特定建設業は、下請負契約の扱いが大きなポイントであり、特に500万円以上の工事や複数の下請業者を使う場合に重要になります。一方で、一般建設業許可は比較的小規模なプロジェクトに適しており、柔軟な経営が可能です。
自分の事業規模や将来的なビジョンを考慮し、一番適した許可区分を選んでください。これにより、今後の申請手続きや事業展開が円滑に進むことでしょう。
読んでいただきありがとうございました。選択に迷ったら、専門家への相談も一つの手です。成功をお祈りしています!


