建設業許可要件をクリアするための基本ガイド
建設業許可を取得しようとするあなたは、煩雑な要件に頭を悩ませていませんか?公式の情報は難解で、情報をまとめる時間もない中小建設会社の経営者や個人事業主にとって、この一歩は大きな壁かもしれません。このガイドを最後まで読めば、必要な資格や手続きが明確になり、不許可のリスクを低減させることができます。
建設業許可要件の基本6項目を理解する
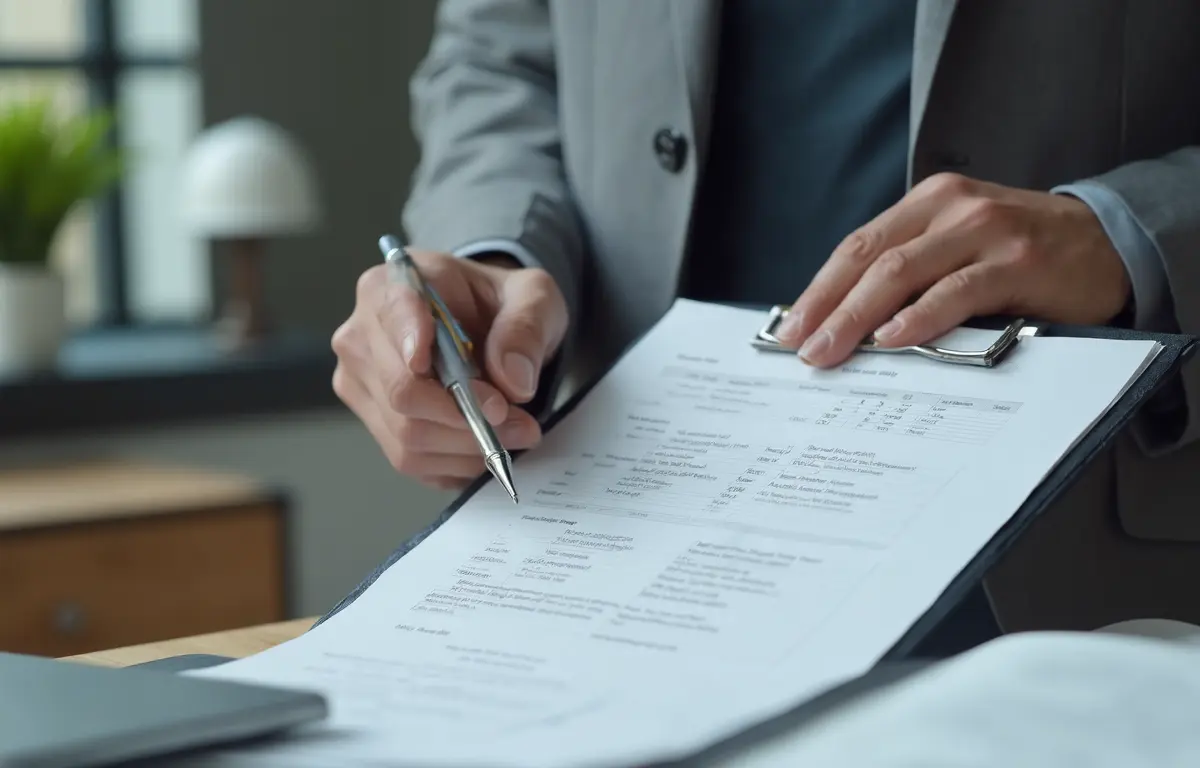
建設業許可を取得するには、建設業法に基づいて定められた6つの主要な要件をすべて満たす必要があります。これは法人・個人事業主問わず共通で、国土交通大臣または都道府県知事による審査が行われます。以下に各要件の内容を簡潔に整理しました。
| 要件 | 簡易説明 |
|---|---|
| ① 経営業務の管理責任者 | 建設業での経営経験者(例:役員として5年以上など) |
| ② 専任技術者 | 建設工事ごとの国家資格所持者や10年以上の実務経験者 |
| ③ 誠実性 | 過去に重大な法令違反や不正が無いことが条件 |
| ④ 財産的基礎 | 一定金額以上の自己資本や融資証明書等で経営体力を証明 |
| ⑤ 社会保険適用義務への加入 | 雇用保険・健康保険など各種社会保険へ適正加入しているかどうか |
| ⑥ 欠格要件への非該当 | 暴力団関係・破産歴・禁固刑などに該当しないことが必要条件 |
これら6項目はどれか1つでも不備があると、不許可となるリスクがあります。書類上しっかり備えているようでも、経歴不足や資格証明ミス、社会保険未加入など細かな部分で落とされる場合もあるため、事前チェックは必須です。特に「建設業 許可 要件」における経営業務責任者と専任技術者は毎年不備報告が多く出るポイントなので注意してください。
経営業務管理責任者の経験要件とは?

建設業 許可 要件の中でも、経営業務管理責任者要件は最もつまずきやすいポイントです。
この「建設業法経営管理責任者」になるためには、申請する建設業において十分な実務経験と立場を証明する必要があります。
代表的な認定基準は以下の2つです。
- 同種の建設業で5年以上、常勤役員として経営業務を担った経験
- もしくは、「当該業種で2年以上役員等→他の建設業種で3年以上の経営経験」の組み合わせ
この条件を満たしているかどうかは、単なる在籍期間ではなく「実際に会社運営に携わっていたこと」が重視されます。
申請時には、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)や会社経歴書、役職ごとの職務内容証明などによってスムーズに立証しましょう。
また近年は制度緩和として「補佐人制度」も導入されました。これは、財務・労務・資金調達・工事受注などの面で直接補佐してきた実績を持つ社員が対象となり、「5年以上の該当分野経験」で条件を補完できる仕組みです。
ただしそれでも「経営業務管理責任者常勤」であることが絶対要件です。別会社との兼任や非常勤扱いになっている場合は不許可リスクが高まりますので注意が必要です。現行基準では就業実態確認も厳格化されており、提出資料には雇用契約書や税務書類など追加的根拠が求められる場合もあります。
専任技術者要件と必要資格一覧

建設業 許可 要件のうち、専任技術者要件は非常に重要な審査項目の一つです。
すべての営業所には、それぞれに1名以上の「営業所専任技術者」が常勤として配置されていなければなりません。この専任技術者には、「建設業許可専任技術者資格」を持つことが求められます。
資格だけでなく、対象業種で10年以上の実務経験でもその代替が認められる場合があります。下記は代表的な建設業種ごとの「一般建設業専任技術者資格」例です。
| 建設業種 | 主な認定資格 | 実務年数代替 |
|---|---|---|
| 土木工事業 | 一級土木施工管理技士 | 10年以上(土木工事の指導監督経験) |
| 建築工事業 | 一級建築士/一級建築施工管理技士 | 10年以上(建築関連工事従事・監督) |
| とび・土工・コンクリート工事業 | 一級とび・土工施工管理技士など | 10年以上(該当分野の現場従事経験) |
| 管工事業 | 一級管工事施工管理技士/給水装置主任技術者等 | 10年以上(給排水・空調等の現場監督) |
営業所専任という名前の通り、その人物が「常勤」であること――つまり、その営業所に毎日勤務し、他社との兼務をしていないこと――が明確にされていないと不許可になります。
提出書類で注意したい点としては、以下を要チェックです:
- 専任する国家資格証明書の写し(コピー)
- 実務経験で代用する場合は、過去勤務先から発行された職務証明書や在籍証明書
- 雇用関係を証明できる資料(給与台帳や源泉徴収票)
特に実務年数による証明では、不鮮明だったり年数計算誤りがあるだけで差戻し対象になるケースも多いため、最初から第三者確認可能な形を整えておきましょう。
500万円以上の工事に必要な財産的基礎とは?

建設業 許可 要件の中でも、「財産的要件」は非常に実務的かつ明確な数値判断がされるポイントです。
特に一般建設業では「500万円以上の工事」を扱うため、最低限の経営体力があることを証明しなければなりません。以下は、代表的な財務要件の目安とクリア方法です:
- 一般建設業:自己資本額が500万円以上であること
- 金融機関からの「融資証明書」で500万円調達可能と示すことでも代替可
- 特定建設業:資本金2,000万円以上+自己資本4,000万円以上という厳格な基準
このうち特定建設業は、元請けとして大規模工事(下請へ4,000万円超を発注する場合など)を行うため、より強い経営基盤が求められます。
対して一般建設業の場合は、新規創業者や中小企業でも比較的クリアしやすい設定となっています。しかし、ここで注意すべきは「証明資料」です。財務状況は口頭では認められず、書面で裏付ける必要があります。代表的なものは以下2つです。
- 預金残高証明書(銀行発行):直近3ヶ月以内の日付入りであることが条件
- 決算書・貸借対照表:税理士署名付きまたは登記済み資料で信頼性を担保
どちらも形式や数値だけでなく「提出時点からの時間経過」にも厳しくチェックされます。特に直近3ヶ月以内という期限付き要件を見落とすケースが多く、不備理由になりやすいので必ず確認しましょう。
また融資による代替認証の場合も、金融機関から正式に発行された「融資可能性証明」が必要になり、「見込み」レベルでは認められません。
つまり、現金保有か確定した信用力――どちらかを立証できない限り許可取得には至りませんので、小規模経営者ほど慎重な準備が不可欠です。
建設業許可で問われる「誠実性」とは?

建設業 許可 要件の中でも、「誠実性」の判断は非常に見落とされがちなところです。
これは単に人柄を問うのではなく、過去の法令違反歴や契約不履行などがあるかどうかという“実績ベース”で審査されます。
代表的な対象として、過去に建設業法違反によって指名停止処分を受けた事業者、暴力団排除条項違反が判明した元請業者、または下請代金未払い事案などがあります。たとえば「許可取得ら2年以内に営業停止命令を受けた」「労働基準法違反による送検歴あり」などは特に重く見られます。
企業単位だけでなく、その法人の役員個人についても厳しく調査され、不利益な経歴がある場合には、その内容と背景を補足説明付きで提出する必要があります。
欠格要件に該当するケースをチェック
建設業 許可 要件の中で、見落としがちなポイントが「欠格要件」です。
これは、申請者本人だけでなく法人の役員全員に適用される重要な確認事項となっており、そのひとつでも該当すると即アウト、不許可確定です。
以下は代表的な欠格要件です。
- 禁固刑や暴力団との関係がある
→ 刑の執行を終えた日から5年以内の前科がある場合や、暴力団員・関係者だった記録がある場合は絶対に不許可となります。 - 過去に建設業許可を取り消されたことがある
→ 偽装申請や重大違反による行政処分歴(取消処分)が5年以内にあれば、再申請はできません。 - 破産手続中で免責を受けていない
→ 法人代表も個人事業主本人も「現在進行中の破産状態」であれば、自動的に欠格扱いです(免責確定済みなら対象外)。 - 虚偽申告・名義貸しなど不正行為がある
→ 他人名義での申請、不正確な資格証明、本来専任すべき技術者との別人記載などは全て虚偽として扱われ、「取消」だけでなく刑事罰対象にもなります。
これらは単なる自己申告では済まず、市区町村発行の身分証明書や登記簿謄本などで厳しく裏付けされます。
特に注意すべき点として「法人役員全員」がこの審査対象になるということ。経営陣のうち一人でも過去に問題履歴がある場合、それだけで許可取得自体が失敗します。
また最近では反社排除条項強化などもあり、名前や戸籍上変化まで調査されるケースも実際多くあります。過去トラブルや懸念事項が少しでも頭によぎる場合には、専門家への事前相談と履歴証明書提出準備が必須です。
一般・特定建設業許可で異なる要件の違い
建設業 許可 要件には、「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があり、それぞれで求められる条件や対応できる工事の規模が大きく異なります。
最も大きな違いは、発注者との関係性と工事金額にあります。一般建設業は主に下請けとして500万円以上の工事(建築一式なら1,500万円以上)を受注する場合に求められる許可です。
これに対し、特定建設業は元請負人として下請に出す金額が5,000万円(建築一式は8,000万円)を超える場合に必要となり、より高い経営安定性と技術者の資格水準が求められます。
以下の表に両者の主要な違いを簡潔にまとめました。
| 区分 | 資本金等要件 | 工事範囲 | 技術者資格基準 |
|---|---|---|---|
| 一般建設業 | 自己資本500万円以上 | 下請金額5,000万円未満の元請/下請工事 | 一級または二級施工管理技士など資格または10年以上実務経験 |
| 特定建設業 | 資本金2,000万円以上+自己資本4,000万円以上 | 元請として5,000万円以上(建一式8,000万超)の下請への発注を含む工事全般 | 原則一級施工管理技士等、国家資格レベル必須 |
どちらを選ぶべきかという判断軸ですが、“元請になるかどうか”が最大のポイントです。
もし自社が今後、大型案件でゼネコンや官公庁から直接受注し、その内容を他社へ再委託(下請化)する可能性があるならば特定許可取得が必要になります。
逆に「自社完結型」や「中小規模メイン」の施工体制なら、資本や要件面で優しい一般許可からスタートするほうが現実的です。自社事業計画との整合性をよく見直した上で、無理のないラインから取り組むことが大切です。
建設業許可申請の必要書類と進め方
建設業 許可 要件をクリアするためには、各種条件だけでなく「必要書類の正確な準備」と「手続きの順序を守ること」が決め手になります。
特に、建設業許可必要書類はどれも漏れやミスが不許可に直結するため、理解と対応が非常に重要です。
建設業許可取得方法:申請手順
以下は、一般的な建設業許可取得方法として推奨される5ステップです。
- 要件確認
まず、自社が6つの主要要件(経営業務管理責任者/専任技術者/財産的基礎など)をすべて満たしているか再点検します。 - 必要書類準備
建設業許可必要書類として、不足しやすいもの含めて下記をそろえます:
- 申請書一式(専用様式)
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
- 過去3期分の決算報告書・貸借対照表
- 専任技術者・経営業務管理責任者の資格証明または実務経験証明
- 納税証明書(法人税/消費税等)
- 銀行発行の預金残高証明または融資証明
個人事業主と法人で添付資料項目が異なることもあるため、申請先で正式リストを確認しましょう。
- 予備審査(相談)
都道府県庁または行政委託窓口で事前相談し、不備内容や改善点をチェックしてもらうことで補正リスクを事前低減できます。 - 正式申請
準備資料一式を提出します。窓口で形式不備があると即返されるケースもあり注意。 - 審査~許可取得
審査期間は標準で30~45日程度。不足資料提出などが求められる場合、この期間中に修正指示があります。
ミス防止&審査通過率向上に:チェックリスト活用
経験上、不許可や遅延につながりやすいポイントには以下があります:
- 資格証コピーの日付・氏名違いなど形式ミス
- 決算資料に税理士署名なし
- 経営業務経験年数計算ミス
- 専任技術者と営業所の雇用契約不整合
- 預金残高証明の日付が古い(1ヶ月超)
こうしたミス回避には、自社専用のチェックリスト作成がおすすめです。行政書士など専門家による事前レビューも効果的です。
「あとちょっと足りない」を防ぐためにも、各種建設業許可申請資格と関連資料を早めに洗い出し、不安点は早期確認するクセをつけましょう。
建設業 許可 要件をクリアするための最終チェックポイント
建設業許可を取得するために必要な要件について詳しく知りたいと思ってこのガイドを手に取ったあなた。難解な情報や煩雑さに圧倒されることなく、ここで提供する重要なポイントを押さえることで、不許可のリスクを回避し安心して申請手続きを進められます。
まず、経営業務の管理責任者を置くことは基本的な条件ですが、この役割を正しく理解し、証明できる書類をしっかり整備しておく必要があります。また、各営業所に専任技術者を配置することも必須条件です。これらの役割に相応しい人材がいるか事前に確認しましょう。
さらに、誠実性や財産的基礎、適切な社会保険への加入状況もチェックリストに加えてください。これらの条件が満たされているかどうかが、許可取得への大きなポイントとなります。そして、欠格要件に該当しないことも必ず確認しておきましょう。
計画的に準備と確認を進めることで、無理なく許可申請を成功させることができます。このガイドが少しでも皆様のお役に立てたなら幸いです。不明点があれば、専門家へ相談することもおすすめします。頑張ってくださいね!


