建設業許可が必要な解体工事、登録との違いを押さえよう
解体工事を始めるにあたり、建設業許可の取得は重要なステップです。しかし、どう手続きを進めれば良いのか悩んでいる方も多いでしょう。このブログでは、許可取得に関する具体的な手順や注意点を解説し、書類作成に不安を感じるあなたをサポートします。これを読めば、許可取得への不安が和らぎ、一歩を踏み出す自信が得られるでしょう。
建設業許可(解体)と解体工事業登録の違いを明確に理解しよう

解体工事を行うためには、「建設業許可(解体)」または「解体工事業登録」のいずれかが必要です。この2つは混同されがちですが、実際には制度上・運用上で明確な違いがあります。
まず、「解体工事業登録」は小規模な工事、つまり税込500万円未満の請負に対応する制度で、都道府県知事への届出だけで比較的簡単に取得できます。営業所設置義務もなく、個人・法人問わず申請可能です。一方、「建設業許可(解体)」はそれよりも大規模な施工や元請として公共案件などに関わる場合を対象とし、専門性・組織性が問われます。平成28年6月以降、従来の「とび・土工工事業」から分離され、「解体工事」は独立した建設業種として認識されています。
適用範囲の主な違いは以下の3点になります:
- 請負金額による区分:
税込500万円以上の解体工事には「建設業許可(解体)」が必須。下回る場合は「解体工事業登録」で対応可能。 - 発注形態による扱い:
元請として公共案件や多棟契約を想定する場合、「建設業許可」が必要不可欠。 - 手続きおよび資格要件:
建設業許可取得には経営業務管理責任者や専任技術者など厳しい条件がある一方、登録は比較的緩やか。
自社がどちらに該当するかを判断するためには、まず行う予定の解体作業の契約金額が税込500万円を超えるかどうか、それが元請けなのか下請けなのか、公的物件なのか民間なのかといった要素から丁寧に検討することが重要です。不安な場合は建築行政窓口または専門家への相談も有効ですよ。
解体工事業に必要な建設業許可の取得要件とは?

建設業 許可 解体 を取得するには、「専任技術者」「経営業務管理責任者」「財務基盤(資金力)」の3項目で明確な条件があります。これらはすべて満たす必要があり、ひとつでも不備があると申請が却下される恐れがあります。
専任技術者
これは現場を直接管理する立場の技術者です。配置が義務であり、一定資格または実務経験10年以上であることが求められます。代表的な解体業 資格 には、「1級建築施工管理技士」や「解体工事施工技士」が含まれます。ただし、指定学科卒であれば実務経験3年でも足ります。証明には資格証や年金記録、過去の工事契約書等が必要です。
経営業務管理責任者
法人の場合は常勤役員の一人、個人事業主なら本人か支配人が該当可能です。この役割は5年以上の解体・建設業経営経験を有することが条件で、その内容を裏付ける経歴証明資料も必要です。このポジションが不在だと許可申請自体できません。
財務的要件(資金力)
建設業許可 解体 は健全な経営基盤も問われます。一定以上の自己資本、継続的に施工できる運転資金などの確認があります。具体的には直近決算書、納税証明書、残高証明などを通じて信用性や資産状況が審査対象になります。
以下に主要要件を表形式で整理しました。
| 要件区分 | 内容と条件概要 |
|---|---|
| 専任技術者 | 資格保持(例:1級施工管理技士)または実務経験10年以上 |
| 経営業務管理責任者 | 解体・建設等に関し5年以上の経営実績・常勤役員または本人 |
| 資金力・信用状態 | 財産証明・納税履歴・預貯金残高など財政健全性を示す資料 |
この3点を押さえれば、解体工事業 許可要件 の98%は理解できたと言っても過言ではありませんよ。
専任技術者の資格と実務経験による証明方法

建設業 許可 解体 を申請する際、専任技術者の配置が求められます。専任技術者として認められるには3つのルートがあり、それぞれに必要な条件や提出書類が異なります。以下でそれぞれのルートを詳しく説明します。
① 資格取得者ルート
もっとも分かりやすい道は「解体工事施工技士」など国家資格を保有しているパターンです。一級・二級建築施工管理技士や土木施工管理技士でも要件を満たせることがありますが、解体業に特化した「登録解体工事講習修了証」がある場合、該当講習を受けていれば専任技術者として認定されます。この場合、資格証明書(写し)や講習修了証が提出必須となり、追加で工事実績の証明は基本不要です。
② 学歴+実務経験ルート
大学・専門学校など指定学科(建築・土木系)卒業者であれば、3年以上の実務経験があれば専任技術者に該当します。ただし、この場合は卒業証明書と3年以上勤務したことを証明するための施工実績資料や契約書類、雇用保険加入記録など複数の裏付け資料が必要になります。会社ごとのフォーマットではなく、公的な根拠資料を添えることが重要です。
③ 実務経験のみルート
指定学科卒でない人でも10年以上の現場経験があれば、専任技術者として認められる可能性があります。このパターンでは特に「一貫した職歴」を示す必要があり、できるだけ多くの工事契約書や注文書類を集めて提出します。加えて雇用保険記録や厚生年金被保険者記録照会回答表など、公的な就労履歴も強力な裏付けとなります。
以下に3つのルートと必要書類を一覧で比較しました。
| 資格ルート | 必須書類 | 実務年数 |
|---|---|---|
| 資格取得者 | 国家資格証 or 登録解体工事講習修了証 | 不要(免除) |
| 学歴+経験 | 卒業証明 + 業務経歴証材料一式 | 3年以上 |
| 実務経験のみ | 雇用保険記録・複数工事契約資料等 | 10年以上 |
どのルートでも中途半端な資料では信用されません。特に経験のみルートなら、不備によって申請却下になるケースも多いため十分注意してください。
建設業許可(解体)の申請手続きと必要書類
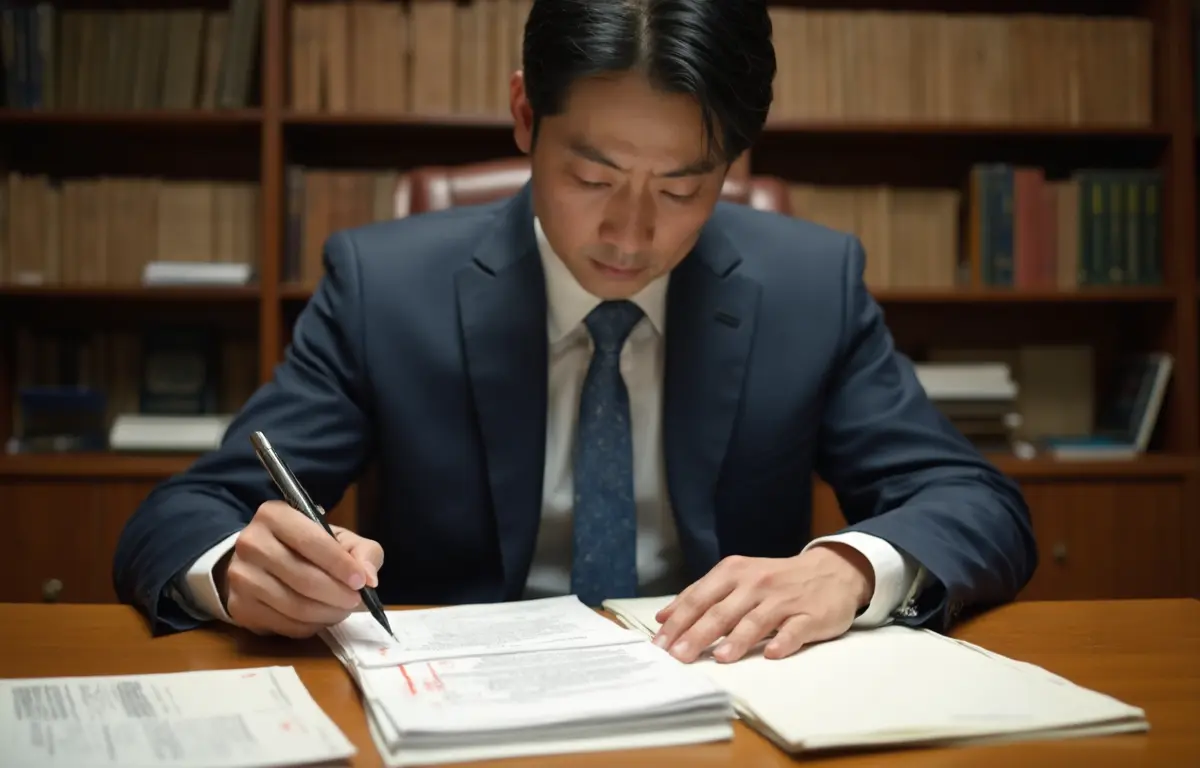
建設業 許可 解体 を取得するには、申請に必要な事前準備と、正しい流れを押さえておくことが不可欠です。まず、施工予定の解体工事が税込500万円以上であれば、簡易な登録制度ではなく正式な建設業許可が必要になります。許可には「知事許可」か「大臣許可」があり、営業拠点の所在エリア数によって区分されます。ひとつの都道府県内のみで営業するなら「知事」、複数府県にまたがる場合は「大臣」の管轄となります。
まず着手すべきは条件の確認からです。経営業務管理責任者や専任技術者の要件を満たしているかどうか見極めましょう。その次に、解体工事 申請書類 を揃えます。全ての添付資料が整ったら都道府県庁や地方整備局など該当窓口へ提出します。また、不備や不足があると受付不可や差し戻しになるため、「完璧な状態」で出すことが重要です。なお、自社で手続きを進める以外に、行政書士へ依頼して代行してもらう選択肢もあります。その場合は別途10万~30万円程度の費用目安となります。
以下は建設業 許可 解体 において提出必須となる代表的な書類6点リストです:
- 履歴事項全部証明書
→ 法人登記情報を示すもので、有効期限3ヶ月以内のものが適用されます。 - 定款
→ 現在有効なもの。会社目的欄に「解体工事」の記載があることを確認しましょう。 - 住民票
→ 個人事業者本人または法人代表役員分。マイナンバー記載なし版を用意してください。 - 納税証明書
→ 法人税または所得税の納付実績を示す資料で、国税庁様式第3号などタイプ指定あり。 - 専任技術者の資格証明書
→ 二級施工管理技士・登録講習修了証・実務経験証など条件に応じて異なる証明方法があります。 - 経営業務管理責任者の経験証明書
→ 実務5年以上等を裏付ける過去契約書、社保加入履歴等を整理したうえで添付します。
どれか一つでも不備があると許可申請 は失敗する恐れがありますので、「段取り」より「正確性」を優先して準備してくださいね。
解体工事業登録が適用されるケースと注意点

「建設業 許可 解体」が必要となるのは税込500万円以上の解体工事に限られます。これに対し、請負金額が500万円未満であれば「解体工事業 登録」だけで合法的に工事を行うことが可能です。この制度は比較的ハードルが低く、都道府県知事への申請のみで済むため、小規模事業者にも多く利用されています。また、「登録」では資本金や常勤役員人数、組織体制などの厳格な条件も課されません。元請け・下請け問わず、500万円未満の解体作業であれば誰でも該当になります。
ただし、「解体工事業 登録」は簡単そうに見えても、乱用すると無許可施工と誤認される恐れがあるため注意が必要です。特に最近では監督行政側も契約実態を厳しく見る傾向があります。また、「登録要件」に該当しないケーズ=例えば設備撤去のみなど一部作業だけの場合は対象外となるため、自己判断で進めないようにしましょう。
以下は「解体工 事業 登録要件」を誤認して起きやすい注意点3つです:
- 請負総額で500万円(税込)以上でないか確認を必ず行うこと
- 口約束ではなく契約書を明文化しておかないと後で「無許可」とみなされるリスクあり
- 工事中または完了後に追加費用発生した場合、その結果として合計額が500万円以上なら再確認(許可取得要否)の必要あり
安易な判断から手続きミスにつながりやすいため、自社案件の性質と金額を細かく洗い出した上で「登 録」と「許可」のどちらが必要かを検討してくださいね。
無許可解体のリスクと罰則について知っておくべきこと
「建設業 許可 解体」を取得せずに解体工事を行うとどうなるのか?――それは明確に「建設業法違反」となり、かなり重たい処分を受ける可能性があります。請負金額が税込500万円以上であるにもかかわらず「解体工事業登録」だけで施工した場合や、そもそも登録すらせずに工事を始めた場合などが該当します。
最初は行政指導(是正命令)が入りますが、悪質または繰り返し違反の場合は、「工事中止命令」や「営業停止・指名停止」、さらには懲役刑まで科されることもあります。
「軽微だから大丈夫」と誤認していると危険です。「建設業 許可 解体」や「解体工事業 登録」は規模や発注形態によって義務付けられているため、自社案件の金額や内容に応じて必ず確認し、必要手続きを済ませた上で着手するようにしましょう。
解体工事許可取得にかかる費用と期間の目安
建設業 許可 解体 を取得する際の法定費用は、知事許可の場合で約90,000円です。
これは申請手数料として都道府県または国へ支払う金額です。ここに行政書士など専門家へ代行を依頼する場合は、追加で10万〜30万円程度の報酬が発生します。自社対応ならコストを抑えることも可能ですが、書類ミスや経験値不足から再提出になることも少なくありません。実際、専門家に依頼した方が資格取得や合格率面でも安心感があるとの声も多いです。
一方、建設業 許可 解体 の取得までにかかる時間は、通常1〜2ヶ月程度が一般的です。ただし条件や準備状況によって幅があります。不備が発覚した場合や繁忙時期には3ヶ月以上かかるケースも実際にありますので「余裕を持ったスケジュール設定」が不可欠ですよ。
以下は取得期間の目安をパターン別にまとめたものです:
- スムーズな場合:1ヶ月強
- 標準的な場合:1〜2ヶ月
- 書類不備や繁忙期:3ヶ月超
どれだけ早く進めたい場合でも、「正確な資料」と「要件確認」を怠らないことが最短取得への近道です。
建設業許可で解体工事を行うための要点
解体工事を始めるにあたり、許可取得への不安を感じている方も多いでしょう。必要な手続き、要件、そして書類作成の手順について具体的にご紹介しました。最初に述べたように、許可の取得は重要なステップであり、多くの人が悩む部分です。
手続きや書類作成は複雑に見えるかもしれませんが、一歩一歩進めていくことで解決できます。あなたの努力が成功へと繋がることを願っております。最後に、この記事を読んでいただき、本当にありがとうございます。不明点があれば専門家へ相談するのも一つの手です。


