特定建設業許可取得への道のりと必要要件を徹底解説!
特定建設業許可の取得を目指す際、どのような要件が必要なのか、明確にご存じでしょうか?多くの中小建設会社の経営者や総務担当者にとって、具体的な基準や必要書類を理解し、不許可を避けることは重要です。この内容を理解すれば、特定建設業許可の取得に向けた一歩を自信を持って進むことができます。このブログでは、その道筋と要件をご紹介します。
特定建設業許可が必要なケースとその背景

「特定建設業 許可 要件」に関して最も重要なのは、「どんなときにこの許可が必要なのか?」という点です。
まず結論から言うと、
特定建設業許可が必要となるのは、
元請として1件あたり5,000万円(建築一式工事なら8,000万円)以上の工事を発注する場合、
またはそのような規模を下請に出す場合です。
これ未満であれば一般建設業許可だけでも足りますが、それを超えると法律上「特定」の枠組みが求められます。
たとえば、あなたの会社が民間から土木一式工事を受注し、「全体で5,500万円」かかるうち5,100万円分を専門工事業者へ外注する場合、この発注者としての行為に対して特定建設業の資格が無ければ違法になります。
これは単なる登録制ではなく、監督官庁(都道府県や国交省)によるしっかりした審査対象となっており、
一般建設業との最大の違いは「元請として大きな責任ある立場で安全・品質・予算管理など全体マネジメント能力」を持っているかどうか、という視点で判断される点です。
特に公共性の高い工事や大口融資との関連性も強いため、中小企業でもこの要件クリアを狙って戦略的に動くケースも増えています。
- 元請で1件5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の工事を発注
- 一般建設業許可では請け負えない規模
- 公共工事での元請け参加
- 銀行融資や信用評価の向上
- 契約時に法的根拠としての提示が求められる場面
このような場面を想定して、自社ビジネス規模や成長計画に合わせたタイミングで「特定建設業 許可 要件」に本格着手することが必要不可欠になってきます。
特定建設業許可の財産的要件の詳細

特定建設業 許可 要件の中でも最も差がつきやすいのが財産的要件です。
まずこの許可を取得するには、次の4つの財務指標すべてを満たす必要があります。
1つ目は「資本金または出資金が2,000万円以上」であること。これは会社設立時または増資時に登記簿謄本で確認されるため、かなり明確な条件です。
続いて2つ目、「純資産額が4,000万円以上」。これは貸借対照表ベースでチェックされます。債務超過状態ではもちろんNGとなりますので、赤字続きだったり設備投資負担が重くて自己資本がマイナスだと申請できません。
3つ目、「欠損比率が20%以下」であること。
4つ目、「流動比率が75%以上」も条件です。これは(流動資産÷流動負債)×100で求める一般的な安全性指標なのですが、この点も実務上見落とされやすいです。売掛金偏重決算や短期借入多めだと簡単に引っかかります。
審査では法人なら「直近確定決算書」、個人なら「直近の確定申告書」が基準となり、一部だけ満たしていてもダメです。また更新時にもこれら条件は再判定されますので、一回クリアしたからと言って油断は禁物です。
| 財産的要件項目 | 基準値 |
|---|---|
| 資本金 | 2,000万円以上 |
| 純資産 | 4,000万円以上 |
| 欠損比率 | 20%以下 |
| 流動比率 | 75%以上 |
特定建設業許可に必要な専任技術者の要件とは?

特定建設業 許可 要件の中でも多くの事業者がつまずきやすいのが「専任技術者」の確保です。
まず大前提として、この専任技術者は「申請会社に常勤していること」が求められます。単なる登録のみではなく、毎日の勤務実態があるかどうかを社会保険証や雇用契約書の写し等で証明する必要があります。
専任技術者が満たすべき資格や経験には以下の3パターンがあります:
- 1級建築施工管理技士、1級土木施工管理技士などの1級国家資格保持者
- 監理技術者資格証(実務経験に基づく取得可)を有する者
- 主任・現場監督等として全体を統括していたことを立証できる指導監督的実務経験者
とくに実務経験ベースで申請する場合、第三者による証明書類や過去工事記録など煩雑な準備が必要になり、書類不備によって不許可となることも少なくありません。
また、一般建設業では2級資格や下位レベルでもOKだったケースがありますが、特定建設業ではより高度なマネジメント能力と総合的な現場統括力を持つことが評価されるため、同じ「専任」という言葉でも内容はかなり異なります。
| 技術者区分 | 要件・補足説明 |
|---|---|
| 1級国家資格 | 1級施工管理技士など。有資格確認でクリアしやすい。 |
| 監理技術者 | 監理技術者講習受講 + 実務経験確認あり。 |
| 実務経験者 | 主任/現場責任として通年指導実績 + 客観資料必須。 |
- 技術者は申請会社の常勤職員である必要あり
- 監理技術者資格者は実務経験が重視される
- 一般建設業との技術者要件の差異に注意が必要
一般建設業と特定建設業の許可要件の違い

同じ「建設業の許可」でも、一般建設業と特定建設業では目的とハードルがまったく異なります。
一般建設業は中小工事が中心で、元請として下請に出す金額が少額な範囲であればこの許可で足ります。
一方、特定建設業は下請代金が5,000万円(建築一式なら8,000万円)以上になる工事を発注する元請として必要な資格です。
よって、大型案件や公共工事に対応したい企業には特定建設業 許可 要件への対応が不可欠となります。
加えて、そのハードルを分けるのが財産的基盤と技術者配置要件。
特定では資本金や純資産など具体的な財務基準に加え、より高度な国家資格や現場経験をもつ専任技術者の常勤配置も求められます。
| 項目 | 一般建設業 | 特定建設業 |
|---|---|---|
| 工事規模 | 500万円以上 (一式工事:1500万未満) |
下請5000万以上の場合必須 (一式工事:7,000万以上) |
| 財産要件 | あり | 資本金2,000万以上+ 純資産4,000万以上 など |
| 技術者資格 | 2級施工管理技士等可 | 1級施工管理技士がメイン |
| 許可取得難易度 | 比較的取得しやすい | 書類精度・人材確保ほか高難度 |
上記のように「何をどこまで担うか」によって必要となる許可形態は明確に異なり、
戦略的な許可選択が企業規模拡大や信頼性向上に直結する場合も多いため注意が必要です。
特定建設業許可取得のための手続きと必要書類
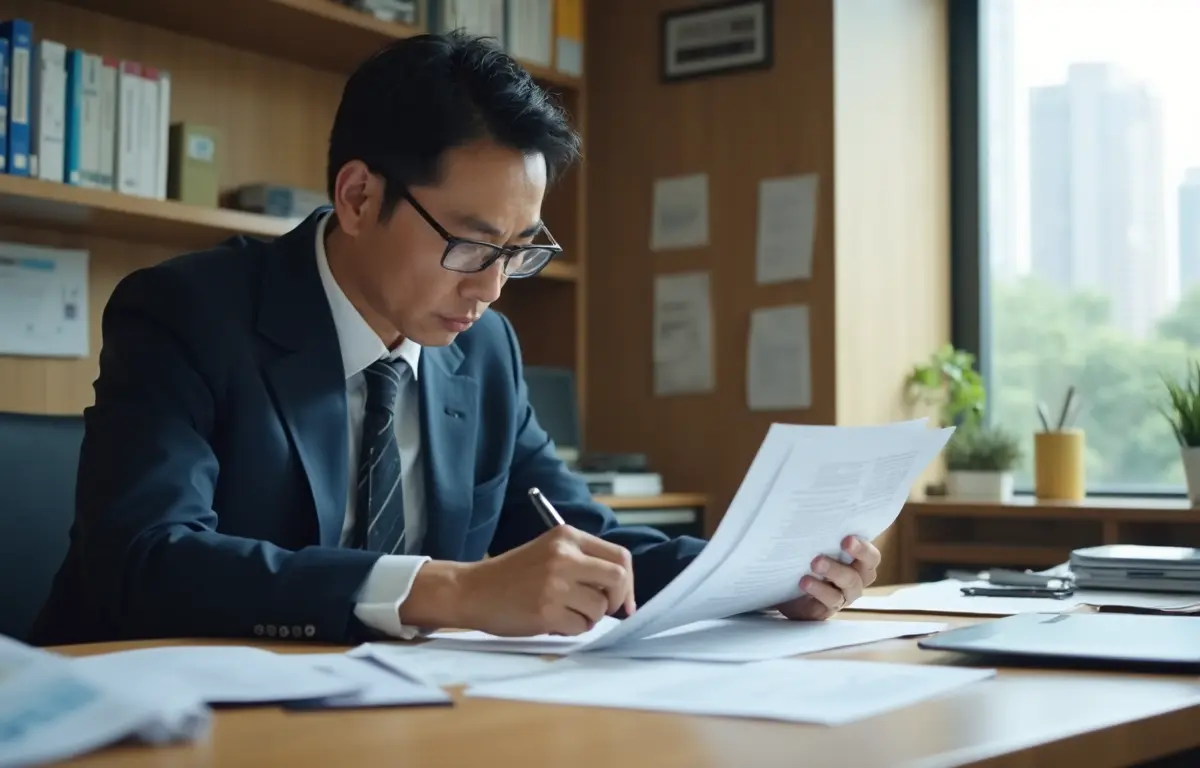
「特定建設業 許可 手続き」を進める際にまず押さえておくべきなのは、申請書本体以外にも多岐にわたる添付書類が必要となり、しかもその内容に不備があると簡単に差し戻されてしまうという点です。
いくら実態上要件を満たしていても、「証明できる文書」が整っていない限り、役所側はその内容を認定しません。
基本的な手続きとしては、まず直近決算が終わっていることを前提に、市区町村 or 都道府県などの監督行政庁への申請書提出から始まります。
このとき「提出先」は会社所在地によって異なるため、一律ではなく必ず事前確認が必要になります。
地味だけど侮れない落とし穴は、「技術者関連書類」と「財務関係資料」の両方で細かい確認不足による差し戻しパターンです。担当者レベルでよくありがちなのが、社会保険証のコピー漏れや役員履歴書に一部空欄があるケースなど、小さいようでいて致命的なミスになり得ます。
以下は特定建設業許可申請時に揃えるべき代表的な「建設業許可 必要書類」のリストです👇
- 登記簿謄本
- 定款(目的欄や資本金額確認用)
- 財務諸表(貸借対照表・損益計算書など直近1期分)
- 技術者の国家資格証明や監理技術者資格証明
- 技術者の実務経験証明(対象者には工事契約書等添付)
- 雇用契約書や社会保険加入証明(常勤性確認資料)
- 役員および代表取締役全員分の履歴書・身分証明書
これらはすべて原本もしくは原本確認済み写しで求められることが多く、とくに財産要件クリア後でも気を抜けない部分です。
また、管轄する行政庁ごとに若干様式や必要部数が異なる場合もあるため、自社所在地のルールを把握したうえで確実な準備を進めましょう。
特定建設業許可のポイントと取得の現実的対応策
特定建設業 許可 要件が厳格なのは事実ですが、正しい準備と戦略さえあれば、中小企業や新設法人でも十分に取得可能です。まず覚えておきたいのは、一般建設業許可を持っていなくても、特定建設業許可だけを直接申請できるという点です。
そして、会社設立直後であっても、「資本金2,000万円以上」「純資産4,000万円以上」の両方を準備し、かつ1級資格保持技術者などが常勤として所属していれば条件的には合格ラインに達します。問題はその状態をどうやって作るか。そこにこそ取得戦略の工夫が必要になります。
一例として、以下の3つは実務でよく使われている合法的な対策手段です👇
- 1級資格者を採用し要件を充足
→ 外部から施工管理技士など有資格者を雇用し常勤性証明付きで要件クリア - 子会社を用いて別法人で許可を取得
→ 親会社では要件不足だったため、新規法人作って最初から許認可仕様で設立・別体で特定業許可獲得
なお、「建設業許可 名義貸し」は当然ながら違法行為であり、摘発されると営業停止や罰金など重い処分対象になります。「裏ワザ感覚」で他人名義借りたりする方法はNGです。
あくまで合法かつ透明な手段に絞って対応することが最大の近道と言えるでしょう。
特定建設業許可の更新要件と注意点
特定建設業 許可 要件を満たして取得できたとしても、それで終わりではありません。建設業許可は取得から5年ごとの更新が義務付けられています。
この「更新」では、初回申請時とまったく同じハードルが再び課されます。
たとえば赤字決算が数期続いた結果、バランスシート上で欠損比率が基準を超えてしまうと、それだけで「更新不可」になる可能性もあります。経営上の一時的な数字でも容赦なく判断されるため、常に自社の財務状態をチェックする体制構築が重要です。
また許可期間満了日の30日前までに手続きを完了しなければならず、もし期限を過ぎれば新規取得扱いとして審査や書類提出がすべてやり直しになります。
以下はスムーズな更新に向けて必ず押さえるべきポイントです👇
- 更新期限の数年前から準備を開始する
- 財務管理体制を整備し要件を満たし続ける
- 技術者の在籍確認と書類の最新化を忘れないこと
特定建設業 許可 要件についての結論
特定建設業許可の取得に向けて、必要な要件をしっかり理解することは、確実な一歩を踏み出すための鍵です。これらの情報を把握することで、申請時のミスを避け、不許可やトラブルを減らすことができます。特定建設業許可は、財産的基礎や技術者の要件に応じた適切な準備が求められるため、一つ一つの手続きに注意を払いましょう。最後までお読みいただきありがとうございました。この知識があなたのビジネスの成功につながることを願っています。必要に応じて、専門家に相談することも検討してください。


