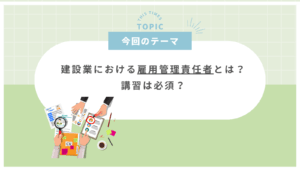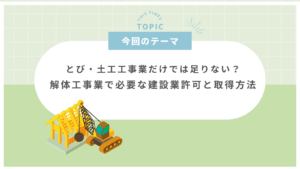【最新版】今動かなければ取り残される!? 建設業に必須の「建設キャリアアップシステム(CCUS)」とは
建設キャリアアップシステム(CCUS)は毎年改正やシステム変更があり、クセもあって建設業の皆さんにとって使いやすいものではありません。建設キャリアアップシステム(CCUS)を代わりに扱えるのは、元請企業やCCUS登録行政書士に限られます。
しかし、CCUS登録行政書士であっても、積極的に対応できている人は非常に少数です。多くは登録代行だけを請け負い「荒稼ぎ」を狙っているだけ。建設業者にとって聞きたくても聞けない、そんな状況が続いています。
ですが、社長にとって今動かなければ取り残されるリスクが上がっています。

なぜ行政書士はCCUSに取り組もうとしないのか…?
理由は明白で、CCUSは現場実務に直結し、しかも建設業法・労働安全衛生法・行政手続といった横断的かつ複雑な知識が求められるからです。施工体制台帳や安全書類、労務管理、労災・社会保険の知識などが絡む領域になれば、知識不足で対応できない専門家も多いのです。その結果、建設業者がCCUSについて相談できるプロフェッショナルが存在しない──そんな現場の声を、私たちは日々受け取っています。
当事務所はこうした現状に向き合い、現場と法律の橋渡し役として、建設業の未来を見据えた支援に取り組んでいます。
今回は、建設業界の今後に直結する「CCUSの必要性」について、現場目線で整理しました。
CCUSは人手不足対策から建設業のメインシステムへ変貌
建設業界は現在、慢性的な人手不足と高齢化という2つの大きな課題を抱えています。その中で、優秀な技能者を適切に評価し、確保できる企業こそが今後生き残っていくでしょう。
それは、建設業法改正の方向性にも表れています。
- 技能者の処遇改善
- 適正な賃金支払い
- 働き方改革による労働時間の適正化
これらが義務として明文化され、対応できない事業者には行政指導、公共工事の受注停止、入札排除といった直接的なリスクが発生するようになっています。2025年の制度改正を契機に、「CCUSを活用していない企業=建設業ではない」のような傾向が急速に強まっています。
さらに元々は人手不足対策だったCCUSですが入退場管理や安全書類などと波及していき、徐々に建設業の中核システムに形が変わっていっています。つまり、いまや「CCUSに登録していない建設会社や技能者は、現場から締め出されるリスクを抱えている」のです。
技能者・会社にとって「適切な登録=存在を証明できない」リスク
技能者にとっても「CCUSのIDを持たない=存在を証明できない」という深刻な問題が発生しつつあります。技能者IDは施工管理技士の受験資格や外国人の在留資格変更、実務経験証明などにも活用される流れが予想されています。今後はIDがあるだけでなく、自社の状況を反映したものにしていく必要があります。
というのも、CCUSが導入されてから最初は大手ゼネコンがIDを発行することを優先しました。元請が下請のデータをサービスでやってあげたわけですが、元請の事務員の負担は相当なものです。そこで、事務を簡略化するために下請の状況とは一致してない情報で登録していったのです。
例えば、技能者を正しい職種で登録していないと、いくら施工実績を積んでもキャリアにはなりません。土木工事をしているにもかかわらず、建築工事として登録されてしまえば、履歴は“死んだ勤務データ”となります。「とりあえず登録すればよい」と処理された情報が、今後、業界全体の信頼性を損なう大きな問題になるのは時間の問題です。
さらに、施工体制台帳や安全書類への監査は年々厳格化しており、それらを正しく作成・点検できる元請や行政書士はごく一部に限られています。
いわば、職人の“マイナンバー”的な役割を担い始めているのです。
もちろん、建設業許可取得時の要件確認にも波及していくでしょう。
今なら「行政書士なら手続きできるんだろ?」だけで選んでいる社長にとって、どれだけ建設業のことを研究している行政書士を獲得できるかが経営リスクに直結します。
CCUSを導入・活用すれば、600万円以上の人件費を削減できる可能性も
多くの現場では、建設業法により技術者の現場配置が義務化されています。しかし、技術者は慢性的に不足しています。そんな中、CCUSを導入・活用しておけば、技能者の履歴が明確になるため、兼任・兼務が認められやすくなります。
結果として、別の技術者を新たに雇わずとも現場対応が可能になり、年間数百万円単位の人件費削減につながる可能性があります。さらに兼務した現場から得られる利益も増えるでしょう。
特に既に公共工事に関わる建設会社にとって、このコスト効果は見逃せません。
民間の下請業者にも「ミニ経審」制度が波及
国は、CCUSの活用を経営事項審査(経審)に連動させる方向で動いています。特に東京・埼玉エリアではモデル事業としてすでに運用が始まり、「CCUS登録人数」や「活用状況」がスコア化され、加点対象として評価されます。
「うちは民間工事だから関係ない」と思った方も注意が必要です。
今後、施工体制台帳や安全書類、入場管理など様々な管理業務がCCUSとリンクしていき、自社の施工能力のスコア化やランク付けが業界全体に広がります。元請だけでなく、下請の立場であっても、CCUS未対応の会社は“選ばれない側”になってしまいます。
元請責任の強化と情報の透明化が急速に進行中
2023年以降、施工体制台帳の記載義務や連絡員の設置義務が強化され、行政が直接データを閲覧できるAPI連携も実装が進んでいます。これにより、形式だけの書類ではなく、リアルタイムで信頼性あるデータを提出することが強く求められる時代になりました。
現実に、施工体制台帳の不備によって行政処分を受けた事例も出ており、今後この動きはさらに強まっていくでしょう。
プロに任せる価値|「CCUSに対応できる専門家」と組むべき理由
建設キャリアアップシステム(CCUS)は、単なる制度ではありません。建設業界の構造そのものを変える“本質的な変化”です。
「働いたのに働き損」にならないよう、技能者のキャリアを正しく反映させ、会社の評価・利益につなげていくためには、現場と法制度の両方に精通した専門家と連携することが重要です。
当事務所では、CCUS登録代行はもちろん、施工体制台帳、現場管理書類の支援も行っていきます。
“変化に乗るか、取り残されるか”
今まさに、その分かれ道に立っているのです。