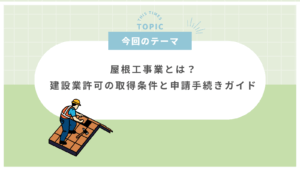社長が急死!息子がいたのに建設業許可が失われた実話
当事務所では「建設業許可は社長の人生と似ている」と言っています。それは建設業許可が次の世代にも引き継がれていくものでもあるからです。しかし、できないケースもあります。それは「事故」にも似ていますが何度も防ぐチャンスがあることも多いです。
今回は経営業務の管理責任者(経管)が親から子に引き継げずに許可取り消しになったケースをご紹介します。実際に当事務所でご相談があったものを基にしていますので、社長の会社にも襲ってくるかもしれません!
経管が急死!建設業許可が失われた具体例
当事務所では経管が不在のときの記事があります。とても読んでいる方が多く、みなさんにとって関心が高い内容ですよね。
<経営業務の管理責任者(経管)とは?不在時の対応策と許可取得のポイント>
では、今回のケースです。
従業員数約10名の建築施工会社。社長は60代半ばで職人気質。財務も自分で見るし、施工もできる。行動力もあって判断も速かったそうです。そんな社長にはすでに10年以上自社で勤務する30代後半の息子がいて財務以外は一通り任せられるレベルになっています。すでに建築施工管理技士の取得済みです。
健康状態に全く問題がない社長は70歳には引退しようと考えていましたが…、ある日突然亡くなってしまいました。数カ月後、当事務所にご連絡頂いた息子さんが今回の相談者です。
会社の全部履歴事項証明書(登記簿)を見ると、息子さんは社長が亡くなるに合わせて取締役として登記されていました。つまり、息子さんは建設業許可の要件である経営経験5年がないのです。
このままでは建設業許可が維持できません。
結論ですが、このケースでは建設業許可は取消しとなっています。
どうすれば防げたのか?
父である社長が息子さんを早い時期に取締役として登記さえしておけば済んだ話です。建設業許可では法人の場合、取締役であったかは基本的には全部履歴事項証明書(登記簿)で確認します。
税務なども絡む話ではありますが、登記費用自体は登録免許税と含めても6~8万円程度で済みます。しかし、社長としては「息子はまだ早い」「忙しいから後回し」などとついそのままになってしまいます。行政書士である私も建設業で役員経験がありますが、社長の周辺が説得するのには骨が折れたと聞いています。
息子さんは「どうして周りの専門家が声をかけてくれなかったんだ」とおっしゃっていました。
他に方法はなかったのか、行政書士は何を見ていったか?
書けない要素は省いているので、読まれている方はお察し頂ければと思います。
さて、まっさきに建設業許可を維持するために考えたのは「他に経営責任者はいないのか?」ということです。建設業許可には救済制度がいくつかありますが、基本的には法律上の要件を満たしている必要があるので今回のケースでは使いにくい。使えたとしても死亡から数ヶ月経過してしまっていて適用外の可能性もあります。
※30日以内ルールがあっても行政によって柔軟に対応してくれることがあるのでお問い合わせ下さい。
参考(関東地方整備局PDF):https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000877209.pdf
ヒアリングの結果、経管の可能性がある人はいませんでした。一時的に外部から招く案もお話しましたが、社会保険に加入は必須なので、人件費は増えます。外部の人間が入れば、さまざまな経営リスクを負う負担のほうが大きいという決断をされました。
建設業法 施行規則第7条第1号イ(3)は使えないか?
法律要件のハードルが高い
「建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、 施行規則第7条第 経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有していること」
これは可能性がありえましたが結果的にはこれも選択肢から外れていきました。この規定は今回のように息子さんや会社の部長職の方などを経管にすることができます。救済枠の1つですが、群馬県庁でもほぼ事例がなく、事前相談の上個別具体的に審査することになります。
この要件のハードの高さは証明書類が揃わないことに尽きます。
群馬県庁の手引きは以下の通り記載があります(R7.5.3時点)
群馬県の手引きより抜粋
次の全てを提出してください。これらの資料が揃わない場合は審査を行いません。
ア 執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にある ことを確認するための資料
例:組織図
イ 業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部門である ことを確認するための資料
例:業務分掌規程
ウ 取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受け、業務執行 に専念する者であることを確認するための資料
例:定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規定
※書かれてはいませんが辞令の提出でも可能性はあります
エ 建設業を営んでいたことを証する資料(次のいずれか)
・建設業許可通知書の写し(5年分) ・工事契約書・注文書等の写し、発注証明書(1年1件、5年分、注1)
毎年1件、つまり6年分の組織図、業務分掌規程、辞令などが必要と考えられます。もちろん、当時のものが必要です。大企業向けのルールと思われがちですが、書類さえあれば数人規模の会社であってもOKです。
これだけの文書整理をするなら普通は取締役として登記するのが普通。
とはいえ、行政書士としては将来に備えて組織図などの整備を提案するのも仕事だと思います。
実態があったかどうかが肝心!!
読んだ方は思ったかもしれません。
「あとから組織図とか作っちゃえばいいじゃん」
ここらへんはセンシティブな話題ですが、あえて書いてみます。行政書士から言うともっとも重視していることは、本当に息子さんが経営を補助していたかどうかです。今回のケースでは微妙なラインでした。
この審査は事前相談とあるように、チャレンジしてみないと行政側も分からないということです。では行政側から見てみると、組織図などの書面は自己申告なわけですよね。審査する行政としても「本当か???」と裏を取る必要があります。
具体的には他社が証明してくれるかどうかです。
群馬県ではありませんが、当時の税理士とのやり取りやお客様との契約条件の打合せのメール、当時の役員との報酬の差を示す資料などを求められたという事例があります。そうなると、本当に補助をやってなければ証明することは不可能です。
でっちあげてくれと言うは簡単ですが、疑問を持たれたときにボロがでてしまえばカバーできません。もちろん、その前に当たり前ですが虚偽申請で犯罪です。
その会社はどうなったのか
経管の要件が満たせないなら「時が解決するのを待つ」しかありません。当然ながら500万円以上の工事は受注できないので事業規模は縮小する可能性があります。公共工事関係の仕事や民間工事も元請が嫌がることなり、取引関係も見直しが必要になりました。
息子さんは嘆いても仕方がない、やれることをやろうと逆にポジティブではありますが、ポロッこぼされたことがありました。
「どうして親の行政書士が一言いってくれなかったのか、代書屋とバカにされても仕方がないじゃないか」…と。
建設業許可証はただの紙切れではない
当事務所の記事では何度も「建設業許可証は社長の人生、命と同じ」と書いてます。世代交代を前提にお取引させて頂いている会社様も多く、決算変更届などのタイミングでは対策をお話しています。
一方で許可を取ったら、はいさよなら!という行政書士など専門家も少なくありません。許可証を失って事業が停滞すれば、経営者や従業員の家族の人生はどうなるのでしょうか。
全国の建設業様がこの記事を読まれると思います。そんな風に会社のことを心配してくれる専門家をパートナーにしてください!きっとお住まいの地域にもいるハズです!