塗床工事の建設業許可に必要な業種分類と取得の流れを徹底解説
この道を歩むことで、より確実に夢を形にしたいと考えるあなた。塗床工事の世界に飛び込もうとするにあたって、建設業許可の取得は一つの大きなハードルです。どの許可が必要なのか、手続きがどれだけ複雑なのか、これらの不安を抱えたまま迷ってはいませんか。このガイドを通じて、あなたのその疑問を解消し、次なるステップへと踏み出す自信をあたえることができるでしょう。
塗床工事に必要な建設業許可の種類と業種分類

塗床工事を実施するには、工法や目的に応じて正しい建設業許可の「業種分類」を取得する必要があります。
まず、基本となるのは「塗装工事業」です。塗料や樹脂を床面に塗布する行為は、国交省が示すガイドライン上、「吹付け・塗付け・貼り付け」作業として明確に定義されており、多くの樹脂系塗床工事はこの区分に該当します。ライニングやエポキシ系の薄膜施工もここに含まれます。
次に、厚みのあるモルタル状の材料(例:エポキシモルタル)をコテで成形して仕上げる場合、それは壁・床問わず「左官工事業」として扱われます。鏝(こて)による成形が主であれば、「左官」が中核になります。
もし防水性を強調するような仕上げ——例えば厨房などの水場向けで、水漏れ対策が主目的の場合——には「防水工事業」に該当します。ウレタン塗膜防水などが該当例です。
一方、「内装仕上工事業」はよく混同されがちですが、本来これはフローリング・カーペットといった『張りもの』による床仕上げを指します。したがって、塗料や樹脂を使って直接床面を施工する塗床は通常、この区分には入りません。
複数業種取得も現場では珍しくありません。例えば:
- リフォーム会社ならば「内装仕上」と併せて、「塗装」「左官」もカバーしているパターン。
- 一人親方でウレタンやエポキシ主体なら「塗装工事業」のみでもOK。ただし厚みある補修や左官的作業が多いときは注意。
- 防水施工にも一定対応しているなら、「防水工事業」の追加取得がおすすめです。
以下に、代表的な施工内容ごとの対応許可区分をまとめた表をご覧ください。
| 工法・目的 | 該当する業種許可 |
|---|---|
| 樹脂塗布 | 塗装工事業 |
| 厚塗りモルタル | 左官工事業 |
| 塗膜防水 | 防水工事業 |
| 床材張り | 内装仕上工事業 |
主たる施工内容ごとに適切な法人・個人許可を取ることで、請負範囲も法的に明確化できトラブル回避につながります。特定分野だけではなく複合的な施工スタイルの場合、自社の強みに応じた組み合わせ許可取得が理想です。
建設業許可を取得するための4つの主な要件(塗床工事業者向け)

塗床工事で建設業許可を取得するには、次の4つの主要な要件をすべて満たす必要があります。国交省が定める「一般建設業許可」の基準に沿って、それぞれ詳しく解説します。
-
経営業務管理責任の体制
現在では、特定個人に限定した「経営業務管理責任者(いわゆる“経管”)」配置義務は廃止されています。その代わり、会社全体として経営業務を的確に管理できる体制があるかどうかが審査されます。具体的には、「常勤役員等」——取締役や執行役など——が過去に5年以上、建設業の経営経験やこれに準ずる実績を有していることが原則条件です。過去勤務していた企業や自営での経験も対象になり得ますが、証明資料(登記簿・確定申告・契約書など)の整備が必須です。 -
専任技術者の配置
施工品質と安全性を担保するため、各営業所に専任で常勤する「技術者」が必要です。塗床工事では多くの場合、「塗装工事業」で申請されます。この場合、有資格者または実務経験者であることが求められます。代表的なパターンは以下の通りです:
- 1級または2級建築施工管理技士(仕上げ)であれば即適格
- 指定学科卒+3~5年実務
- 実務経験のみで10年以上も可能
複数業種を追加取得する場合(例:左官、防水)、その分だけ専任技術者を兼ねて構成できるか確認されます。ただし兼務には厳しい常勤要件がありますので注意しましょう。
- 財務的基盤の証明
安定した事業継続性も判断項目です。次のいずれか一方に該当すればOKです:
- 自己資本500万円以上(決算書・貸借対照表等で証明)
- 金融機関から500万円以上調達できる能力(残高証明・融資枠など)
法人だけでなく個人事業の場合も同様条件となります。不足している場合には一時増資や親族借入による残高調整といった対応策も考えられます。
- 誠実性と欠格要件への該当確認
反社会勢力との関係や法令違反歴などによっては許可審査で不合格になることがあります。具体的には:
- 過去5年以内に重大な法令違反歴がないこと(不正請負・脱税・暴力行為等)
- 現在破産手続中でないこと(免責確定済なら問題なし)
- 成年被後見人等としての制限状態がないこと
役員全員について上記チェックがありますので、人選にも注意しましょう。この点では「役員=看板だけ」の構成は危険なので絶対避けてください。
塗床工事業者として建設業許可を取得する流れと必要書類
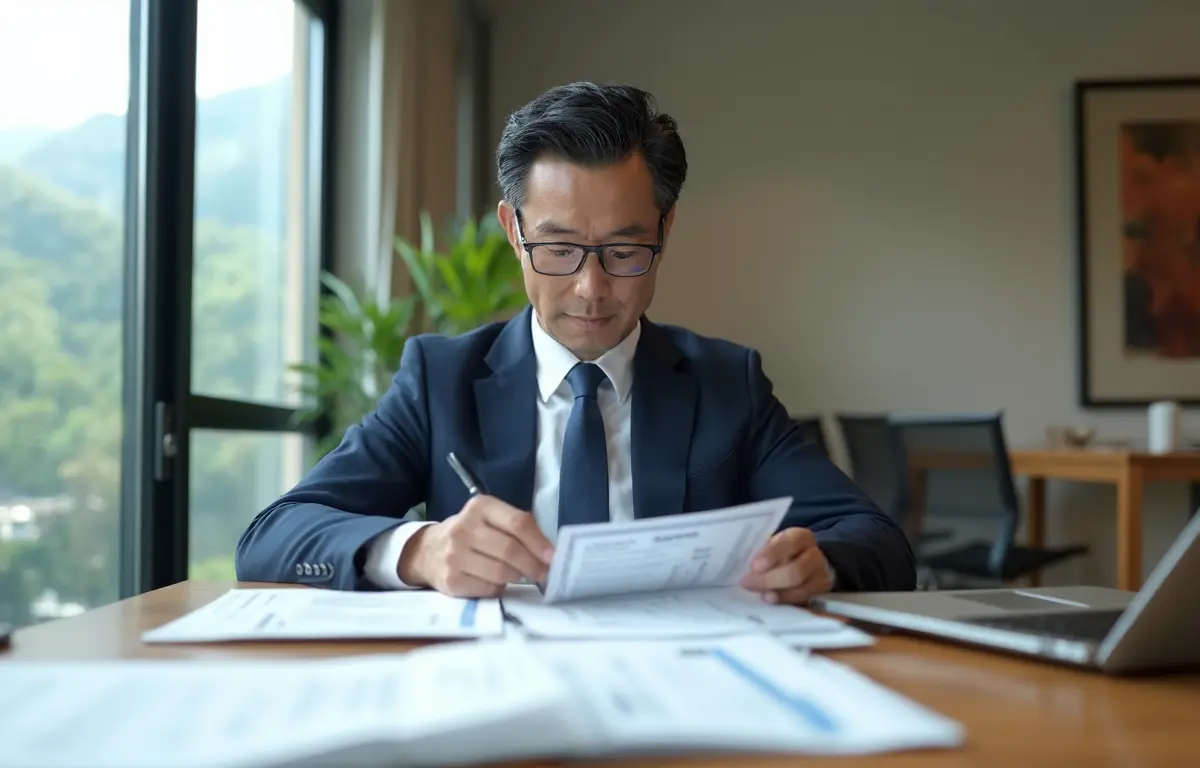
塗床工事で建設業許可を取るには、まず自社の状況を冷静に見極めたうえで段取りよく申請プロセスを踏んでいく必要があります。ここでは、許可手続きの全体像と書類準備のポイント、申請にかかる期間について具体的に説明します。
申請の基本的な流れ
塗床工事の場合、多くが「塗装工事業」で申請されますが、こて塗り仕上げが中心なら「左官工事業」も含まれます。このように自社の主要工法や得意領域を明確化したうえで、どの業種区分が該当するか判断してください。
一連の申請プロセスは次のとおりです:
- 自社状況の確認(業種分類・人的要件・財務要件などの整理)
- 必要書類の収集と作成
- 申請先の選択(都道府県知事または国土交通大臣)
- 書類提出と受理
- 審査(1〜3か月)
- 許可証の交付
営業所が1都道府県内のみの場合は「知事許可」、複数エリアにある場合は「大臣許可」となります。群馬県では審査期間は概ね1.5〜2.5か月程度が目安です。
書類準備について
申請時には実務経験や財務、経営管理体制など幅広い観点から審査されます。出すべき書類は多岐にわたり、不備や漏れがあると修正対応でかなり時間を取られてしまいます。代表的な提出書類をまとめると以下になります。
| 書類名 | 概要 |
|---|---|
| 登記事項証明書 | 会社の法人情報 |
| 納税証明書 | 税務署で取得 |
| 決算書類 | 直近の財務状況 |
| 資格証明/実務証明 | 専任技術者要件確認用 |
ほかにも印鑑証明や事業所写真、役員全員分の住民票や履歴事項まで細かく要求されますので、余裕を持って準備しましょう。特に10年以上実務経験で専任技術者認定を受けたい場合、裏付ける契約書・写真・元帳コピーなども求められます。
滞りなく進めるためにも、自社単独だけで対処せず早期段階から専門家へ相談しておく方が安心です。時間ロスも減らせますし、不支給リスクも低減できますよ。
塗床工事の建設業許可取得にかかる費用とスケジュール

塗床工事で建設業許可を取得する場合、どのくらいの費用と期間がかかるのかを明確に把握しておくことが大切です。ここでは、申請時に発生する主な支出項目と、手続き全体にかかる日数の目安を整理しました。
まず、知事許可(都道府県単位)で必要となる「手数料」は以下のようになっています。登録免許税等は一切不要です。
| 項目 | 費用(目安) | 備考 |
|---|---|---|
| 新規申請手数料 | 90,000円 | 収入証紙で納付 |
| 業種追加 | 50,000円 | 同様に収入証紙 |
| 更新申請 | 50,000円 | 5年ごとに必要 |
| 専門家報酬 | 150,000〜350,000円 | 難易度・実務証明有無により変動 |
なお、専門家へ依頼せず自社内で申請する方法も可能ですが、書類作成や証明準備が煩雑なため、多くの事業者は行政書士などへ外注しています。報酬額には個人差・地域差がありますが、証拠資料提出が複雑な「実務経験のみ」で技術者認定を受けるケースでは上限額まで膨らむ傾向があります。
続いて「期間」についてですが、新規許可申請から交付までは全国的には約1〜3か月程度です。群馬県の場合はやや早めで、おおむね1.5〜2.5か月程度が多く見られます。ただし審査中に追加資料提出が求められることもあるため、「提出後すぐ施工予定」といったスケジュール設定には注意してください。
塗床工事業で建設業許可を取得するメリットとは?

塗床工事において「建設業許可」を取得することは、単なる義務ではなく、取引先・契約規模・信用あらゆる面でのビジネス展開に直結する武器になります。
以下に、塗床工事業者が建設業許可を取得する主なメリットを整理しました。
- 税込500万円以上の案件を合法的に請け負える
- 元請・ゼネコン・大手とのビジネス契約締結が容易になる
- 公共工事への入札参加資格の前提条件として必須ステップとなる
- 登録企業としての信頼性向上で金融機関からの与信評価が高まる
- アウトソーシング先やクライアントに対して法令順守姿勢を明確化できる
建設業許可がない場合、税込500万円以上の塗床関連工事(材料費+施工費含む)は受注そのものが違法になります。とくに近年は元請側(ゼネコン・施設所有者など)のコンプライアンス意識も高く、「許可無し=下請できない」場面も増加中です。
また、建設キャリアアップシステム(CCUS)導入や公共インフラ整備への関心が高まる中で、経営事項審査 → 入札参加資格という流れへの対応も必要です。そのためにも建設業許可の有無は避けて通れません。
さらに金融機関による融資審査でも「正式な認可を得た上で安定運営している会社」と評価されやすいです。これは特に創業間もない企業には大きなプラス要素になります。
塗床工事業の許可取得後に注意すべき法令遵守と更新
塗床工事で建設業許可を取得したあとは、それで終わりではありません。運用を継続するには定期的な法令遵守と更新手続きが必要です。
まず、建設業許可の有効期間は5年間です。この「更新手続き」は忘れずに行わないと、許可失効=無許可営業となり違法になります。遅れずに、都道府県や大臣へ所定の書類を提出しましょう。
さらに、「決算変更届(毎事業年度終了後4カ月以内)」の提出も義務となります。財務状況や経営体制が継続して要件を満たしているか、都度報告することが求められる仕組みです。
また、「専任技術者」は常勤体制が条件のため、退職や異動で不在になると要件不備となります。その時点で法的リスクが生じるため、人材配置の管理にも気をつけましょう。
名義貸しや虚偽記載などの法令違反は、厳しく取り締まられており、一発で「許可取消」となることもあります。安定運営には社内体制の逐次見直しとコンプライアンス意識の継続が不可欠です。
塗床工事 建設業許可を取得するために知っておくべきこと
塗床工事を始める際、建設業許可の取得が重要な一歩であるということをお話しましたが、具体的にはどの許可を取得すべきか不安を感じていたかもしれません。実際には、塗床工事は塗装工事業や防水工事業の一環として認識されることが多く、それぞれに応じた許可が必要です。
この許可取得に向けて重要なのが人的要件です。経営責任者と技術責任者の役割、そしてそれぞれがどのような基準を満たす必要があるかについても説明しました。これにより、具体的に誰がどの役割を担うべきかを判断できるでしょう。
許可取得の準備を進めるにあたっては、書類準備に時間をかけすぎないよう、抜け漏れなく計画的に進めることが求められます。これには、申請ミスを防ぐために専門家のアドバイスを活用することも検討すべきです。
今回のガイドがお役に立つことを願っています。塗床工事業で成功し、新しい扉を開くために頑張ってください!


