建設業 許可 取得条件を完全解説 初心者でも理解できる6要件と申請成功のポイント
初めての建設業許可申請で、何から手をつけるべきか迷っていませんか。実務経験や資本金などの条件が複雑に感じても、この6つの要件を順に理解すれば、許可取得への道は意外と明確になります。本記事では、初心者でも迷わず進められる具体的な基準と成功のコツを、実例を交えて解説します。
建設業許可の取得条件6要件とは?基本ポイントの整理

建設業 許可 取得条件は、国土交通省令で定められた6つの要件を満たすことが必要です。以下に、それぞれの判断基準とポイントを整理しました。どれか1つでも欠けると許可が下りないため、申請前に全項目を確認することが重要です。
① 経営業務を管理できる体制が整っていること
経営業務の管理責任者の要件は、従来「経験5年以上の経管1名必須」でしたが、現在は柔軟化され、常勤役員等1名に加え、その補佐者によるチーム体制でも証明可能です。
同一営業所内に限り専任技術者との兼任も認められます。
② 専任技術者を営業所ごとに配置していること
専任技術者の要件は「資格・学歴・実務経験」のいずれかで判断されます。
- 一般建設業:指定学科大卒3年以上/高卒5年以上/実務10年以上/2級施工管理技士など
- 特定建設業:1級施工管理技士または監理技術者資格者証保有者 等
いずれも常勤である必要があります。
③ 誠実性を有していること
誠実性とは、請負契約や労務契約などを公正・適切に履行する能力があることを指します。過去に請負トラブルや虚偽申請などがあった場合は、この要件で不許可になる可能性があります。
④ 財産的基礎または金銭的信用があること
財務諸表の提出要件にも関連します。
- 一般建設業:自己資本500万円以上等で証明(預金残高証明でも可)
- 特定建設業:資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上
直近決算書類で判断されます。
⑤ 社会保険・雇用保険等への加入義務を履行していること
健康保険・厚生年金・雇用保険などへの加入は原則必須です。社会保険加入証明書や適用事業所番号通知書等の提出で立証します。
⑥ 欠格事由に該当しないこと
欠格事由と許可取り消し制度は密接です。過去5年以内に許可取消処分や禁錮刑以上の刑罰を受けた場合、また暴力団関係など反社会的勢力との関係がある場合も不許可になります。法令違反歴や破産未免責も審査対象です。
これら6項目すべてを満たすことで、建設業 許可 取得条件をクリアし、正式な申請へと進むことができます。
経営業務の管理責任者(経管)に求められる経験・体制とは

建設業 許可 取得条件の中でも、最も審査でつまずきやすいのが「経営業務の管理を行う体制」に関する部分です。2020年の法改正で要件が緩和され、以前のように「経営業務の管理責任者(経管)1名必須」ではなく、一定の経験を持つ常勤役員等と、その補佐によるチーム体制でも認められるようになりました。
経営業務の管理責任者の要件とは
従来は、建設業における経営経験5年以上を持つ人物のみが認定対象でした。現在も基本的な考え方は同じですが、「常勤役員等1名」または「その補佐を含む組み合わせ体制」のいずれかで足りると運用されています。
この“建設業に関し”という表現がポイントであり、「同業種である必要」はありません。つまり、土木工事会社から電気工事業への転用申請なども、建設業経験として評価されます。
例として、中小企業の代表取締役として5年以上建設業務を行った者や、他社で取締役・支店長など経営管理職にあった者が対象になります。法人の場合は登記簿謄本や就任期間証明書、個人事業主の場合は確定申告書などで証明します。
管理補佐による柔軟な証明方法
改正後は「主たる常勤役員1名」と「補佐的立場」にある人物(財務担当や労務担当など)の連携でも許可が可能です。
複数人で構成し、財務・人事・契約など各分野において適切な管理能力を有することを示せばよいとされます。その場合、組織図・職務分掌表・勤務実態資料などを提出し、実際に運営を把握していることを説明する必要があります。
営業所設置と常勤条件
常勤とは、「同一営業所内で日常的に勤務している状態」を指します。
週数回のみ出社하거나兼任拠点間を往復するだけでは常勤扱いになりません。給与支給記録や社会保険加入記録なども確認対象になります。同一営業所内に限っては専任技術者との兼任も可能ですが、その場合は両方の常勤要件が満たされる必要があります。
専任技術者の設置要件(一般と特定の違い)

建設業 許可 取得条件の中でも、専任技術者の要件は特に重要な審査項目です。営業所ごとに常勤で配置し、その技術者が施工管理や品質確保を担保できることが求められます。ここでは、一般建設業と特定建設業でどのような差があるのかを具体的に解説します。
一般建設業の専任技術者要件
一般建設業の取得要件は柔軟性があり、資格・学歴・実務経験のいずれかで満たせます。以下のいずれかをクリアしていれば申請可能です。
- 指定学科を専攻した大学卒業+3年以上の実務経験
- 指定学科を専攻した高校卒業+5年以上の実務経験
- 国家資格(2級施工管理技士、2級建築士など)の保有
- 学歴や資格なしの場合は10年以上の実務経験
このように複数ルートから証明できるため、中小規模事業者でも比較的申請しやすい構成になっています。
特定建設業の専任技術者要件
特定建設業では、発注金額4,000万円(建築一式6,000万円)以上の工事を下請けに出す場合が多いため、より高い専門性と管理能力が求められます。そのため一般とは異なり、「1級レベル」の国家資格または監理技術者資格証による裏付けが必須です。
また、国土交通省告示に基づき「指導監督的実務経験」として2年以上証明できる場合も認められます。工事現場で現場代理人や工事主任として管理に関与した履歴など、経営体制上でリーダーポジションを担った証明資料が必要です。
| 区分 | 資格 | 学歴+実務 | 実務経験のみ |
|---|---|---|---|
| 一般建設業 | 2級施工管理技士・建築士等 | 指定学科大卒+3年 or 高卒+5年 | 10年以上 |
| 特定建設業 | 1級施工管理技士・監理技術者証 | 該当なし | 指導監督的実務2年以上 |
専任技術者は原則として「常勤」であることも要件になっており、社会保険加入記録や給与支給資料などから勤務実態を確認されます。同一営業所内であれば経営業務管理責任者との兼任も可能ですが、その場合は両役割とも常勤条件を満たさなければなりません。
財産的基礎と金銭的信用の判断基準

建設業 許可 取得条件の中で、財産的基礎または金銭的信用の要件は「資金の裏付けがあるか」を確認する極めて重要な部分です。
ここを誤ると、他の要件を満たしていても許可が下りないケースがあります。
一般建設業における基準
一般建設業では「自己資本500万円以上」が目安です。
もし直近決算書上で自己資本が500万円未満でも、複数口座の預金残高証明で補える場合があります。
これは審査時点で実際に動かせる資金力を確認する意図であり、帳簿上の赤字よりも実質的な支払能力が重視されます。
提出書類としては以下が基本です。
- 貸借対照表(直近1期)
- 預金残高証明書(500万円以上)
- 金融機関からの信用証明書(任意)
これらにより「請負契約を履行できる経済的体力がある」と判断されます。
特定建設業における基準
特定建設業ではより高いレベルの基準が要求されます。
原則として以下2つを満たす必要があります。
- 資本金2,000万円以上
- 自己資本4,000万円以上
この基準は元請として下請総額4,000万円(建築一式6,000万円)以上を発注できるかどうかを見るためです。
実際には税務申告済みの直近決算書コピーで確認され、以下の場合は審査が不利になります。
- 債務超過状態
- 大幅な赤字計上
これらの場合、追加で預金残高証明や金融機関の融資枠通知書などを提出し、「短期的支払能力」を立証すると良いです。
財務諸表の提出要件と注意点
財務諸表は新規・更新ともに必ず必要です。法人の場合は確定申告書に添付された決算報告書、個人事業者は所得税青色申告決算書で代替できます。
記載内容の一貫性が重視されるので、以下に留意してください。
- 代表者住所・商号・印の日付一致確認
- 総勘定元帳など内部資料との突合一致
- 経理担当者署名漏れ防止
直近数期分の経営状況が不安定な企業でも、補完資料で誠実性と再生計画を示すことで評価される可能性があります。
決算書作成時のポイント
提出前には必ず「貸借対照表」に自己資本額が明確に記載されているか確認してください。
社内保留金調整や役員貸付処理が不適切な場合、審査官から再提出を求められることがあります。中小企業では税理士の確認印付き決算書が最も信頼性が高いと評価されます。
財産的基礎と金銭的信用は単なる数字条件ではなく、「工事履行能力」そのものを判断する指標です。したがって一時的な赤字でも対応策資料を添付すれば、十分に申請通過の可能性があります。
許可申請に必要な書類とチェックリスト
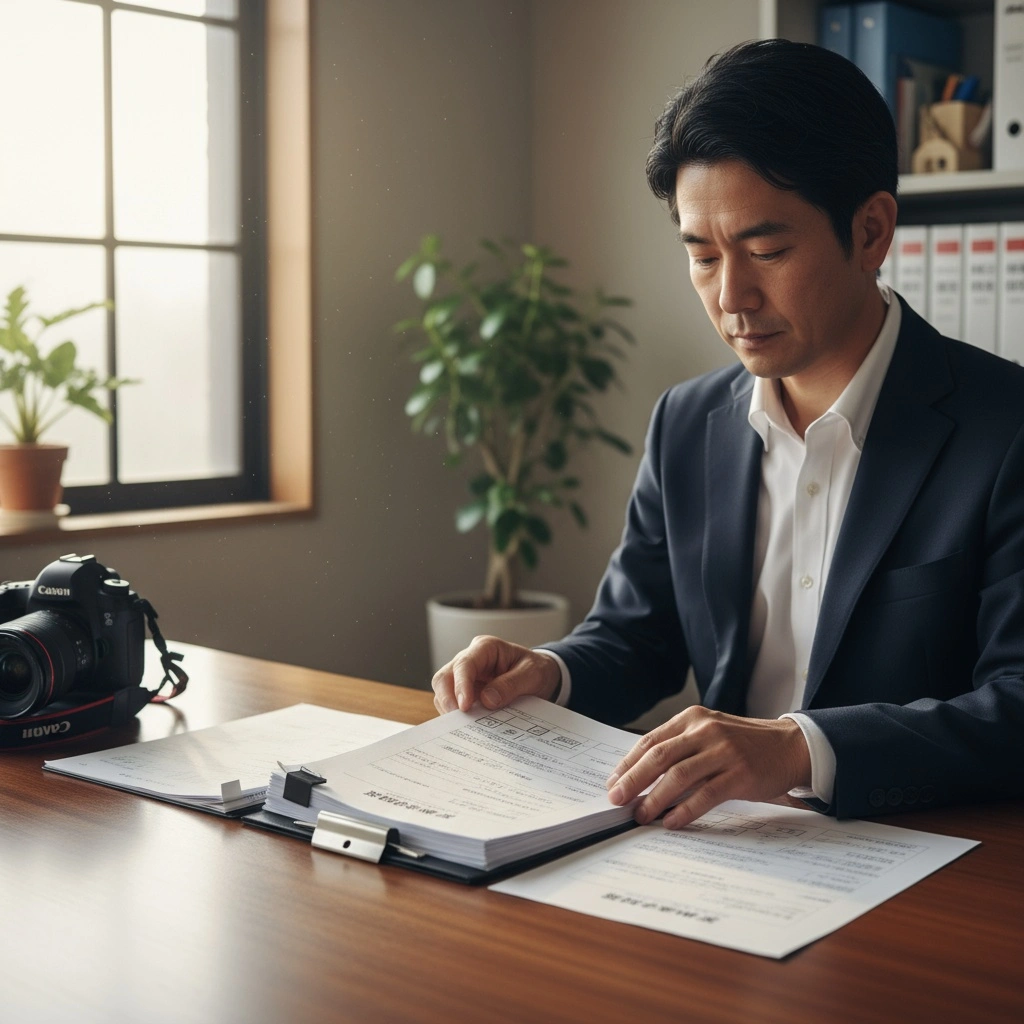
建設業 許可 取得条件を満たしても、書類不備があると審査で止まるケースが非常に多いです。ここでは、群馬県での知事許可申請を想定し、必ず準備しておく「申請に必要な書類一覧」と「提出時のチェックリスト」を整理します。
主要提出書類10点
以下の書類は原則すべて提出対象です。法人・個人で内容や形式が一部異なるため、自身の属性に合わせて確認してください。
-
登記事項証明書(登記簿謄本)
法人登記内容(商号・所在地・役員構成)が最新でなければ受理されません。発行後3か月以内の原本が必要です。 -
定款(法人の場合)
法務局登記簿と整合しているかを確認します。特に目的欄で建設工事関連が明示されている必要があります。 -
納税証明書
法人は法人税、個人事業主は所得税について、直近分を税務署で発行します。電子申請でもOKですが、収受印付きが望ましいです。 -
財務諸表(直近決算分)
貸借対照表と損益計算書をセットで提出します。一般許可では資金裏付け確認資料として扱われます。 -
技術者の資格証または実務証明書
専任技術者要件を立証する最重要資料です。施工管理技士・建築士資格証や実務年数証明などを添付します。 -
経営業務管理体制の経験資料
経営経験者の在籍期間が分かる登記簿写しや確定申告控え、人事辞令などを添付し体制を証明します。 -
社会保険・雇用保険加入確認資料
健康保険・厚生年金保険加入適用通知、雇用保険適用事業所番号通知書などを提出し、加入状況を立証します。未加入の場合は申請不可になることがあります。 -
事務所の使用権限証明資料
賃貸の場合は契約書写し、自社所有なら登記事項証明や固定資産台帳等で確認可能です。同じ所在地で電気・水道契約があるとなお良いです。 -
印鑑証明書(代表者)
発効日から3か月以内、有効期限切れに注意してください。同時に押印様式も統一させましょう。 -
添付チェックリスト(自治体指定様式)
群馬県では申請窓口備え付けまたは公式サイトよりダウンロード可能です。不足項目を防ぐため、この一覧に従って整理することが推奨されています。
提出前チェックポイント
以下の「許可申請のチェックリスト」を使うと、不備による差戻しを防げます。
- 書類すべて最新版か(発行から3か月以内)
- 登記簿と定款内容が一致しているか
- 社会保険番号や資格番号など数値誤りなし確認済みか
- 財務諸表の日付・社印一致しているか
- 添付漏れ箇所なし(特に補佐者資料)
これら5項目を正しく確認すれば、初回提出でもほぼ問題なく審査通過する可能性が高まります。
許可申請の流れと手数料、申請先の違い
建設業 許可 取得条件を満たしたら、次は正式な建設業許可の申請手続きフローに進みます。初心者でも迷わず進めるよう、知事許可・大臣許可それぞれの提出先や費用感、電子申請対応までを6ステップで整理しました。
① 許可種別の判定(知事/大臣、一般/特定、業種区分)
最初に行うべきは「どこに申請するか」を決めることです。
- 都道府県知事許可:営業所が1つの都道府県内にのみある場合。
- 国土交通大臣許可:複数都道府県に営業所を設置している場合。
さらに、「元請として下請総額4,000万円(建築一式6,000万円)以上を出す工事」があるなら、その業種では特定建設業となります。それ以外は一般建設業です。
② 提出書類の収集と作成
判定後は必要書類をそろえます。登記事項証明書、定款、決算書、技術者資格証など10点前後が基本です。各自治体公式サイトで最新版様式を入手し、押印漏れや発行日超過がないよう注意します。
③ 申請窓口の確認(各都道府県庁 建設業課等)
群馬県を例にすると「県土整備部 監理課 建設業係」が窓口です。他県でも概ね「建設業課」「土木課」など専用部署が担当します。郵送受付不可の場合も多く、本人または委任代理人による持参提出が基本です。
④ 手数料の納付(印紙または電子納付)
手数料(印紙代含む)は以下が目安です。
| 区分 | 新規 | 更新 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 都道府県知事許可 | 約9万円 | 約5万円 | 収入証紙で納付(窓口販売所等) |
| 国土交通大臣許可 | 約15万円 | 約5万円〜7万円 | 電子納付または郵便局販売印紙貼付方式 |
自治体によって収入証紙・印紙どちらか指定されますので窓口案内で確認してください。
⑤ 書類提出と受付
全書類をまとめて受付簿へ提出します。書類審査時に軽微な不一致があれば即座に電話やメールで補完要求が来ます。この段階で多い不合格原因は押印漏れ、発行日経過、書類の欠落です。
⑥ 審査および補正対応(30~45日程度)
審査期間は通常1ヶ月強です。内容確認中には追加資料提出要請や補正指示が来る場合も多く、修正完了後に最終認可日と通知書が発行されて許可番号が付与されます。
なお、一部自治体では段階的に電子申請を試行中であり、今後マイナポータル連携による完全オンライン化も予定されています。ただし2024年時点では対象限定運用のため、多くの事業者は依然として対面での書類提出が必要です。
特定建設業と一般建設業の違いと選び方
まず結論から言うと、「下請だから特定が必要」ではありません。
元請として発注した下請代金の合計が一定額を超えるかどうかが判断基準です。
一般建設業の取得要件
一般建設業の取得要件は、小規模工事や自社完結型の施工で足ります。主な条件は以下です。
- 専任技術者:2級施工管理技士または相当実務経験者(10年以上など)
- 財産的基礎:自己資本500万円以上または同等の金銭的信用
- 下請けを出す場合でも、総額が4,000万円未満(建築一式6,000万円未満)なら可
つまり、自社チームで完結可能なレベルか、中小規模企業は一般許可で十分です。
特定建設業の取得要件
大規模工事を元請として多くの下請けに外注する場合は特定建設業許可が必要です。条件は一般より厳格で、以下の項目が追加されます。
- 専任技術者:1級施工管理技士または監理技術者資格証保持者
- 財産的基礎:資本金2,000万円以上および自己資本4,000万円以上
- 審査時には直近決算書でこれらの要件が実質的に満たされているか確認されます。
追加書類として財務諸表、預金残高証明書などの提出が求められることがあります。
判断基準と選び方のポイント
どちらを取るべきか迷ったら、次の基準で判断してください。
- 元請として下請総額が4,000万円(建築一式6,000万円)未満 → 一般建設業
- 同額以上を下請に外注予定 → 特定建設業
特に「自分は常に下請だから」として特定許可を必ず取得する必要はありません。
実際、大多数の専門工事業者は元請仕事をほとんど行わないため、一般許可だけで十分な場合が多いです。
ただし、今後元請比率を増やしたり公共工事への参入を考えている場合は、初期から特定許可体制で準備する方が運営上有利です。
許可更新と提出義務のスケジュール管理
建設業 許可 取得条件を満たして許可を受けた後も、適切な更新管理と報告義務の履行が必要です。これを怠ると、行政処分や許可失効につながる恐れがあります。以下では、実務に即したスケジュール管理ポイントを整理します。
許可の有効期間と期限管理
建設業許可の有効期間は5年間です。
更新申請は満了日の3か月前から30日前までに行う必要があります。この期間を過ぎると自動的に失効し、新規扱いで再申請しなければなりません。
有効期間の例として、許可日が2020年4月1日の場合、有効期限は2025年3月31日までです。したがって、2025年1月1日から3月1日までの間に更新申請を完了させる必要があります。休日の取り扱いは自治体によって異なるため、群馬県の場合は「許可通知書記載の提出期限」を必ず確認してください。
更新申請のタイミングと手順
建設業許可が正常に更新されるためには、以下の手順を踏む必要があります。
-
書類準備(満了日の4か月前〜)
財務諸表・決算変更届・社会保険加入資料など最新情報を更新します。 -
申請書作成(3か月前)
指定様式で作成し、印鑑・添付資料確認を徹底します。 -
提出および審査(30日前まで)
紙提出が原則で、手数料は知事許可で約5万円程度です。
年次報告(決算変更届)
毎年事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届を提出する必要があります。
この報告は各許可当局に財務状況を通知するもので、未提出の場合は行政指導が行われる可能性があります。
主な添付書類は以下です。
- 貸借対照表および損益計算書
- 工事経歴書および完成工事高内訳書
- 事業税納税証明など
変更届と報告義務
許可を受けた後に組織構成や運営情報に変更があった場合は、即座に報告する必要があります。対象項目は以下です。
- 役員・取締役の変更(退任・就任を含む)
- 商号・住所の変更
- 専任技術者の交代または不在の発生
- 営業所の新設・廃止・移転
- 業種追加申請
変更発生日から原則として2週~30日以内に報告が求められ、遅延した場合は行政警告の対象となります。
更新・決算報告・変更申告のスケジュールは必ずカレンダーで管理してください。
特に期限前の書類準備を遅らせると「新規扱い」再入場リスクがあるため、少なくとも半年前からチェックを行うことが安全です。
建設業 許可 取得条件のまとめと実務対応のポイント
ここまで見てきたように、建設業許可を取得するためには「経営業務の管理責任者」「専任技術者」「誠実性」「財産的基礎」「社会保険」「欠格要件」の6つを満たすことが基本条件になります。これらはすべて、事業を継続的・安定的に行う能力があるかを確認するためのものです。
特に初めて申請する方は、証明書類の整備や経験証明の書き方でつまずくことが多いです。経営業務管理責任者としての経験要件を満たすために、どんな書面を準備すればよいか、また専任技術者として認められる資格・実務年数の整理を早めに行うことが成功への第一歩になります。
申請が複雑に感じられる理由は、条件の判断基準が「形式的」ではなく「総合的」に審査される点にあります。よって、単に要件を説明的に読むだけではなく、自社の状況を客観的に照らし合わせることが欠かせません。
書類作成や制度理解に時間を取られるよりも、事業の方向性に集中することが理想です。そのため、行政書士や専門家のサポートを受けながら計画的に進めることが、結果的にコスト・時間の両面で効率的になります。
最終的に、「建設業 許可 取得条件」を正しく理解し、段階的に準備を進めることで、申請却下のリスクを減らし、スムーズな許可取得につなげられます。制度の複雑さに不安を感じていた方も、今は何から始めるべきかが明確になったのではないでしょうか。どんなに小さな一歩でも、法令を正しく理解して行動することが、安定した事業継続への最短ルートになります。


