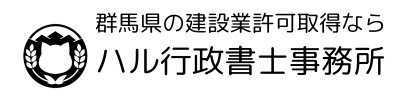建設業 許可 500 万円基準を完全解説 法改正対応で失敗しない許可取得ガイド
工事の見積が500万円を少し超えそうな時、「この場合は許可が必要?」と迷った経験はありませんか。金額の基準や算定方法を誤解してしまうと、意図せず無許可施工にあたるリスクもあります。このページでは、500万円基準の正しい意味と判断ポイントを整理し、あなたの現場が法的に安心して動ける状態を作るための道筋をお伝えします。
建設業許可における「500万円」基準の正確な意味と法的位置づけ

建設業 許可 500 万円の根拠は建設業法第3条にあり、許可が必要となる工事規模を金額で区切るための中核基準です。この条文では、建築一式工事以外の工事について「1件の請負代金が500万円(税込)以上なら許可が必要」と明確に規定しており、建築一式工事の場合は1,500万円(税込)以上、または延べ面積150㎡を超える木造住宅の新築で許可が必要となります。建設業法改正の影響でこの基準値自体は変更されていませんが、特定建設業の金額や技術者配置要件など別分野が改正されたことで、この500万円基準の解釈だけを誤って理解する事例が増加しています。以下、工事種別ごとの許可基準を整理しました。
| 工事種別 | 許可必要金額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 建築一式工事 | 1,500万円以上 または木造150㎡超の新築 |
基準を満たせば許可必須 |
| 建築一式以外 | 500万円以上 | 材料費・労務費等の総額で判断 |
| 軽微工事 | 上記未満 | 許可不要の工事区分 |
軽微な建設工事とは、建築一式工事であれば1,500万円未満かつ150㎡以下の木造住宅の新築、または建築一式以外で500万円未満の工事を指します。この範囲であれば許可不要ですが、あくまで「工事全体の総額(税込)」で判断する点が核心です。特に小規模工事の許可判断では「元請が材料支給だから安い」「部分修繕だから500万円に入れなくてもいい」といった着想がしばしば発生するため、注意が必要です。誤解されやすい落とし穴としては三つが代表的です。
- 消費税抜き価格で判定してしまい、税込では500万円を超えているケース
- 一体の工事を複数契約に分割し、見かけ上500万円未満にする行為(脱法行為として違法になり得る)
- 追加工事を別契約扱いにして、最終総額で500万円を超えるのに許可不要と誤認する事例です。この三つは行政指導や無許可工事のリスクに直結するポイントであり、500万円基準の正確な理解が必須です。
「500万円」判定のための金額算定方法と具体的な注意点

建設業 許可 500 万円の判定では、まず税込金額で判断する点が最重要になります。税抜499万円でも、消費税を加えた最終的な請負代金が500万円を超えれば許可が必要になります。行政の実務でも「税込で500万円以上かどうか」が基準として用いられるため、見積段階から税込総額を明記しておかないと誤判定が起きやすいです。特に元請・下請ともに税抜表示に慣れている場合、契約書と請求書の税込表記に差異が出てトラブルになるケースが少なくありません。材料費・労務費・機械使用料を含めた「工事の総額」が請負代金となるため、材料支給の場合でも市場価格+運送費を加算して判定する必要があります。自己調達か支給材かに関わらず、工事実態として必要となる費用は全て算入されるのが原則です。以下の要素は、金額判定時に必ず確認する必要があります。
- 消費税を含めるかどうか
- 材料費の調達形態(支給・仕入)
- 労務費の計上基準
- 機械・仮設資材費用
- 見積書・請求書の一致確認
この五つが曖昧なまま契約を進めると、500万円基準の誤判定だけでなく、後から施工体制確認や元請の内部審査で問題になる場合も発生します。少なくとも見積書・契約書・請求書の構成項目は揃えておき、材料費や労務費が抜け落ちていないかのチェックを推奨します。最後に、金額を500万円未満に見せかける目的で契約を複数に分割する行為については明確に注意が必要です。建設業法では、実質的に一体の工事であるにもかかわらず合理性のない分割を行えば脱法行為として違法と判断され得ます。一方で、目的・仕様・工期・発注者が明確に独立している工事は分離契約が認められますので、実務では図面・発注書・見積根拠を通じて独立性を証明できるかが鍵です。
契約を分割して「500万円未満」に見せる行為の可否とリスク

建設業 許可 500 万円の判定で最もトラブルが多いのが、契約を複数に分割して金額を小さく見せるケースです。結論から言うと、実質が一体の工事を分割して500万円未満に見せる行為は脱法行為として違法です。分割支払での判定も同じで、支払方法が月払い・段階払いでも、工事全体の総額(税込)で判断されます。一方、目的・仕様・工期・発注者が明確に別れている独立した工事であれば、別契約として扱うことが認められます。追加工事の取り扱いでは、後から契約した分も含めた最終総額で判断するため、当初は軽微工事であっても追加分を合わせて500万円を超えれば許可が必要になります。
| 行為分類 | 適法・違法 | 判断基準 |
|---|---|---|
| 正当な分割 | 適法 | 目的・仕様・工期・発注者が明確に独立している |
| 見せかけ分割 | 違法 | 実質が一体の工事を分割し金額を500万円未満に調整 |
| 追加工事の扱い | 総額で判断 | 当初契約と追加分を合わせた最終金額(税込)で許可要否を決定 |
見せ金のリスクを伴う偽装申請や、意図的な過少契約はすぐに発覚します。行政は見積書・契約書・図面・現場写真など複数資料を突き合わせるため、不正申請が発覚した事例も珍しくありません。無許可施工が確認されれば、建設業法違反として3年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象になり、法人には両罰規定により罰金刑が科される可能性もあります。特に偽装申請の罰則は厳しく、営業停止や信用失墜まで波及するため、契約分割での回避は絶対に避けるべきです。
500万円未満の工事でも守るべき建設業者の義務

500万円未満の軽微工事であっても、建設業者として守るべき最低限の義務は変わらない点が最重要です。まず誤解しやすいのが技術者配置で、主任技術者や監理技術者の選任義務は「建設業者」に課されるものであり、許可を持たず軽微工事だけを行う者に一律で課されるものではありません。一方、許可業者は工事規模に応じて専任技術者の配置要件が求められ、一定規模では現場に常駐する専任義務が発生します。500万円未満であっても技術的な責任体制を明確にしなければ、元請審査や取引の信用面で問題が生じやすいです。500万円未満の工事でも契約書の必要記載事項(工事内容・金額・工期・支払条件・瑕疵対応など)を整備することは不可欠です。建設業法上、施工体制台帳の義務は4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)の元請工事にのみ適用されるため、軽微工事では作成義務はありません。ただし、契約の透明性や下請とのトラブル回避のため、現場体制に関する最低限の書面管理は必要です。
- 契約書の作成と保存
- 技術者の適正配置
- 労災・社会保険の加入
- 安全管理・品質確保措置
最後に、建設業 許可 500 万円の基準と混同されやすいのが「財産要件の500万円」です。工事の許可要否を判断する500万円はあくまで税込の請負金額であり、財産要件で求められる500万円は自己資本や資金調達能力、または過去の施工実績によって示す金銭的信用です。この二つはまったく別物ですので、金額が500万円未満の工事だけを行うと財産要件と無関係になるわけではない点を必ず認識してください。
財産要件としての「500万円」—自己資本と資金調達能力の確認方法

建設業 許可 500 万円と聞くと「手元に現金500万円がないと許可が取れないのでは?」という質問が多いですが、結論から言えば現金保有は必須ではありません。財産要件は次の三つのいずれかを満たせば足ります。
- 資本金で満たす基準としての自己資本500万円以上
- 純資産と自己資本比率に基づく500万円以上の資金調達能力
- 直近5年以内に500万円以上の工事施工実績
自己資本は貸借対照表上の純資産であり、リースや借入のような負債は含まれません。個人事業主や新設法人でも、現金がなくても資金調達能力で要件を満たせる点が重要です。
| 基準項目 | 内容 | 証明手段 |
|---|---|---|
| 自己資本 | 純資産が500万円以上 | 決算書・貸借対照表 |
| 資金調達能力 | 500万円以上の資金を確保できる能力 | 残高証明、融資証明 |
| 施工実績 | 直近5年以内の500万円以上の工事実績 | 請負契約書・請求書 |
証拠書類の取得では、まず決算書で純資産額を確認し、自己資本が足りなければ残高証明の取得方法を使うケースが多いです。銀行口座に500万円を一定期間置く必要はなく、発行時点の残高が確認できれば足ります。新設法人や個人事業主は銀行融資を使う場合の注意として、金額が明記された融資証明を提示できるかが重要です。施工実績で満たす場合には契約書と請求書に金額・工期・発注者が明確に記載されているかを必ず確認してください。実務では、資本金で満たす基準をそのまま使うよりも資金調達能力でクリアするケースが最も多いです。純資産と自己資本比率が不足しても、残高証明や融資証明で補う方式が安定的です。また、銀行融資を使う場合の注意としては、一時的な借入で自己資本を膨らませたように見せる手法は認められないため、必要な書類を正確に揃えることが許可取得成功の鍵です。
建設業許可取得後に維持すべき管理義務と更新手続き
許可取得後の実務で最優先となるのは、毎事業年度ごとに行う決算変更届の提出です。提出期限は「事業年度終了後4か月以内」で、この期限を1日でも過ぎると行政指導の対象になり、累積すると許可取消しの原因にも直結します。決算書の整備方法としては、貸借対照表・損益計算書・工事経歴書などを年度ごとに正確に揃えておき、社会保険加入状況や役員・技術者の変更有無を同時に点検する方式が最も安定的です。特に書類作成チェックリストを事前に用意しておくと、年度末に必要項目を取りこぼさず処理できるため、実務負担が大幅に減少します。
- 毎年度決算変更届の提出(4か月以内)
- 更新申請(5年ごと)
- 社会保険等の持続的適正加入
- 許可票・公告等の最新化
許可更新の期限と手続きについては、建設業許可の有効期間が5年で、満了日の30日前までに更新申請を済ませる必要があります。更新申請を忘れると自動的に許可が失効し、無許可状態での工事が即座に建設業法違反となるため、5年周期の管理は絶対に欠かせません。更新準備では、直近数年の決算変更届が期限内に提出されているか、技術者や役員体制が要件を満たしているか、社会保険加入状況に問題がないかを優先的に確認する必要があります。不備があるまま更新に入ると、補正指示が繰り返され最悪の場合は許可取消しの原因となるため、年度中から書類管理と台帳整備を習慣化することが最も現実的な対処です。また、許可取消しの原因と対処を考える際には、届出漏れ・不正申請・社会保険未加入の長期化などが主要リスクとして挙げられるため、実務では毎年内部点検表を作成し、定期的に確認する方式が安定的です。この流れを押さえておけば、建設業 許可 500 万円基準をクリアして取得した許可を長期的に維持し、信頼性向上につながるステップへ自然に繋がることができます。
「500万円」基準を正しく理解して信頼を築く建設業経営へ
建設業 許可 500 万円の基準を正しく運用することは、法令遵守だけでなく取引先からの信用を確立する最短ルートです。許可を取得すると、公共工事の入札資格に必要な前提条件を満たせるようになり、さらに経営事項審査との関係でも評価点が加算されるため、受注機会が一気に広がります。公共性の高い案件や大手元請との取引では、許可の有無そのものが信用判断の入口となるため、500万円基準を正確に理解し、軽微工事からのステップアップを見据えて許可取得後の成長戦略を持つことが重要です。一方で、この基準を誤って軽視すると、気づかないうちに無許可営業に該当し、刑事罰や信用失墜につながる重大リスクを抱えることになります。特に500万円(税込)超の契約かどうか、材料支給を含む総額として判定できているか、追加工事を合算して確認しているかは各現場でチェックすべき核心です。無許可営業を避けるチェック項目を定期化することだけでも、財務・技術・体制の整備と合わせて経営の安定性が大幅に向上します。
建設業 許可 500 万円の正しい理解が経営リスクを防ぐ鍵です
ここまで見てきたように、「500万円」という基準は単なる金額ではなく、建設業許可が必要かどうかを見極めるための法的なラインになります。請負代金の合計には、材料費や消費税も含まれること、また契約を細かく分割して500万円未満に見せるような行為は、軽微な工事の範囲から外れ、違法行為となる可能性が高い点を確実に理解しておく必要があります。
一方で、500万円未満であっても主任技術者の配置や契約書の作成義務など、遵守すべきルールは存在します。つまり、「許可が不要だから自由」ではなく、「金額に関わらず建設業法に基づいた適正な管理」が義務となります。
初めて許可取得を考えているリフォーム業者や一人親方の方にとって、こうした基準を正確に理解することは「無許可施工のリスクを避ける第一歩」です。
もし自社の工事内容が500万円基準の対象になるのか判断が難しい場合は、申請条件や金額の解釈を専門家に確認することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
要するに、「500万円」という基準を正しく捉えることが、法律遵守と信頼経営を両立するための最も確実な方法です。複雑に感じる部分こそ丁寧に整理し、安心して次の工事へと進んでくださいね。