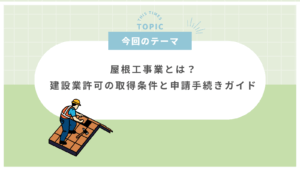とび・土工工事業だけでは足りない?解体工事業で必要な建設業許可と取得方法を解説
解体工事業の定義と範囲
解体工事業とは
「解体工事業」とは、建築などを取り壊す工事を行う業種です。
建設業法では、2016年6月の法改正により新たに登場した業種です。
つまり、現在では解体を専門に行うには、専用の建設業許可(解体工事業)を取得する必要があります。
具体的な工事例
以下のような工事が「解体工事業」に該当します。
- 木造・鉄骨造・RC造などの建物の全解体
- 重機や足場を使った大規模解体工事
解体工事業の特徴と他業種との違い
以前は一式工事や各種専門工事業として扱われていましたが、現在は解体工事業は独立した業種となり、専用の許可が必要です。
例えば、建物の解体だけを請け負っていて「とび・土工工事業」の許可しか持っていない場合は、法令違反とみなされる可能性があるため注意が必要です。
もっとも勘違い多いのは、解体工事業とは「基本的に全解体のとき」に該当する業種ということです。建物の一部だけを壊すだけならとび・土工、管工事、内装工事などに分けられます。要は、更地にするのが解体工事業ということです。
少し専門的な言い方をすると、一式工事で建てたもの(住宅など)を壊すのが解体工事業です。ですが、全解体後に更地にして、さらに新築するまでを請負場合は建築一式工事に該当します。また、スケルトン解体までしてリフォームする場合も建築一式になったりします。
このように非常に判断が難しいのが解体工事業。解体業者さんの工事経歴書を作っても、行政書士から見ると、建築一式やとび土工などが実態で解体工事は1件もやっていないということもあります。
建設業許可取得の重要性
法令遵守の観点
建設業法では、工事1件の請負代金が500万円(税込)以上の場合は、解体工事業の建設業許可が必要です。
無許可で請け負った場合、営業停止や罰金、入札資格の停止などの重大なペナルティがあります。
また、廃棄物処理法や石綿障害予防規則など、他法令との連携が求められるのも解体工事の特徴です。
許可取得のメリット
- 公共工事や大手元請案件への参入が可能になる
- 社会的信用の向上につながる
- 顧客への安心感と信頼性をアピールできる
- 不許可による違反リスクを回避できる
解体工事業の許可申請手続き
必要書類と申請手順
建設業許可の申請には、以下のような書類が必要です。
- 建設業許可申請書(様式第1号など)
- 経営業務の管理責任者に関する証明書類
- 専任技術者の資格証明(解体工事実務経験、施工管理技士など)
- 財務書類(直近の決算書など)
- 営業所の使用権を証明する資料(賃貸契約書など)
- 納税証明書、登記事項証明書 等
申請時の注意点
- 専任技術者には、原則として解体工事の実務経験が必要
- 解体に関する公的資格(例:施工管理技士)の保有も有利
- 500万円以上の自己資本または預金残高の証明
- 社会保険・労働保険の加入状況も審査対象になる
まとめ:専門家による支援の重要性
複雑な申請プロセス
解体工事業では、とくに「実務経験」の証明や、他業種との境界線の判断が難しい場面があります。
許可を取っているつもりでも、該当工事が別業種扱いと判断される可能性もあるため、正確な知識と書類作成の精度が求められます。
行政書士に依頼するメリット
申請に必要な要件や証明方法を正しく見極め、書類作成や申請窓口とのやりとりまで丁寧にサポートします。
当事務所では、群馬県内を中心に多くの建設業許可の申請を手がけており、解体工事業特有の課題にも柔軟に対応。
「うちの業務内容は、解体工事業の許可が必要なのかな?」
そんな疑問をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。現場実情に即したアドバイスで、安心・確実な許可取得をサポートします。
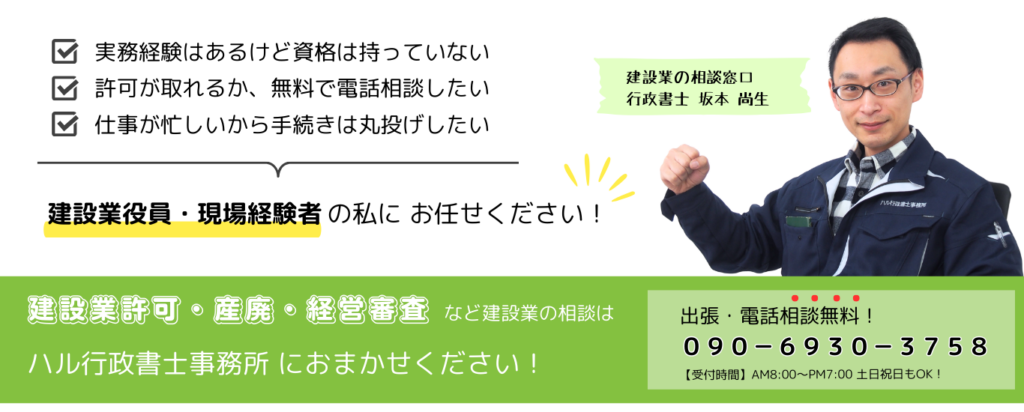
注意:法律・制度は改正される可能性があります。本記事の内容は最終更新日時点のものです。最新かつ正確な情報については、関係機関への確認や専門家へのご相談をおすすめします。
また、本記事は群馬県を基準に執筆しており、他地域では異なる場合もありますのでご注意ください。
当事務所では、常に最新の情報提供に努めております。ご不明点やご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。