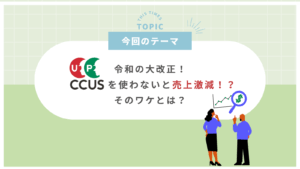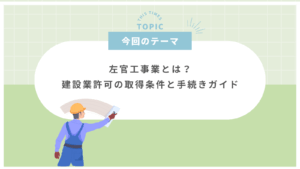鋼構造物工事業とは?建設業許可の取得条件と申請手続きガイド
~ 鉄骨・鉄塔・門・看板・大型架台などの施工に関わる方向けに、業種の定義や許可の要点を解説 ~

鋼構造物工事業の定義と範囲
鋼構造物工事業とは
鋼構造物工事業は、鋼材を使用して構造物を加工・組立・設置する工事を対象とする業種です。
建設業許可の業種区分において、「形鋼、鋼版等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事」と定義されており、主に鉄骨・鋼製の構造物や大型の金属製設備などが対象になります。
※国土交通省中部地方整備局 建設業許可の業種区分(PDF)
具体的な工事例
- 鉄骨工事(製作・組み立て)
- 鉄塔・送電塔・看板の設置
- 水門の設置
- 鋼製階段・架台・デッキの設置
- ガスなどの貯蔵用タンク設置工事
特徴と他業種との違い
鋼構造物工事業のキーワードは「鋼材で構造物をつくる and 取り付けること」です。
類似工種との違いを整理すると、以下のようになります。
- とび・土工工事業:看板の設置、鉄骨の組立や仮設足場などが含まれるが、「恒久的な構造物の施工」は鋼構造物工事に該当
- 鉄筋工事業:鉄筋を“構造材として埋め込む”工事で、建物の骨組みそのものをつくる鋼構造物とは異なる
- 板金工事業:薄板金属(屋根・外壁材など)の施工が対象。構造物の構築は含まない
構造的な役割や使用材料の厚み・サイズで区分が変わることが多いため、施工実態に合わせた判断が重要です。実務的には「看板の設置」をされる業者さんで鋼構造物、とび・土工、内装工事どれで許可を取得するかを悩むことが多いです。鋼構造物工事は施工管理技士などの資格で取れないことが多く、実務経験を証明するケースが多いのも特徴です。
建設業許可取得の重要性
法令遵守の観点
鋼構造物工事は、1件あたりの請負代金が500万円(税込)以上となる場合、建設業許可が必要です。
工事の規模が大きくなりやすいため、知らずに無許可で施工してしまうと、重大な法令違反となる可能性があります。
許可取得のメリット
- 鉄骨工事や架台設置などの大型案件に正式に対応できる
- 公共工事・インフラ関連の発注に参入できる
- ゼネコン・設備業者との取引で有利になる
- 技術力と信頼性を対外的にアピールできる
鋼構造物工事業の許可申請手続き
必要書類と申請手順
- 建設業許可申請書(様式第1号など)
- 経営業務の管理責任者の経験証明書類
- 専任技術者の資格証または10年以上の実務経験証明
- 財務書類(貸借対照表・損益計算書など)
- 営業所の使用権を証明する書類(登記簿謄本・賃貸契約書など)
- 納税証明書、登記事項証明書 等
申請先は知事または国土交通大臣で、許可取得までには1〜2ヶ月程度かかります。
申請時の注意点
- 自己資本または預金残高で500万円以上の資力を証明
- 専任技術者の常勤性・実務経験または資格の証明
- 経営業務の管理責任者の要件(5年以上の経験など)を満たすこと
- 社会保険・労働保険への加入が審査対象となる
まとめ:専門家による支援の重要性
複雑な申請プロセス
鋼構造物工事業では、「鉄骨の製作をするのか」「とび土工とどちらが近いか」など、業種区分に迷うケースもよくあります。
また、製作工場と現場施工を分けている事業者では、実績の整理・証明も複雑になりがちです。
行政書士に依頼するメリット
当事務所では、鋼構造物工事業の許可取得を多数サポートしており、業種の線引きや実務経験の整理も含めて丁寧に対応しています。
現場での施工内容や契約形態をヒアリングし、最適な形での許可申請を進めますので、「うちの仕事、鋼構造物にあたるのかな…?」という段階からでも、お気軽にご相談ください。