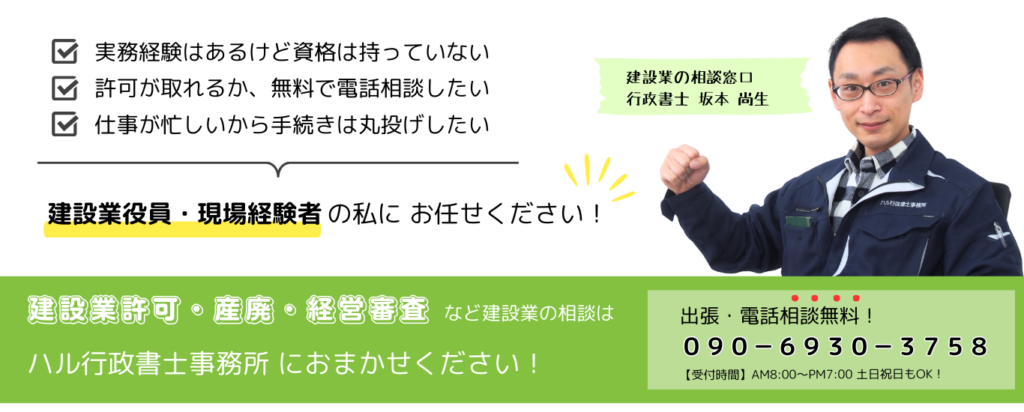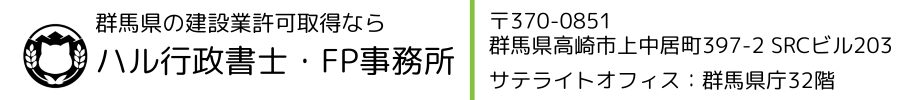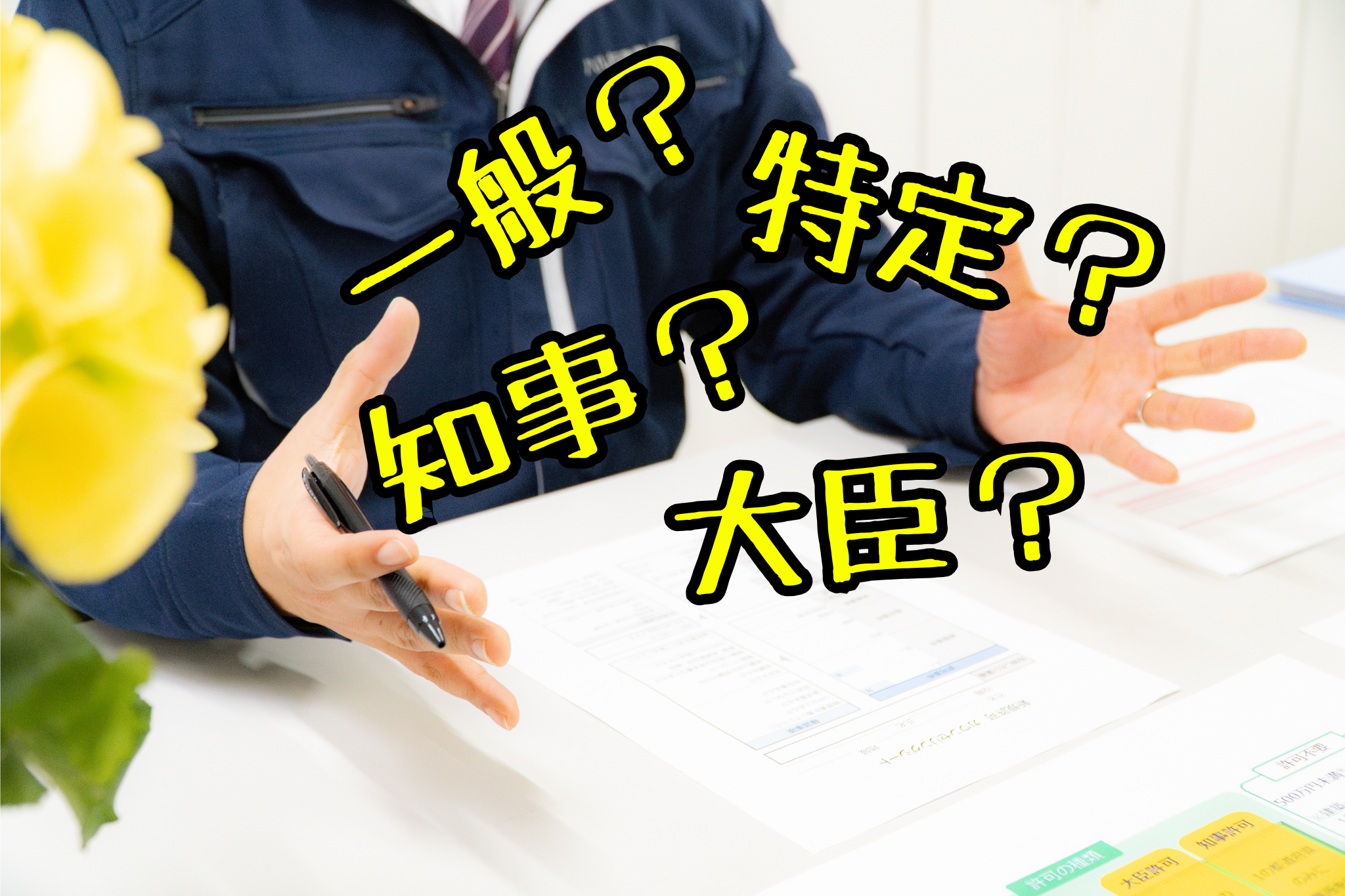建設業許可には一般と特定、知事と大臣の4つの組合せがあります。大臣許可を検討する会社はまれで、県知事×一般と特定かのどちらかを選ぶことになります。行政書士は法律要件を教えてくれますが、なぜこの区分けがあるのかや経営上の注意点までは意外と知りません。
当事務所も特定許可を取得しているお客様も多くいます。一般解説は他事務所の記事に任せて、なるべくリアルな話をしていきたいと思います。
誰を守りたいかで変わる
どんな会社が特定許可を持っているのか
法律上は下請に出す金額が5,000万円以上だと特定許可は必要です。(令和7年2月以降) この金額はインフレなどに合わせて変わるので、1年後には変わっている可能性もあります。
ポイントは下請けに出す金額という点です。
つまり、大規模な工事を請負う「元請」になりたいなら必要ってことです。公共工事の入札参加条件でもAクラスでは特定許可を持っていることを条件にしていることも多くあります。
当事務所の顧客でも特定許可を持っているのは公共工事を主力にしている会社、民間工事でも大規模工事が多い会社がほとんどです。
一般許可は「発注者」を守りたい
一般と特定の違いがなぜ発生するのかは、国が何をしたいかを知れば超カンタンです。
まずは一般許可を見ていきましょう。
建設業法は「〇〇を守るために悪い業者を取り締る」ためのルールです。
一般許可の〇〇は発注者、分かりやすく言うとお施主さんです。
なので、請負代金が500万円以上で許可が必要になります。
しかも税込みです。税抜きで455万円以上ならアウトです。
「 材料費は別途支給」は危険!
「うちは500万円以上なんて工事ねぇし関係ねぇな」

そう思った社長、危険!!
請負代金には材料代もカウントされます。注文書など見て「材料費は別途支給」となっていたら計算してみてください。注文書の代金が400万円…支給されている材料が200万円なら400万+200万円=600万円で違法です。
なぜかというと、注文者を守りたいので穴をふさいで、なるべく法律にひっかかるようにしているからです。役所が具体ケースで悩んだときにはお施主さんが有利になる方で判断することが多いでしょう。
私は「社長、労基署は従業員が有利になるように言いますよね、それと同じですよ」と身近な例で説明しています。
この考え方は意外に知られていません。建設業許可を新規取得するとき、材料費別途支給と書かれた資料を出してしいまい、役所からの質問に四苦八苦している行政書士を見かけます。
特定許可は「下請業者」を守りたい
特定許可は注文者に加えて、下請業者を守るためにあります。
下請業者が工事代金を確実に貰えるようにしたいというのがポイントです。
特定許可の条件を見ても「財務状況が良いかどうか」ばっかり書いてあります。
逆に言うと「下請業者が困らないなら特定許可じゃなくてもいいよ」ってことです。
例えば、下請に6,000万円工事を発注する場合には特定許可が必要ですよね。でも、元請が材料費3,000万円を購入して下請に支給するなら下請は困らないのでOKよってことです。
特定は上位互換のようで違う
許可としては「別々」
特定許可は一般許可の上位互換という覚え方はだいたい合っています。
だから、特定許可にしておけば安全かというと話は変わってきます。
実際に発行されてくる建設業許可証を見てもらうと、許可証は一般と特定は別々です。
あくまで一般は一般、特定は特定という扱いです。
しかも同じ工種で一般と特定の両方を持つことはできません。
といっても、これでどんなことが発生するか分からないですよね。
具体例を入れていきましょう。
一般許可から特定許可はスムーズ
一般許可から特定許可は法律で出来ると書かれています。
もちろん財務状況や1級技術者など揃えるのは大変なので「難しい」と説明されます。
でも、手続きとしては結構シンプルです。
特定許可から一般許可は危険がともなう
ネット記事を見ると「カンタンだ」と書くものが多くありますが、そうでもありません。
テクニカルな話ですが、特定から一般にできるとは書いていません。
びっくりしますよね。
ということは、一度特定許可を廃止して、一般許可で取り直すことになります。気付いた方もいるかもしれませんが「建設業許可を持っていない空白期間が発生する」わけです。公共工事や大手などコンプライアンスが求められる取引では致命的です。
お客様とは時期を綿密に打合せした上で行っています。
許可の 空白期間を無くすためには
特定許可はただ技術者がいればいいだけではなく、経営状況によっても失われるリスクがあります。万が一、そうなった場合には1ヶ月程度の空白期間が生まれてしまいます。せめて、建設業許可がある状態にしておくにはどうしたらいいでしょうか?
答えは、一般許可と特定許可の両方を持っておくこと。
簡単にいうと、建設業許可は工事の種類ごとに取得することを利用します。例えば建築一式は特定許可、塗装工事は一般許可で取得しておきます。建築一式が失われている状態でも、一般許可は残ることになります。
もちろん、一定金額やm2以上の建築一式の工事は請負えませんが、建設業許可は持っている。取引関係で建設業許可があればよいことも多くあるのでリスクは低減します。
ただし、この手法は事務が煩雑になりますし、費用も増えます。法律的な扱いも複雑になってきます。特定許可はコストが増加するのは間違いないので経営判断が分かれるところでしょう。
こういった処理は意外にも行政書士は苦手です。建設業に例えるなら、行政書士は「新築工事」はできても「増改築・リフォーム」は苦手だからです。なぜなら「手引き」「しおり」など参考資料が圧倒的に少ないからです。このタイミングで専門の行政書士事務所に切替えする検討も必要です。
気軽に特定を提案する行政書士は要注意
「特定許可がダメになっても、一般許可に自動的に切替わりますから!」
このように他事務所から説明されてきたというご相談者もいました。
そんなことはありません…。
当事務所では毎年の決算状況を見て財務条件など要件を満たしそうかもチェックしています。経営リスクもしっかりとご案内しています。許可をとったら終わりではありませんのでご安心ください!