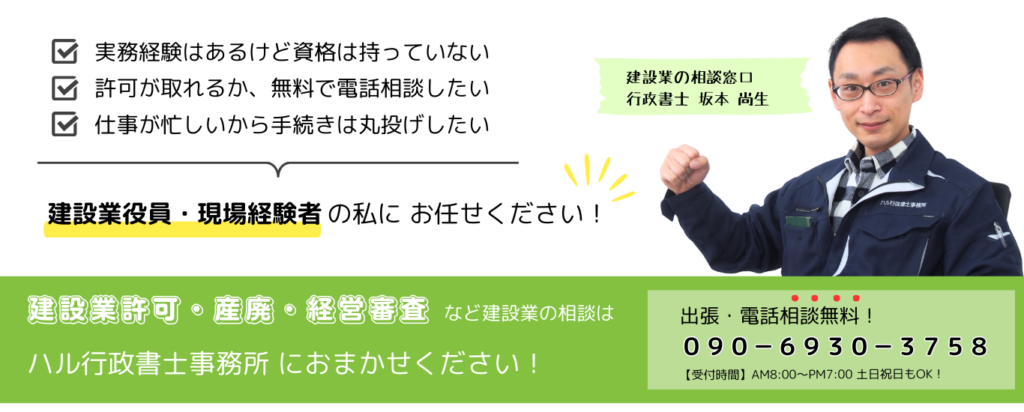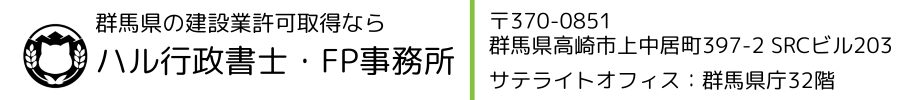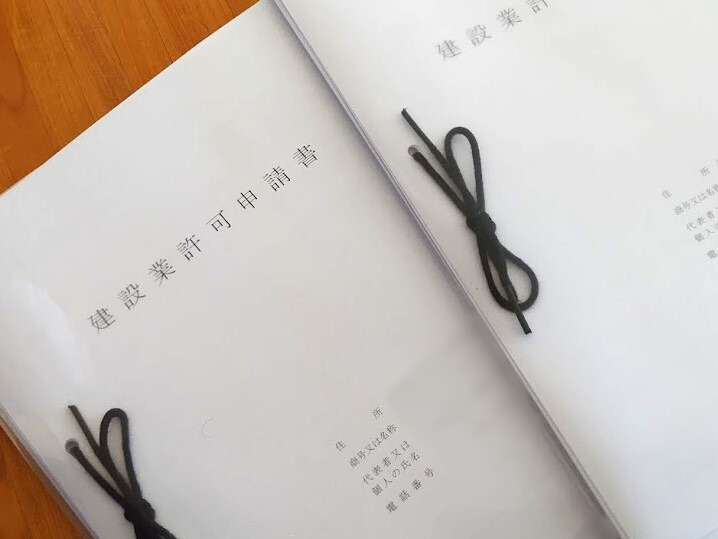建設業を営むには、必ず建設業許可が必要?
建設業許可が必要になるのは、一定規模以上の工事を請け負う場合です。軽微な工事の場合は許可を受ける必要がありません。
しかしながら、近年は業者間の競争が激しく、建設業許可が不要な工事の場合でも、建設業許可を取得している事がメリットとなり、受注につながるケースも増えています 。
この記事では、建設業許可取得のための要件とメリット・デメリット、申請までの流れをわかりやすく解説していきます。
建設業許可とは
建設業許可とは、建設事業者が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上又は延べ面積が150平方メートル以上の木造住宅工事)の工事を請け負うために必要となる許可のことです。ただし、軽微な工事のみを請け負う場合は、許可を受ける必要はありません。
許可のいらない軽微な建設工事とは?
軽微な建設工事とは、
〇建築一式工事の場合
・工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事
・延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
〇その他の建設工事
・工事1件の請負代金が500万円未満の工事
建設業許可の必要な工事を無許可で請け負った場合、建設業法違反で懲役刑又は罰金刑の対象となります。
また、建設業許可のない業者に対して、下請に出すことが出来る工事は「軽微な建設工事」のみで、請負代金500万円以上で下請に出すと、建設業法違反となり営業停止処分などを受けるおそれがありますので注意が必要です。
建設業許可を取得するメリット
大規模な建設工事を請け負うことができる
建設業許可を受けていれば、500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上又は延べ面積が150平方メートル以上の木造住宅工事)の工事を請け負うことができるように。
請負代金の制限なく建設工事を受注・施工できるようになり、受注の拡大につながります。
社会的信用の向上
建設業許可を取得するためには、様々な厳しい要 件があります。
建設業許可を取得している業者は、それらをクリアしているため、対外的な信用度が向上します。
また、金融機関や保証協会からの信用も得られやすくなるので、融資を受ける際、資金調達をする際にも有利になるといえます。
公共工事入札に参加できる
公共工事とは、市や県、国から発注される工事のことです。 工事は税金により行われるため 、信用力と施工力のある適正な建設業者に発注する必要があります。
そのため、公共工事の入札に参加するためには、建設業許可を取得していることが必須とされています。
技能実習 ・特定技能実習生を雇用できる
技能実習制度は、日本の技術や知識を発展途上国へ伝え、母国の発展に貢献することを目的としています。実習生を受け入れることで国際貢献を果たしつつ、現場の技術力向上や異文化交流の機会を得ることができます。
また、建設業の現場では、人手不足が深刻な問題になっております。
人材の確保の一つの方法として、特定技能実習生の受け入れという方法があります。
どちらの場合も建設業許可が要件となっております。
建設業許可を取得するデメリット
建設業を取得することで、大きなメリットを得られますが、以下のようなデメリットが発生する場合もあります。
- 事業年度ごと に決算変更届 を 提出する必要がある
- 5年に一度の更新手続きが必要で、忘れると許可がなくなってしまう
- 用意する書類が膨大で、申請までに時間と手間がかかる
- 自分の行っていた仕事と違う業種で申請してしまった
建設業許可を取得するための手続きや、毎年の届出など大きな事務負担が生じてしまいます。
手続きを任せられる、建設業に強い行政書士に相談するとよいでしょう。
建設業許可を取得するための6つの要 件
建設業許可を受けるためには、次の6つの要 件を満たしている必要があります。
要件 ① 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有していること
一般的な要件は、「常勤役員等のうちの1人が、建設業に関し、経営業務の管理責任者(経管)としての経験が5年以上あること」です。
具体的には、法人の役員や個人事業主として経営業務を行っていた経験が挙げられます。
管理責任者としての経験がなくても、場合によっては要件を満たせることも。
迷ったら一度専門家に相談してみましょう。
要件 ② 専任の技術者を有していること
各営業所に常駐し、常勤で働く従業員のうち1名以上が以下のいずれかの要件 を満たしている必要があります。
<一般建設業許可の場合>
- 許可を受けようとする業種に対応した国家資格を有する
- 許可を受けようとする業種に対し3~5年の実務経験を有し、指定学科を卒業している
- 学歴・資格を問わず10年以上の経験がある
- 国土交通大臣特別認定者
<特定建設業許可の場合>
- 許可を受けようとする業種に対応した国家資格を有する
- 一般建設業許可の専任技術者要件を満たしており、2年以上の指導監督的実務経験を有する(元請工事で、請負金額4500万円以上の工事が対象)
- 国土交通大臣特別認定者
※土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種については、1もしくは3に該当しなければなりません。
また、事業所が複数ある場合には、全ての事業所に専任の技術者を置く必要があるので注意しましょう。
要件 ③ 請負契約に関して誠実性を有していること
直近5年間で、建設業法、建築士法、宅地建物取引業法の規定により、免許取消処分や営業停止処分を受けていないことが要件 になっています。
法人、役員等(非常勤を含む)、個人事業主本人、支配人、営業所の代表者などが詐欺、脅迫、横領などの請負契約に関して不正又は不誠実な行為をすることが明らかな場合は、建設業許可を取得できません。
要件 ④ 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
<一般建設業>
次のいずれかに該当することが必要です。
- 自己資本の額が500万円以上であること
- 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
- 申請前の過去5年間許可を受けて継続した営業実績がり、現在群馬県知事許可を有すること
<特定建設業>
次の全てに該当することが必要です。
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
一般建設業と特定建設業のどちらかを取得するかで必要となる要件が変わってきますが、特定建設業は 難易度の高い要件となります。
要件 ⑤ 欠格要件に該当していないこと
欠格要件は11つの項目があり、そのいずれにも該当しないことが必要です。
- 破産者で復権を得ないもの
- 不正の手段で許可を受けた、又は許可を取り消されてから5年間を経過しない者
- 建設業法に違反して営業停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 請負契約に関し、不誠実な行為をしたことにより営業を禁止され、その禁止期間を経過しない者
- 禁固以上の刑に処せられ、又は建設業法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、暴力団対策法及び刑法の特定の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5年を経過しない者
- 暴力団員、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 申請者が未成年者で、その法定代理人が上記に該当する者
- 法人でその役員等、又は一定の使用人が上記に該当する者
- 個人でその支配人、又は一定の使用人が上記に該当する者
- 暴力団員がその事業活動を支配する者
- 許可申請中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき
要件 ⑥ 適切な社会保険等に加入していること
加入の対象となるのは、健康保険、厚生年金、雇用保険の3つです。
法人の場合、従業員数に関わらず健康保険・厚生年金への加入が必要となります。
個人の場合、常勤の従業員(事業主は除く)が5人以上で加入が必要です。
雇用保険は法人・個人問わず、週20時間以上働き、31日以上の継続雇用する見込みがある人を1人以上雇っている場合に加入義務があります。
建設業許可の区分と種類
建設業許可には次のような種類・区分があります。
大臣許可と知事許可
- 2以上の都道府県に営業所を設けている場合→国土交通大臣許可(大臣免許 )
- 群馬県内にのみ営業所を設けている場合→都道府県知事許可(知事免許 )
営業所が2つ以上の都道府県にあるかどうかで、免許の種類が変わります。
群馬県以外にも営業所がある場合には大臣免許、県内のみならば知事免許になります。
一般建設業と特定建設業
- 一般建設業の許可
特定建設業の許可が必要な工事を除く、建築一式工事の場合は1,500万円以上又は延べ面積が150平方メートル以上の木造住宅工事)の建設工事を請け負う場合に必要な許可 - 特定建設業の許可
建設工事の最初の注文者(発注者)から、直接に請け負った1件の建設工事について、下請代金の合計金額が 5000万円以上(建築一式工事では8 ,000万円以上)となる下請契約を締結して、下請負人に施工させる場合
特定建設業でポイントになるのは、請負金額には制限はなく、下請代金へ制限がかかっているところです。自社施工であれば請負金額の制限がないため、一般建設業許可でも問題ありません。
建設業許可の29業種の分類
建設業許可の業種は、2種の一式工事と27種の専門工事に分かれています。
2種の一式工事
・土木一式工事
・建築一式工事
27種の専門工事
・大工工事業
・左官工事業
・とび・土工工事業
・石工事業
・屋根工事業
・電気工事業
・管工事業
・タイル・れんが・ブロック工事業
・鋼構造物工事業
・鉄筋工事業
・舗装工事業
・しゅんせつ工事業
・板金工事業
・ガラス工事業
・塗装工事業
・防水工事業
・内装仕上工事業
・機械器具設置工事業
・熱絶縁工事業
・電気通信工事業
・造園工事業
・さく井工事業
・建具工事業
・水道施設工事業
・消防施設工事業
・清掃施設工事業
・解体工事業
自社が請負う工事がどの業種に該当するのか、どの業種で申請するべきなのか考えてみましょう。
建設業許可の有効期限
許可の有効期間は、許可を受けた日から5年間です。
許可年月日から5年後の応答日の前日に満了となります。(満了日が休日であっても、その日をもって満了となることに注意)
更新申請は、許可の切れる日の3か月から30日前までに手続きをしましょう。
提出期限の詳細については、許可通知書の下部に記載されています。
例:許可年月日が令和7年8月9日の場合、令和12年8月8日に許可が満了となります。
更新申請を令和12年7月8日までに行う必要があります。
建設業許可の取得にかかる費用
| 申請区分 | 知事許可 | 大臣許可 |
|---|---|---|
| 新規 | 9万円 | 15万円 |
| 更新 | 5万円 | 5万円 |
| 業種追加 | 5万円 | 5万円 |
(2025年2月現在)
知事許可の許可手数料は群馬県収入証紙で納入(消印等を押印しないこと)
建設業許可申請の流れ
申請先を確認する
建設業許可を 取ると決めたら、まず自社がとる許可の種類を決めます。
「知事許可」か「大臣許可」のどちらを取得するかによって異なります。
知事許可の場合は、各都道府県庁へ
大臣許可の場合は、国土交通省の各地方整備局へ
申請する必要があります。
許可申請区分を確認する
建設業許可には「知事許可か大臣許可か」「一般建設業か特定建設業か」「該当する工事の種類はどれか」など、自社に該当する区分を明確にしましょう。
許可申請書と必要書類を用意する
許可申請書の様式と、その他の必要書類については国土交通省や群馬県のページに記載がありますので漏れが無いよう書類を作成・資料収集します。
特に、取得要件を満たしているかの判断や 必要書類の有無、10年間の実務証明など ケースによって提出する書類が異なり煩雑です。
日々の業務の中で申請書類を作成することは本業に影響がでてしまいますので、
建設業に強い行政書士に相談することもおすすめします。
建設業許可取得への道筋と専門家サポートの重要性
建設業許可取得は、事業拡大や社会的信頼性向上の鍵となります。
しかし、許可取得には様々な要件や注意点があり、経営業務の管理責任者や専任技術者の確保、複雑な業界実態の理解、適切な申請手続きの実施など、クリアすべき点が多くあります。
これらの課題に適切に対応するためには、専門家のサポートが非常に有効です。
当事務所では、要件をクリアしているかの確認から申請書の作成 ・提出までトータルサポートいたします。
建設業許可申請でわからないことがあれば、ぜひ一度ご相談ください。